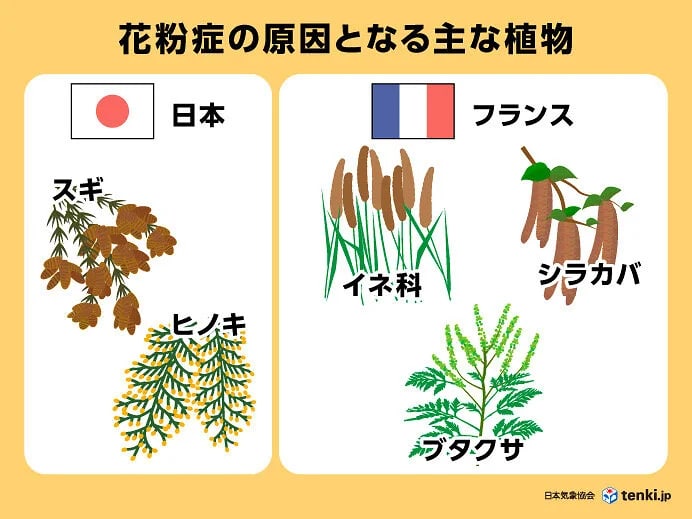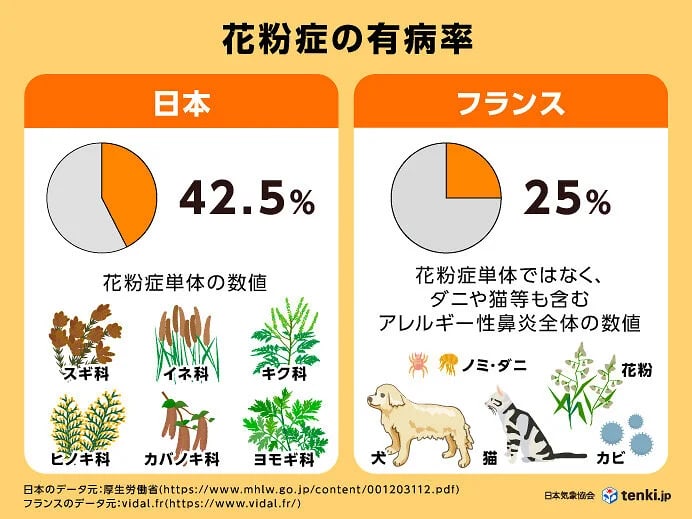私が医師になった30数年前は“不治の病”だった疾患が、
その後の医学の進歩で“治療可能な疾患”になった例がいくつもあります。
“隔世の感”という表現がありますが、
まあ、私自身、結構長く医者をやってきたんだなあ、と感慨深くなります。
ただ、そのような疾患は遺伝性の代謝異常が多く、
私のサブスペシャリティであるアレルギー疾患にはありません。
あまり詳しく知る機会がないため、
あえて自分で情報を取りに行かなければわからない分野です。
そんな中、解説記事が目に留まりましたので読んでみました。
<ポイント>
・がんゲノム医療の対象は成人が大半を占めるのに対し、遺伝性疾患に対するゲノム医療は、小児が対象になる。今後ますます疾患メカニズムの解明が進むにつれ、ゲノム医療の適用範囲は拡大していく。
・先天異常は、生まれてくる赤ちゃんのおよそ3~5%に見られ、乳児死亡の大きな原因の一つ。
・日本では、過去10年間で「次世代シークエンサー」「NIPT(非侵襲性出生前遺伝学的検査)」「PGT-M(着床前遺伝学的検査)」「PGT-M(着床前遺伝学的検査)」「エクソーム解析」等、小児遺伝性疾患に関する診断や治療が大きく進歩した。
・日本では196種類の疾患に対する遺伝学的検査が保険適用で実施されている。
・遺伝子やゲノムを詳しく調べる解析技術の進歩で、原因不明の病気の約半分が遺伝学的に診断できるようになり、病気の原因がわかることにより、その子どもに合った健康管理や治療方針を具体的に立てられるようになった。治療については大きな進展があり、一部の遺伝性疾患では、診断が早ければ早いほど効果的な治療が可能となった。
(例)軟骨無形成症(手足が短く、低身長になる特徴を持つ先天的な骨の病気):これまで生後数年してから治療が始まる選択肢に限定されてきたが、最近では、出生後数か月でも使える薬が登場し、診断後早期からの治療により、成長をより早期から助けることが可能になった。 (例)脊髄性筋萎縮症(筋力が弱くなり体の動きが制限される遺伝性疾患):以前は診断に時間がかかり、治療の開始が遅れることが課題だったが、現在は、拡大新生児スクリーニング検査の対象にこの疾患を含める自治体もあり、これにより、生後間もなく遺伝子検査による診断を目指せるようになった。その結果、筋力低下を防ぐ治療が早期から可能となり、子どもたちの生活の質を大きく向上させることが期待されている。 ・現在、約7,000種類の遺伝性疾患が知られているが、そのうち根本的な治療が可能なものは今のところ約200種類。
・診断を受けることに対して、不安や戸惑いを感じる方もいる。たとえば、「病気の名前がつくことでレッテルを貼られるような気がする」「治らない病気なら、診断する意味がわからない」という気持ちを抱えることもある。
・遺伝情報にはいくつか特徴がある。これらは、家族が診断を受けることに慎重となる要因にもなっている;
✓ 「原因を知りたい」と思う人にとって大きな助けになる。
✓ 現時点では根本的な治療法が見つかる可能性が低い。
✓ 知らなくてもよいと思っていた遺伝情報を予期せず知らされることもある。
✓ 家族全体に影響を与える可能性がある。
✓ 病気が将来発症するリスクを知る可能性がある。
✓ 一生変わらない情報である。
予想通り、日進月歩の分野ですね。
ただ、気になったのは、新しい医療技術が登場するときの宿命ですが、
「光と影」が発生すること。
私は30年ほど前、小児医療センターNICUに勤務していました。
医療技術の発達によりそれまで救命できなかった小さな赤ちゃん達が助かるようになった時代です。
肺胞サーファクタントの効果には目を見張るものがありました。
しかし一方で、救命はできたものの障害が残り、
自宅に帰れない赤ちゃん達もいました。
遺伝情報は病気の診断・治療に役立つことはもちろんですが、
似た遺伝情報をもつ家族に病気の影を投げかけることもあり得ます。
よかれと思って行った検査の結果を報告する際、
「知りたくなかった」
「知らなければよかった」
という反応が返ってくる可能性もあるのです。
その人の遺伝情報をすぐに全解明する技術の登場も間近。
その価値を生かすも殺すも、使う人間次第・・・ということになりますか。
▢ 小児遺伝性疾患に対する医療の過去・現在・未来~専門医が考える「紡ぐゲノム医療」とは?
ヒトゲノムが完全解読された今、遺伝子/ゲノム解析等を伴う「ゲノム医療」は遺伝性疾患の領域では欠かせない医療の一部となりつつあります。がんゲノム医療の対象は成人が大半を占めるのに対し、遺伝性疾患に対するゲノム医療は、お子さんが対象になる場合も少なくありません。また、今後ますます疾患メカニズムの解明が進むにつれ、ゲノム医療の適用範囲は拡大していくと予想されます。
こうしたゲノム医療の進展に伴い、小児遺伝性疾患の診断や治療はどのように変わってきているのでしょうか?また、今後どのように発展していくと期待できるのでしょうか?小児遺伝性疾患と小児遺伝医療の「これまで」と「これから」について、東京都立小児総合医療センター遺伝診療部臨床遺伝科部長の吉橋博史先生に詳しくお話をうかがいました。・・・
ーー小児遺伝性疾患の診断や治療は、10年前と比べてどのように進歩してきていますか?
10年前は、病気の原因がわからない子どもたちが多く、診断がつかないために、適切な健康管理や治療につながることが難しく、家族も不安を抱えながらの子育てが続いていたかもしれません。当時、一度にたくさんの遺伝子を調べることができる「次世代シーケンサー」という機器が、先駆的な大学病院やセンター病院の研究室で導入され、臨床の現場でも実装に向けて経験を積みはじめた頃でした。しかし、研究目的で次世代シーケンサーを利用できる施設は限られているうえに、研究目的にかなう条件を満たした方しか参加できないため、遺伝性疾患が疑われたとしても、遺伝学的に診断することは容易ではありませんでした。そのため、「いま検査するのは難しいのですが、5年後、10年後には環境が変わると思うので、そのとき、また考えましょう」と患者さんに説明し、将来の見通しをお伝えするにとどまることも少なくありませんでした。
日本では、過去10年間で小児遺伝性疾患に関する診断や治療が大きく進歩しました。2013年には、国内で妊婦血液を用いて胎児に染色体疾患(21トリソミー、18トリソミー、13トリソミー)があるかどうかを調べる検査「NIPT(非侵襲性出生前遺伝学的検査)」の臨床研究が始まりました。当時、さまざまな議論が起こる中、こども病院でも家族からの相談を受ける機会が増えました。2022年には、出生前検査認証制度等運営委員会が認めた地域の医療機関等が窓口となっています。
また、2015年には、「小児未診断疾患イニシアチブ(IRUD-P)」という取り組みがはじまりました。このプロジェクトでは、原因がわからない病気を持つ子どもの遺伝子を全て調べることで、原因の特定や、新しい病気の発見を目指しています。さらに、2019年には、「Priority-i」という新しい取り組みが開始されました。このプロジェクトでは、重い病気をもつ新生児について、ゲノム(体の中にあるすべての遺伝情報)を迅速かつ正確に調べることで、治療法につながる病気の早期発見を目的としています。遺伝子やゲノムを詳しく調べる解析技術の進歩で、原因不明の病気の約半分が遺伝学的に診断できるようになりました。 こうして病気の原因がわかることにより、その子どもに合った健康管理や治療方針を具体的に立てられるようになりました。その結果、その時点で利用可能な最善の医療の準備や、日常生活の質を向上させる支援が可能になりました。これらの取り組みは、形を変えて2025年現在も続いており、多くの家族にとって希望となっています。
特に、治療については大きな進展があり、一部の遺伝性疾患では、診断が早ければ早いほど効果的な治療が可能となっています。たとえば、軟骨無形成症(手足が短く、低身長になる特徴を持つ先天的な骨の病気)では、これまで生後数年してから治療が始まる選択肢に限られていました。最近では、出生後数か月でも使える薬が登場し、診断後早期からの治療により、成長をより早期から助けることが可能になりました。また、「脊髄性筋萎縮症」という、筋力が弱くなり体の動きが制限される遺伝性疾患では、以前は診断に時間がかかり、治療の開始が遅れることが課題でした。しかし現在は、拡大新生児スクリーニング検査の対象にこの疾患を含める自治体もあり、これにより、生後間もなく遺伝子検査による診断を目指せるようになりました。その結果、筋力低下を防ぐ治療が早期から可能となり、子どもたちの生活の質を大きく向上させることが期待されています。 現在、約7,000種類の遺伝性疾患が知られていますが、そのうち根本的な治療が可能なものは今のところ約200種類と言われています。しかし、新しい治療法が生まれた疾患では、診断が治療への大切なステップとなり、子どもの未来に希望をもたらすものとなっています。
ーーゲノム医療の進歩が、遺伝性疾患を持つお子さんとその家族の希望につながった具体的な事例があれば教えてください
ゲノム医療の進歩によって、これまで診断が難しかった病気の原因がわかるようになり、診断率が向上しています。ある事例では、体のいくつかの部位に先天的な異常があり、知的な発達の遅れが見られる高校生が、長年にわたり原因不明という状況にありました。その家族は「どうしてこのような状況になっているのか」を知りたいと考え、未診断疾患の解明を目指す「IRUD」(アイラッド、未診断疾患イニシアチブ)に参加しました。数年後、この病気が「突然変異」で遺伝子の変化が生じ、発症した希少疾患であることが判明しました。 この病気は報告の少ない希少疾患で、詳しい健康管理の在り方や日常生活の様子に関する情報が乏しく、有効な治療法もありませんでした。それでも、原因が判明したことに家族は安堵された様子でした。「診断がつかないまま17年間も迷い続けていました。やっと原因があることが分かり、本当に良かったです。これでこの子を説明しやすくなりました」と話してくださいました。
また、病気の原因が突然変異のため親や家族の責任ではないことや、きょうだいの将来の家族に遺伝する可能性がないことを知り、根拠のない自責の念から解放された様子もみられました。その結果、家族全体が気持ちを前向きに切り替えることになりました。
一方、診断を受けることに対して、不安や戸惑いを感じる方もいらっしゃいます。たとえば、「病気の名前がつくことでレッテルを貼られるような気がする」「治らない病気なら、診断する意味がわからない」という気持ちを抱えることもあります。こうした思いは、ごく自然なものです。
遺伝情報には、いくつか特徴があります。たとえば、以下のような点が挙げられます:家族全体に影響を与える可能性があること。病気が将来発症するリスクを知る可能性があること。一生変わらない情報であること。これらは、家族が診断を受けることに慎重となる要因にもなっています。
確かに、遺伝子検査やゲノム医療の進歩は、「原因を知りたい」と思う人にとって大きな助けになります。ただし、現時点では根本的な治療法が見つかる可能性が低いことや、知らなくてもよいと思っていた遺伝情報を予期せず知らされることもあります。そのため、検査を受ける前に「家族が今、何を知りたいのか」をじっくり伺うことはとても大切です。これは、患者さんや家族が自分たちにとって何が必要なのかを考える良い機会にもなります。
さらに、家族が「希望」を感じられるポイントは、子どもの病状や家族の状況によっても異なると思います。お子さんが小さいうちは、子どもの成長や治療後の様子が気になると思います。お子さんが成長されると、将来の生活設計や他の家族への遺伝的な影響が心配になると思います。診断により見通しがつく可能性はありますが、その意義が家族に染み入る時機の診断でないと、希望につながらないこともあるので注意が必要です。
ゲノム医療の進歩によって得られる「希望のかたち」は本当にさまざまです。家族が語るその時々の気持ちや考えを、真摯に受けとめることが大切です。
ーーこうした小児遺伝医療の進歩の中で、認定遺伝カウンセラー(R)の役割もますます重要になってきているのでしょうか?
はい、こうした小児遺伝医療の進歩により、医療現場では「認定遺伝カウンセラー(R)」(以下、遺伝カウンセラー)の役割がますます重要になっています。遺伝カウンセラーは、子どもだけでなく妊娠中の家族や成長後の大人も含め、家族全体を幅広く支援しています。たとえば、妊娠中や赤ちゃんが生まれた直後に、遺伝性疾患の可能性が疑われることがあります。このようなとき、遺伝カウンセラーは家族の不安に寄り添いながら、遺伝に関する情報をわかりやすく整理し、次のステップを考える支援をしています。また、「NIPT(非侵襲性出生前遺伝学的検査)」など出生前検査について相談を受けたり、最近は重い遺伝性疾患の原因となる遺伝子を受精卵の移植前に調べる「PGT-M(着床前遺伝学的検査)」に関する相談にも対応することがあります。こうした場面では、遺伝カウンセラーは家族の状況を理解し、倫理的な課題にも配慮しながら、中立的な立場でのサポートを心掛けています。
さらに、原因がわからない病気を持つ子どもの診断を目指す家族には、全ての遺伝子を詳しく調べる「エクソーム解析」が検討されます。この検査は結果が出るまでに数か月以上かかることが多く、結果がわかるまでの家族の不安や悩みにも対応します。報告の少ない希少疾患であることが多いので、疾患情報を集めたり、家族が孤立感を深めることのないよう同じ境遇にある家族がいないか、探すお手伝いをすることもあります。また、遺伝性疾患をもつ子どもが成長すると、小児医療から成人医療に移るときのお手伝い「トランジッション」があります。このとき、疾患に対する子どもの理解度を確認したり、疾患の受け入れや遺伝に関する悩みを丁寧に聞き、心理的な支援を行っています。
このように、遺伝カウンセラーは、診断を受けるまでの過程やその後の人生において、家族や本人を支える大切な存在です。小児遺伝医療の進歩に伴い、遺伝カウンセラーの役割は多様化し、医療と家族をつなぐ架け橋として活躍していくことでしょう。
ーー小児遺伝医療の分野で、日本が世界をリードしていることや、逆に遅れていることがあれば教えてください
小児遺伝医療は、生まれつきの異常や病気(先天異常)の研究や治療において、特に注目されている分野です。先天異常は、生まれてくる赤ちゃんのおよそ3~5%に見られ、乳児死亡の大きな原因の一つとされています。そのため、小児医療における重点疾患のひとつと位置づけられています。日本の1歳未満の乳児死亡率は1.8(2022年:出生数千人あたり)であり、世界総計(27.9)と比べても非常に低いことで知られています。これは、新生児や小児向けの高度な集中治療技術、公的医療費助成制度の充実、さらに地域社会や医療従事者が協力して子どもと家族を支援してきた成果と考えられます。遺伝性疾患を持つ子どもにおいても同様の恩恵が受けられていると思います。
一方で、いくつかの課題もあります。たとえば、小児期には医療費の助成等を受けられても、成人期以降にはその支援が引き継がれない疾患があります。遺伝性疾患を持つ患者さんが成長した後も、継続して支援が得られる仕組みを整える必要があります。また、日本でも「トランジッション」の活動は徐々に普及していますが、複数の症状を持つ遺伝性疾患の患者さんでは、先天異常に馴染みが少ない成人診療科との診療連携が難しいこともあります。
このように、日本は小児医療の質が非常に高いため、遺伝性疾患を持つ患者さんを生涯にわたって支える体制をさらに強化することで、世界のモデルとなる可能性を秘めています。たとえば、医療と福祉が一体となった支援や、患者さんとその家族が安心して相談できる場所の整備などです。そして、遺伝医療に関する経験を有する医療者や遺伝カウンセラーの育成も、より質の高い小児遺伝医療を提供するうえで欠かせません。これらの取り組みを推進することで、遺伝性疾患を持つ子どもとその家族が、どのライフステージでも安心して医療を受けられる社会が築かれるものと、期待しています。
また、全ゲノム解析技術が普及し、日本人の標準的な遺伝情報をまとめたデータベース「日本人全ゲノムリファレンスパネル(60KJPN)」というものが研究者に向けて公開されています。このデータベースは、日本人約6万人分の遺伝情報を基に作られており、病気の原因解明や新しい薬、遺伝子治療の研究に広く役立つものです。特に、日本人特有の遺伝的特徴を考慮した診断が可能になり、より正確な診断や安全な治療薬の開発にもつながります。このデータベースは日本国内だけでなく、世界中の医療研究にも活用され得るもので、日本人のデータを通じて、病気や治療に関する新しい発見が、国際的な医療の発展につながるかもしれません。日本人全ゲノムリファレンスパネルは、私たちの健康を守り、未来の医療を大きく前進させる重要な鍵になると期待されています。
・・・
令和6年度、日本では196種類の疾患に対する遺伝学的検査が保険適用で実施されています。一定の条件を満たせば、1回の採血で複数の遺伝子疾患を調べることも可能となりました。これにより、より多くの患者さんが遺伝学的な診断を目指すことができる時代となりました。しかし、遺伝学的検査の説明で伝えるべき情報量は増え、内容も複雑化しました。検査結果を説明するときも、高い専門性や臨床的な解釈が求められる場面が増えており、診療科や職種を超えた連携の必要性が高まっています。たとえば、2022年には「出生前コンサルト小児科医(日本小児科学会)」という称号がつくられました。NIPTをはじめとする出生前検査について、検査を受けるべきかどうか悩む妊婦さんや、検査を受けた後のさまざまな相談に、認定を受けた小児科医が対応しています。このような横断的な取り組みは、患者さんとその家族を多職種連携で支える一歩を示しています。・・・
ーーそうした同じ立場の専門家の方々の連携により、新たに始まっている取り組みなどあれば教えてください
希少疾患の患者さんと家族を支援するウェブ上の新しいシステム「GENIE(ジーニー)」をご紹介します。GENIEは、希少疾患を持つ子どもと家族が抱える情報不足や孤立といった課題を解消するため、同じような経験を持つ家族が出会い、支え合う「きっかけづくりの場」としての取り組みです。 このシステムは、2023年、有志の医療施設が協力して開設、現在では北海道から九州まで9施設が参加するネットワークに成長しました。オンライン会議ツールを活用し、地域の壁を越えた希少疾患の患者さんの仲間づくり「ピアカウンセリング」の実現を主な活動としています。これまでに医療スタッフも参加して2回のウェブ交流会が実施されましたが、笑顔で楽しそうに交流して下さる家族の様子に、手ごたえを感じています。
GENIEによる活動は、参加施設の医療スタッフが正確な診断の大切さを再認識する、貴重な機会となっています。小児遺伝医療に携わる医療スタッフの学びと経験を深め、さらに支援の質を高めていくことができたらと思います。この取り組みが、診療の枠組み、施設間や地域の壁を越えて、希少疾患を持つ患者さんと家族をつなぐ一つの「モデル」として、今後さらに発展していくことを期待しています。
ーー同学術集会テーマの下で「多様なこどもと家族のウェルビーイングを目指す」とありますが、ここで最も重要な要素は何であると先生はお考えですか?
「ウェルビーイング(well-being)」とは、長く続く幸福感や満足感を意味します。この考え方を、小児遺伝医療の現場でどのように実現できるかを考えることが、大会テーマである「多様な子どもと家族のウェルビーイングを目指す」の大切なポイントです。
遺伝医療を通じてウェルビーイングを実現するためには、いくつかの要素があると考えます。その中でも、患者さんや家族が「自分たちで決めた」と納得できることは、安心感や満足感が長く続くことを目指す意味で、特に大切だと思います。そのためには、医療者が、検査や治療についての選択肢をわかりやすく伝えること、家族の状況や考え方を深く理解すること、子どもや家族が「自分らしい選択」をできるよう意思決定の過程を支えること、などのサポートが重要と考えます。
今回の大会では、「家族のウェルビーイングを支えるためのサポートとはどのようなものか」を、様々な講演を通じて、診断や治療の先にある、より良い支援の在り方をと一人ひとりの役割について考えてみます。
ーー小児遺伝医療では家族がお子さんの代わりに意思決定をすることが多いと思いますが、お子さんが成長した際にその決定をすんなり受け入れることができるのでしょうか?
小児遺伝医療では、家族が子どもの代わりに意思決定を行うことが多々あります。そのため、将来子どもが成長したときに、その決定に納得できるよう、医療者側もサポートすることは大切です。
たとえば、子どもがまだ小さく物事を理解できない時期に遺伝学的検査を受ける場面では、その検査でどのような情報が得られるのか、また、将来的にどのような課題が生じる可能性があるのかを、丁寧に説明しておく必要があります。
子どもが成長し、自分自身の「いま」や「これから」について考えるようになったとき、家族が過去にした意思決定をどのように受け止めるかは、さまざまな要因に影響されると思います。たとえば、家族と医療者がどのように協力して子どもの成長を見守ってきたか、どのような雰囲気のもと疾患が語られてきたか、家庭内で疾患名、検査、治療について子どもに向けて説明されてきたか、などです。こうした要素が積み重なることで、成長した子どもが家族の決定に納得し、自分自身の選択肢として受け入れやすくなるかもしれません。
また、子どもが成長したときに、その家族が胸を張って経緯を説明できる親子関係があることも大切です。医療者は、こうした親子の絆を支える役割を果たせるかもしれません。たとえば、子どもが成長し、物心がついたときに、医療者が「お母さんもお父さんも、あのとき一生懸命に考えてくれたんですよ」と伝えることで、家族の気持ちを代弁することができます。こうした言葉は、子どもが自分の病気や健康について理解を深め、「自分にとっての幸せや健康とは何か」を考えるきっかけになることがあります。
医療者としては、こうしたサポートが子どもや家族にとって大きな励みや支えとなり、成長や将来の選択を後押しできることを願っています。
ーー遺伝性疾患を持つ子どもの多様性を尊重しつつ適切な医療を提供するためには今後どのような取り組みが必要でしょうか?
「みんな違っていて、それでいい」という考え方は、遺伝医療で多様性を説明するとき、とても大切な考え方です。遺伝性疾患も、人の多様性の一部として認識しているからです。
それに取り組む場面としては、成人医療への移行の期間を活用することが効果的と考えます。この移行支援では、子どもが自分の体や疾患について理解し、自分で健康を管理し社会で活躍するための支援をしています。当院では、中学生ごろから、その子自身に「自分の体質や病気はどのようなものか」を少しずつ説明します。そして、高校卒業までの間に、さまざまな専門職が関わりながら、外来診療を通じて理解を深めるサポートをしています。このような取り組みは、成人医療に移行した後も安心して治療を続け、健康を維持していくために欠かせないものだと考えています。
また、遺伝性疾患を持つ子どもから、「自分の病気を広く知ってもらうために、自分で情報をSNSなどで発信したい」と、相談を受けることもあります。こうした想いは、遺伝性疾患や希少疾患への正しい理解が広がり社会啓発につながる可能性があります。小児遺伝医療では、こうしたデジタル世代の子どもたちを多面的に支えていく役割も、今後求められていくかもしれません。遺伝性疾患を持つ子どもたちが「自分らしさ」とともに、安心して生活できる環境がさらに広がっていくことを願っています。
ーー今後10年間で、小児遺伝医療はどのように発展していくと予想されますか?
これからの10年間で、小児遺伝医療は多岐にわたり大きく発展していくと思われます。日本では、遺伝子やゲノム情報を医療に役立てるための技術や体制の整備が進むものと予想します。
たとえば、ゲノム解析技術が進むことで、DNAの情報(設計図の文字)をより速く、安く調べられるようになるでしょう。また、日本人特有の遺伝情報を集めたデータをAI(人工知能)が活用することで、病気の原因をより早く特定できるようになるかもしれません。さらに、DNAの変化が体にどう影響するのかを調べる技術が進めば、これまで原因がわからなかった病気の解明や新しい治療法の開発が進むことが期待されています。
生活習慣病など、複数の遺伝子や生活環境が関係する多因子遺伝病では、子どもの頃からリスクを予測して、予防に役立てることも可能になるかもしれません。もし突然お子さんが亡くなるような事態が起きたときも、遺伝情報を調べることでその原因がわかり、残された家族の健康管理や次のお子さんのリスク予測に役立つ可能性があります。さらに、遺伝子治療が進むと、これまで治療が難しかった病気でも効果的に治療できることが予想されます。
そして、このようなゲノム医療の進歩を生かした小児遺伝医療を発展させるには、遺伝性疾患に詳しい専門家の育成も欠かせません。遺伝情報を扱う医療では、高い知識や技術だけでなく、倫理的・社会的な課題への対応も求められます。さらに、遠隔診療などでデジタル技術を活用すれば、地域を越えた専門家による医療支援が進み、医療全体の質の向上にもつながるはずです。現在、日本には臨床遺伝専門医が約2,000名、認定遺伝カウンセラーが400名以上います(2025年1月時点)。また、2022年からは難病のゲノム医療に特化した専門職を育成するプログラムも始まり、専門家の数や質がさらに充実することが期待されています。
最後に、病気を診断・治療するだけでなく、患者さんや家族が健康で豊かな生活を送れるように支えることも遺伝医療の目標の一つです。そのため、病院だけでなく、行政、患者会、家族会、さらにはメディアとも協力し、患者さんや家族が暮らしやすい環境を整えていく必要があります。そして、技術が進歩し社会が変わっても、「心」を大切にした医療の必要性は変わりません。特に小児遺伝医療では、患者さん本人だけでなく家族全体を支える視点が求められます。遺伝医療が患者さんと家族、そして社会全体の幸福や健康(ウェルビーイング)につながるように、遺伝情報を正しく活用し、さまざまな診療科や職種と連携しながら、より良い未来を築くことに貢献できればと思います。
ーー最後に先生から遺伝性疾患プラスの読者に一言お願いします
小児遺伝診療部門では、子どもと家族の「その人らしさを大切にする医療」を提供しています。遺伝に関する話を、病院で相談するのを少し不安に感じられることもあるかもしれません。患者さんと家族の抱える心配や不安に寄り添い、「その人らしい」生活をサポートしていくことが役割と考えています。ちょっとした疑問や心配事でも構いませんので、「こんなこと聞いてもいいのかな?」と思ったら、是非ご相談ください。一緒に考えていきましょう。・・・
<関連リンク>