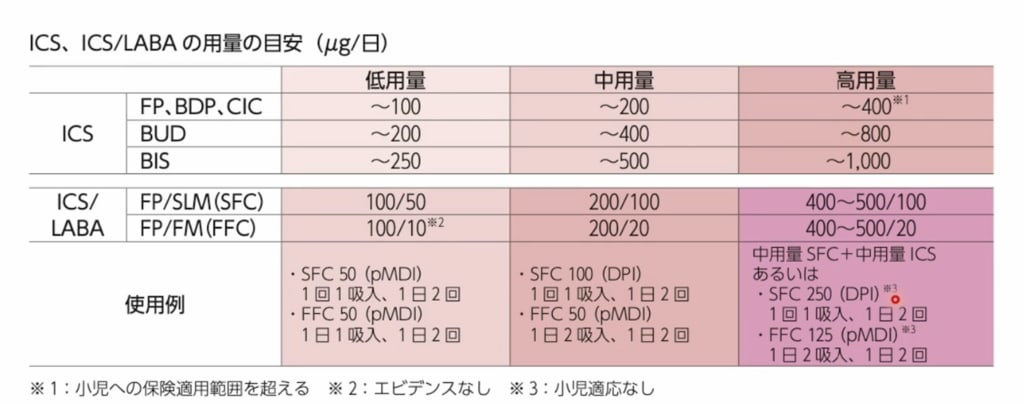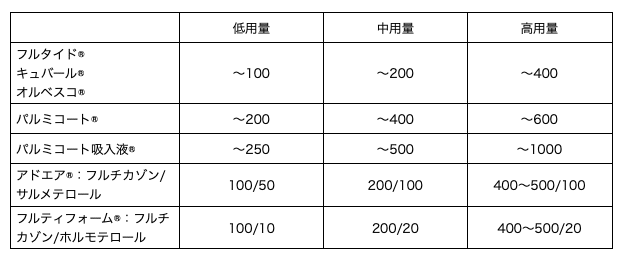一般啓蒙用ではなく、医療関係者向けのフルミスト®解説を見つけました。
このワクチンの特徴は、
・痛くないこと
・生ワクチンであること
・乳児には適応がないこと(副反応出現のため認可されなかった)
・成人には適応がないこと(効果が期待できない)
・アメリカでは一時、推奨から外れたこと
に集約されると思います。
…と思って読んでいたら、
「アメリカでは自己投与が認可された」
という驚くべき記載がありました。
当院でもこのワクチンを接種していますが、
確かに手技は簡単で、医療関係者でなくても可能なレベルと思います。
将来、日本でも自己投与が可能になるときが来るのでしょうか…
<ポイント>
・米国FDAは,2024年9月に経鼻弱毒生インフルエンザワクチン(以降,生ワクチンと略す)の自己投与,介護者による投与を認め、医療従事者による投与を必要としない初のワクチンとなった(ただし2~17歳は生ワクチンの自己投与はできず,介護者が投与する)。
・生ワクチンは細胞培養(Vero細胞)で増殖させた,A型としてA(H1N1)pdm09とA(H3N2)の2種の亜型,B型としてビクトリアと山形の2系統,計4種類のワクチン株を含む4価ワクチン。
→ 日本で接種されるワクチンは3価です。
・米国では2015~16年シーズンに,生ワクチンと不活化ワクチンの効果比較試験が実施され,その結果から,一時,生ワクチンであるFluMist®の使用が中止された。
・肺・気管支などに疾患がある場合,特に喘息児では接種は慎重にすべき。
…以上の内容から、生ワクチンの登場により「インフルエンザ流行が一気に解決!」は期待できないようです。
当院では喘息児や卵アレルギー児が多く通っているので、その点に注意しながら接種をしています。
▢ 経鼻弱毒生インフルエンザワクチンについて
菅谷憲夫 (神奈川県警友会けいゆう病院名誉参事,前神奈川県警友会けいゆう病院感染制御センター長,WHO Public Health Research Agenda for Influenza委員)
(2024-11-06:日本医事新報社)より一部抜粋(下線は私が引きました);
経鼻弱毒生インフルエンザワクチン(商品名フルミストⓇ点鼻液)は,日本でも2023年3月に認可され,2024年秋から,2歳以上19歳未満を対象に接種が開始された。本論文では,フルミストⓇ点鼻液の審議結果報告書1)を解説し,約10年前に米国で接種が中止になった経緯,不活化ワクチンとの効果の比較などを紹介する。
1. 米国での経鼻弱毒生ワクチン自己投与の承認
米国FDAは,2024年9月に経鼻弱毒生インフルエンザワクチン(以降,生ワクチンと略す)の自己投与,介護者による投与を認めた。オンライン薬局を通じての注文,購入希望者の適格性の判断,処方箋の発行,生ワクチンの発送などが決められた2)。米国では生ワクチンは,2~49歳の個人におけるインフルエンザ疾患予防に承認されているが,今回の決定により,医療従事者による投与を必要としない初のワクチンとなった。しかし,2~17歳は生ワクチンの自己投与はできず,介護者が投与することとなっている。
2. 経鼻弱毒生ワクチン
生ワクチンは細胞培養(Vero細胞)で増殖させた,A型としてA(H1N1)pdm09とA(H3N2)の2種の亜型,B型としてビクトリアと山形の2系統,計4種類のワクチン株を含む4価ワクチンである。新型コロナワクチン出現以降,B型の山形系統は世界で分離されないので,日本では山形株は除かれる。2歳以上19歳未満では,0.2mL(各鼻腔内に0.1mL)を1回噴霧する。
用いられる生ワクチン株は,以下の通りである。
- 32℃前後で増殖しやすい低温馴化株である(低温の鼻腔で増殖しやすい)。
- 37℃以上では増殖しにくい温度感受性株である(高温の下気道では増殖しない)。
- 動物モデルでインフルエンザ症状を呈さないという特性を持つ弱毒株である。
生ワクチン株は,上記の特徴を持つA型のA/Ann Arbor株,B型のB/Ann Arbor株とWHOから選定された候補株の遺伝子再集合により作製される。したがって,生ワクチンのHA(hemagglutinin)とNA(neuraminidase)のスパイクは,WHOの候補株と同一である。
1噴霧容器当たり(0.2mL)4種の各ウイルスが,1種当たり7log10FFU含まれている。通常,小児の鼻腔からは,4~6log10FFUのウイルスが分離されるので,生ワクチン株は,インフルエンザに自然感染した小児の鼻腔内よりも10倍から100倍多いウイルス量となる。
3. 弱毒生ワクチンの安全性
2014年に安全性の検討を目的に,2~6歳の日本人健康小児100人に非盲検非対照試験が実施された(007試験)1)。有害事象として,鼻咽頭炎,胃腸炎,皮膚乾燥などが認められたが,重篤な事象はなかった。
4. 弱毒生ワクチンは低年齢小児で有効ではなかった
2016年10月~2017年5月に,国内第3相試験である無作為化二重盲検プラセボ対照試験が,2〜18歳を対象に実施された(J301試験)1)。治験薬は4価の生ワクチンで,0.2mLを鼻腔内に1回噴霧した。ワクチン効果は,生ワクチン接種群と非接種群(プラセボ)にわけて,各群でのインフルエンザ発症率を比較した。インフルエンザ診断はPCR法による。
2016~17年シーズンの流行ウイルスは,A型はA(H3N2)で,B型はビクトリアと山形系統が混合していた。生ワクチン接種群では595例中152例がインフルエンザを発症し(25.5%),プラセボ群では290例中104例が発症した(35.9%)。したがって,すべてのインフルエンザ(A型とB型の合計)に対する発症防止効果は,28.8%〔95%信頼区間(CI):12.5~42.0〕となった。A(H3N2)に対する発症防止効果は28.8%(95%CI:9.0~43.1)であったが,A(H1N1)pdm09については,症例が4例のみで評価はできなかった。またB型に対する効果は,ビクトリアと山形系統を合計して22例で,統計的に有意ではなかった。
年齢群別での,すべてのインフルエンザに対する発症防止効果は,2~6歳群で21.6%(95%CI:−8.6~43.4),7~12歳群で30.6%(95%CI:6.7~48.2),13~18歳群で41.4%(95%CI:−9.6~68.7)であり,2~6歳群と13~18歳群では統計的に有意ではなかった。
J301試験の結果を見ると,生ワクチンのインフルエンザ発症防止効果が28.8%と低く,経鼻生ワクチンの接種対象として期待される低年齢層(2~6歳群)で,有意な結果が得られなかった点が問題である。また抗原性一致株と不一致株にわけてワクチン効果を解析し,すべてのインフルエンザでは36.6%としているが,2016〜17年シーズンは特に抗原変異はなく,その上,方法などが提示されていないので,評価できない。
5. 不活化ワクチンの発症防止効果は低年齢小児で高い
J301試験と同時期(2016~17年)に,日本で実施された4価の不活化ワクチンの発症防止効果が,慶應小児インフルエンザ研究グループ(代表:菅谷憲夫)から発表されている。6カ月~15歳の3869例の小児発熱患者を対象に,発症防止効果をtest-negative case-control design(以下,TND法と略す)で検証し,診断は迅速診断キットによって行われた3)。
すべてのインフルエンザに対する発症防止効果は,39%(95%CI:28~49)で,A型は41%(95%CI:32~50),B型は41%(95%CI:21~56)であった。慶應の報告はTND法であり,一方のJ301試験はコホートという違いはあるが,生ワクチンに比べ,不活化ワクチンの安定した高い効果が示されている。特に1~2歳群の発症防止効果は高く,A型は46%(95%CI:2~60),B型は69%(95%CI:26~87)であった3)。慶應の不活化ワクチンの成績では,低年齢層での効果が全年齢層を通じて最も高いことが示された3)。学童や中学生よりも,1~6歳児での効果が高い。
6. 米国での弱毒生ワクチンの使用中止の経緯
米国では2015~16年シーズンに,生ワクチンと不活化ワクチンの効果比較試験が実施され,その結果から,一時,生ワクチンであるFluMist®の使用が中止された。試験の1つは,New England Journal of Medicine(NEJM)誌に報告された4)。TND法で実施され,診断はPCR法による。2~17歳の小児を対象として(n=2047),インフルエンザが陽性反応を示した大部分がA(H1N1)pdm09とB型であった。すべてのインフルエンザに対する不活化ワクチンの発症防止効果は60%(95%CI:47~70)と高く,一方,生ワクチンは5%(95%CI:−47~39)と効果は認められなかった。
A(H1N1)pdm09に対する発症防止効果は,不活化ワクチンでは63%(95%CI:45~75)と高く,生ワクチンでは−19%(95%CI:−113~33)と効果はなかった。B型に対しては,不活化ワクチンは54%(95%CI:31~69)と高い効果で,生ワクチンは18%(95%CI:−52~56)と統計的に有意ではなかった。本論文によれば,2015~16年シーズンにおいて,小児では,不活化ワクチンは,A(H1N1)pdm09とB型に高い効果があったが,生ワクチンはどちらにも効果が認められず,特にA(H1N1)pdm09にはまったく効果がなかった。
もう1つの試験は,同シーズンに外来患者1012例(2~17歳)を対象に,生ワクチンと不活化ワクチンの効果比較を,NEJMと同様の方法で実施したものである5)。結果は,A(H1N1)pdm09に対し,生ワクチンは50%(95%CI:−2~75)で統計的に有意ではなかったが,不活化ワクチンでは71%(95%CI:51~82)と高い有効率を示した。
2015~16年シーズンに,米国では2つの比較試験が実施されたが,A(H1N1)pdm09に対する発症防止効果は認められなかった。そのため,2016~17年と2017~18年シーズンは,米国では生ワクチンを使用しないよう米国CDCが勧告を出した。
7. 日本小児科学会の不活化ワクチン効果の見解
審議結果報告書1)では,20年も前の2004年の日本小児科学会の見解6)を引用しているが,そこではわが国では,「1歳以上6歳未満の乳児については,インフルエンザによる合併症のリスクを鑑み,有効率20%~30%であることを説明した上で任意接種としてワクチン接種を推奨することが現段階で適切な方向である」としている。この見解を引用したのは,J301試験での生ワクチンのインフルエンザ発症防止効果が28.8%と低く,生ワクチン接種の意義があるかという疑問の出るレベルであるが,学会見解には合致しているとしたいのであろうか。しかし,学会見解の根拠とした報告は,返信用ハガキにより,発熱,咳などについてアンケート調査したものであり,インフルエンザ検査診断を実施していないので,現代のワクチン研究のレベルでは通用しない。
さらに報告書では,「患者の年齢が低下すると,不活化インフルエンザワクチンの効果は低下する」としているが1),慶應小児科の2013~14年シーズン以来のデータでは3)7)8),1~6歳未満の年齢群では,全年齢層で最もインフルエンザ発症防止効果が高いことは明らかである。
8. 今後の弱毒生ワクチンの評価
生ワクチンは,米国でA(H1N1)pdm09には無効であったことが,NEJMなどの雑誌に報告され,2シーズンにわたり使用中止となり,現在はあまり使用されていないことを考えると,今後,生ワクチン効果の慎重な見きわめが必要となる。日本では,低年齢児(2~6歳)には有効性は証明されておらず,A(H1N1)pdm09やB型については効果の検証もされていない。
接種の注意として,生ワクチンのため妊婦には禁忌であり,水平感染の可能性から授乳中の母親は接種後1~2週は乳児との接触を控えることが挙げられる。また,肺・気管支などに疾患がある場合,特に喘息児では接種は慎重にすべきである。さらに,ゼラチンに強いアレルギーのある場合は禁忌となる。生ワクチンという特性から,アスピリン内服中の人は接種できず,接種後4週はアスピリンの使用は避けるべきである9)。なお安全性などについては,日本小児科学会からも見解が出されている10)。
【文献】
1)医薬品医療機器総合機構:審議結果報告書. 2023.3.6.
https://www.pmda.go.jp/drugs/2023/P20230424001/430574000_30500AMX00102_A100_1.pdf
https://www.pmda.go.jp/drugs/2023/P20230424001/430574000_30500AMX00102_A100_1.pdf
2)FDA News Release:FDA Approves Nasal Spray Influenza Vaccine for Self- or Caregiver-Administration. 2024.
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-nasal-spray-influenza-vaccine-self-or-caregiver-administration
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-nasal-spray-influenza-vaccine-self-or-caregiver-administration
3)Shinjoh M, et al:Vaccine. 2018;36(37):5510-8.
4)Jackson ML, et al:N Engl J Med. 2017;377(6):534-43.
5)Poehling KA, et al:Clin Infect Dis. 2018;66(5):665-72.
7)Shinjoh M, et al:PLoS One. 2015;10(8):e0136539.
8)Sugaya N, et al:Vaccine. 2018;36(8):1063-71.