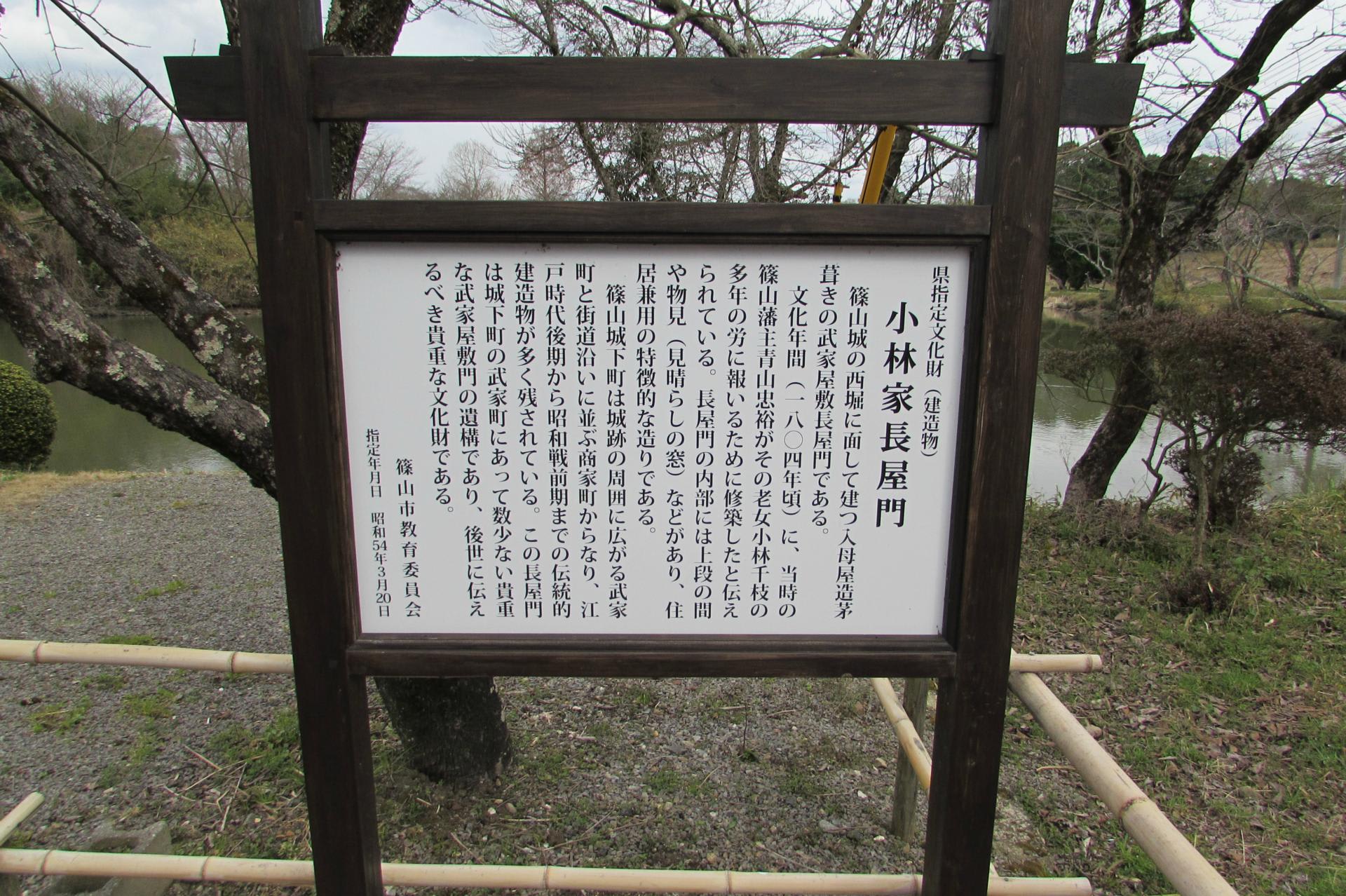2016年3月13日、有馬温泉の月光園游月山荘に泊まりました。神戸を出て、柏原、篠山の町並みを散策し、神戸に戻りました。
プラン名は、特撰黒毛和牛のすき焼きをお部屋で!部屋条件は木の温もりを感じる和室8帖です。山荘は本館から小川を渡り2階建てです。
部屋には小庭園付きです。料金は19440円でした。少し早目につきましたので、温泉街を散策し、お土産などを買って、温泉に浸かりました。
温泉は、本館での大浴場には内風呂と露天風呂、サウナ風呂があります。山荘のほうにも露天風呂があります。川沿いでの露天風呂がありますが、雨が降ってきたのでそこは入りませんでした。本館では風呂上がりの生ビールのサービスも。
神戸市北区有馬町318
map
山荘外観

本館外観


ロビー


売店


ラウンジ

部屋




窓の外の小庭

部屋からの眺め

廊下








夕食です。もちろんビールを飲みながら頂きました。
八寸

旬の野菜

造り

すき焼き

〆にうどん


デザート

朝食はバイキング形式です。


プラン名は、特撰黒毛和牛のすき焼きをお部屋で!部屋条件は木の温もりを感じる和室8帖です。山荘は本館から小川を渡り2階建てです。
部屋には小庭園付きです。料金は19440円でした。少し早目につきましたので、温泉街を散策し、お土産などを買って、温泉に浸かりました。
温泉は、本館での大浴場には内風呂と露天風呂、サウナ風呂があります。山荘のほうにも露天風呂があります。川沿いでの露天風呂がありますが、雨が降ってきたのでそこは入りませんでした。本館では風呂上がりの生ビールのサービスも。
神戸市北区有馬町318
map
山荘外観

本館外観


ロビー


売店


ラウンジ

部屋




窓の外の小庭

部屋からの眺め

廊下








夕食です。もちろんビールを飲みながら頂きました。
八寸

旬の野菜

造り

すき焼き

〆にうどん


デザート

朝食はバイキング形式です。