2016年5月2日、お参りしました。
「初代、神武天皇が即位された橿原宮跡に、明治23年(1890)、神武天皇と皇后を御祭神として御鎮座。本殿は、明治天皇のご聖慮により、元の京都御所の賢所を下賜されたもの。檜皮葺の入母屋造で、国の重要文化財に指定されています。」
奈良県橿原市久米町934
map
案内図

鳥居

参道



鳥居





南神門


深田池

参集所


神楽殿

儀式殿


境内と外拝殿

廻廊


外拝殿


内拝殿



廻廊



弊殿

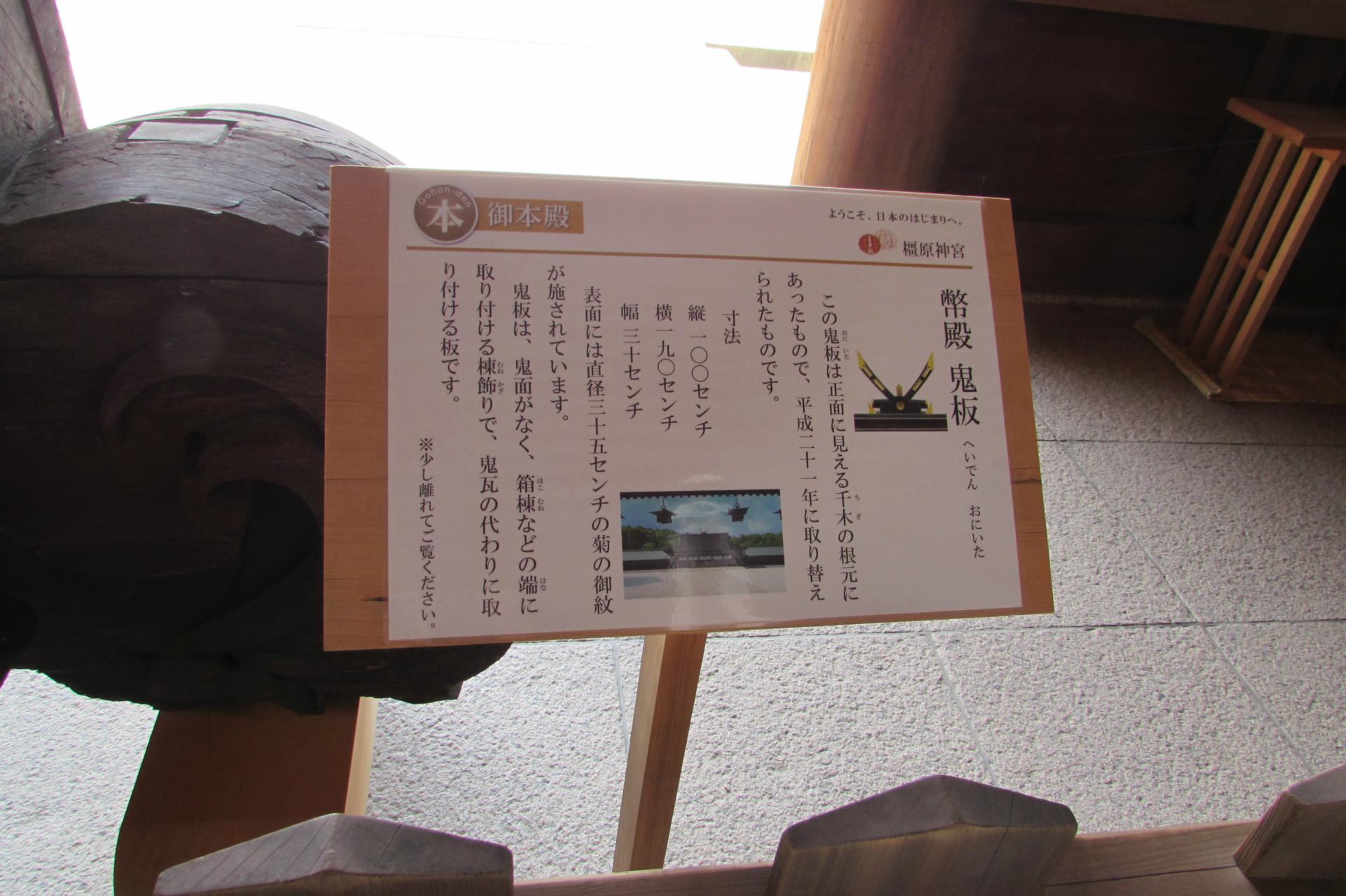

外拝殿の天井


大絵馬


北神門



お疲れ様でした。
「初代、神武天皇が即位された橿原宮跡に、明治23年(1890)、神武天皇と皇后を御祭神として御鎮座。本殿は、明治天皇のご聖慮により、元の京都御所の賢所を下賜されたもの。檜皮葺の入母屋造で、国の重要文化財に指定されています。」
奈良県橿原市久米町934
map
案内図

鳥居

参道



鳥居





南神門


深田池

参集所


神楽殿

儀式殿


境内と外拝殿

廻廊


外拝殿


内拝殿



廻廊



弊殿

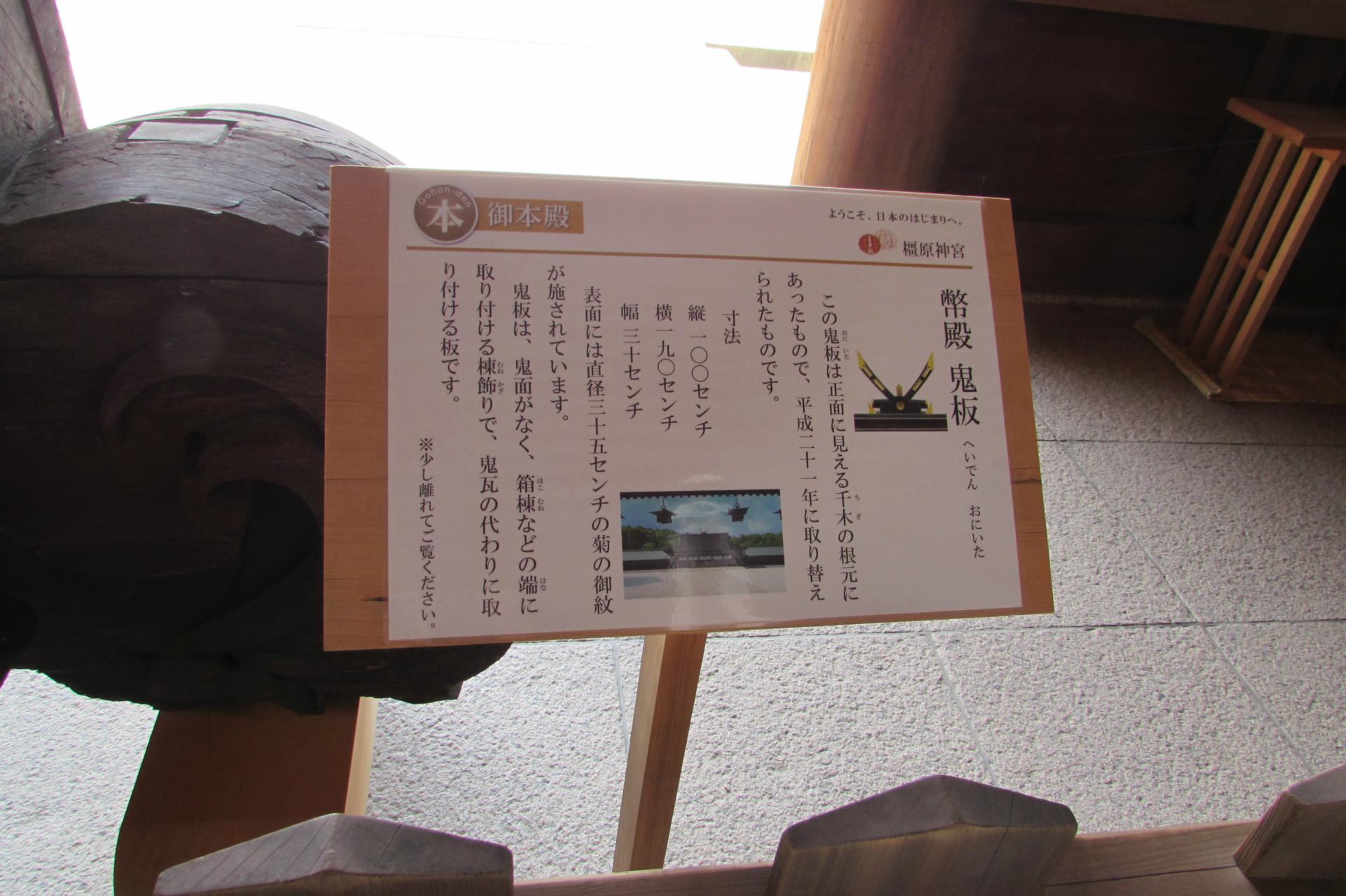

外拝殿の天井


大絵馬


北神門



お疲れ様でした。






























































































































































































