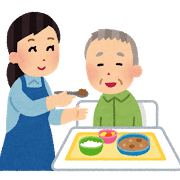1月5日(火)
箕面市の介護予防・
日常生活支援総合事業について②
全国で先行、大阪ではじめて行われている
箕面市の介護予防・総合事業の検証と体制確保を
昨年の12月市議会での、箕面市の介護予防・日常生活総合事業についての一般質問187号の続きをご紹介します。
箕面市の介護予防・
日常生活支援総合事業について
市議会報告187号の続き
この6か月の状況は「(総合事業の」サービス提供とモニタリングを継続している」「様子をみている」とのことですので、まだ、その結果が確認できているとはいえない状況ということです。
⑤今後の体制について 質問します。
対象者が50人だからきめ細かな施策が推進できたのではないか?
新総合事業での要支援者への介護サービス提供では、本人・当事者、家族の意見やケアマネ、市の理学療法士も参加してきめ細かな状況把握と合意による対応がなされてきたとのことですね?
対象者が総合事業の緩和型で10月には9人、11月には通所型で36人、訪問型で14人。そして、チエックリストによる事業対象者が8人の合計50人と答弁でお聞きしましたが、こうした50人くらいの人数だからこそ、きめ細かな対応でこれまでの施策の推進が行われてきたのではないでしょうか?
市の理学療法士の人件費も介護保険以外に確保してこの施策を進められて来れたのではなかったのでしょうか?
対象者が大幅に増えれば、体制は確保できるのか?
今後、その対象人数が、認定の見直し、認定などで今後大幅に増えることが予想されます。今後の体制はどう考えられるのでしょうか?
8月に行われた箕面市社会保障推進協議会の箕面市内事業者へのアンケートへの回答の国・自治体への意見では「介護報酬が改定の度に下がっているので、今後の事業継続やサービスの質の確保に不安があります。引き下げばかりの改定は非常に困ります。」「要支援の介護報酬を下げすぎだと思います。当施設は要支援の方が在籍の7割を占めるので大打撃です。」「介護保険制度の崩壊を心配しています。」など切実な不安の声がよせられました。
一方「新総合事業の緩和型サービスの人員(定員)基準をもう少し緩和していただきたい。」「今の通所介護の条件をもっと緩和してスタッフの人手を新たに増やさなくてもよい1人当たりの面積の緩和など現実的に経営可能になる。」などもっと緩和を求める声もありました。こうした、方向は、ますますサービスを低下させてゆく方向に繋がると考えられます。
介護報酬のマイナス改定と制度改定の認識は?
介護報酬のマイナス改定と制度改定で危機的な状況になるのでは?と懸念されます。「先進的に」基準緩和型を導入してきた市としてのその認識はどうでしょうか?
国に対して基本報酬の削減分を回復することを求めます。「保険料に跳ね返る」と言わず、介護保険の枠内でなく国に国庫負担として増額を求めることが重要です。
サービス向上のための報酬確保を国に働きかけを
さらに、新総合事業は、市町村事業であるなら市が、通所介護所の実態をしっかり把握すべきです。委員会答弁での「非常に質の悪いデイサービスも出てきている、お客さんを囲い込んで、無理やりに介護報酬を稼ぐようなデイサービスセンターも箕面に限らず全国的にふえつつある」「不適切な事業者は淘汰されるべき」などのような市場原理にゆだねる認識では、高齢者のサービス水準は守られないと考えられます。質の悪い事業所があるなら実態を把握して指導する。質の良い事業者の事業が維持できるよう、事業が発展できるよう、利用者へのサービスが向上するための報酬が確保されるよう、府を通して国に働き掛けるべきです。
これまでの通所介護利用が保障されるよう体制確保を!
「設置基準を検査し、基準通り事業を行っているか?実地検査が市と広域課の仕事」にとどまらず、新総合事業の実施で市としてこれまでの通所介護の利用が保障できるような体制確保を改めて求めるものです。
答弁:サービスお提供は利用者の自立にむけた、きめ細かい適切なサービスを提供している。H28年度から、日常生活動作の改善ができる骨・関節系疾患などの方は「自立支援型担当者会議」を引き続き開催しメニューを決定してゆく。それ以外は、利用基準を作成し包括支援センター、ケアマネがサービス調整できる体制を構築する。
緩和型サービスをはじめ総合事業の推進は、きめ細かく対応し、生活機能の維持向上に最も適切なサービス提供をするため導入したもの。持続可能な介護保険制度と地域包括ケアシステム確立してゆくためにはいずれも必要な制度改正である。サービス事業者も、中長期的に参入や経営を検討してゆくもの。市として適切なサービスが提供されるよう、人員、設備の基準を設定し厳格に審査してゆく。
「国への基本報酬の要望」は、財源構成が法律で規定されており、介護報酬の引き上げは保険料の上昇や利用者負担増に影響することから、市として国へ働きかけを行う予定はない。
きめ細かな「自立支援」サービスが今後、機能してゆくのか現在の要支援者の総合事業の対象者は50人程度ですが、その他に、現在、これまでの従来の介護保険サービスを継続できている方々もたくさんおられます。
今後、再認定などで、これらの方々も新総合事業の対象者となってきます。箕面市では、市の理学療法士の体制や「自立支援型担当者会議」で、これまできめ細かな対応がなされていると理解しますが、要支援1.2の認定者が箕面市で約1800人と、今後、大量の要支援者がこの総合事業のサービスと移行されてきたときに、このきめ細かな「自立支援」のサービスが、機能してゆくのか疑問です。
総合事業の状況の検証と体制の確保を!
今後も、その状況をしっかり検証して、体制をつくってゆくことを要望して、介護予防・日常生活支援総合事業についての1項目目の質問を終わります。
介護予防・総合事業についての一般質問の内容おわり
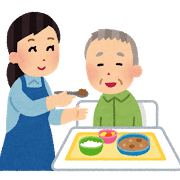
箕面市の介護予防・
日常生活支援総合事業について②
全国で先行、大阪ではじめて行われている
箕面市の介護予防・総合事業の検証と体制確保を
昨年の12月市議会での、箕面市の介護予防・日常生活総合事業についての一般質問187号の続きをご紹介します。
箕面市の介護予防・
日常生活支援総合事業について
市議会報告187号の続き
この6か月の状況は「(総合事業の」サービス提供とモニタリングを継続している」「様子をみている」とのことですので、まだ、その結果が確認できているとはいえない状況ということです。
⑤今後の体制について 質問します。
対象者が50人だからきめ細かな施策が推進できたのではないか?
新総合事業での要支援者への介護サービス提供では、本人・当事者、家族の意見やケアマネ、市の理学療法士も参加してきめ細かな状況把握と合意による対応がなされてきたとのことですね?
対象者が総合事業の緩和型で10月には9人、11月には通所型で36人、訪問型で14人。そして、チエックリストによる事業対象者が8人の合計50人と答弁でお聞きしましたが、こうした50人くらいの人数だからこそ、きめ細かな対応でこれまでの施策の推進が行われてきたのではないでしょうか?
市の理学療法士の人件費も介護保険以外に確保してこの施策を進められて来れたのではなかったのでしょうか?
対象者が大幅に増えれば、体制は確保できるのか?
今後、その対象人数が、認定の見直し、認定などで今後大幅に増えることが予想されます。今後の体制はどう考えられるのでしょうか?
8月に行われた箕面市社会保障推進協議会の箕面市内事業者へのアンケートへの回答の国・自治体への意見では「介護報酬が改定の度に下がっているので、今後の事業継続やサービスの質の確保に不安があります。引き下げばかりの改定は非常に困ります。」「要支援の介護報酬を下げすぎだと思います。当施設は要支援の方が在籍の7割を占めるので大打撃です。」「介護保険制度の崩壊を心配しています。」など切実な不安の声がよせられました。
一方「新総合事業の緩和型サービスの人員(定員)基準をもう少し緩和していただきたい。」「今の通所介護の条件をもっと緩和してスタッフの人手を新たに増やさなくてもよい1人当たりの面積の緩和など現実的に経営可能になる。」などもっと緩和を求める声もありました。こうした、方向は、ますますサービスを低下させてゆく方向に繋がると考えられます。
介護報酬のマイナス改定と制度改定の認識は?
介護報酬のマイナス改定と制度改定で危機的な状況になるのでは?と懸念されます。「先進的に」基準緩和型を導入してきた市としてのその認識はどうでしょうか?
国に対して基本報酬の削減分を回復することを求めます。「保険料に跳ね返る」と言わず、介護保険の枠内でなく国に国庫負担として増額を求めることが重要です。
サービス向上のための報酬確保を国に働きかけを
さらに、新総合事業は、市町村事業であるなら市が、通所介護所の実態をしっかり把握すべきです。委員会答弁での「非常に質の悪いデイサービスも出てきている、お客さんを囲い込んで、無理やりに介護報酬を稼ぐようなデイサービスセンターも箕面に限らず全国的にふえつつある」「不適切な事業者は淘汰されるべき」などのような市場原理にゆだねる認識では、高齢者のサービス水準は守られないと考えられます。質の悪い事業所があるなら実態を把握して指導する。質の良い事業者の事業が維持できるよう、事業が発展できるよう、利用者へのサービスが向上するための報酬が確保されるよう、府を通して国に働き掛けるべきです。
これまでの通所介護利用が保障されるよう体制確保を!
「設置基準を検査し、基準通り事業を行っているか?実地検査が市と広域課の仕事」にとどまらず、新総合事業の実施で市としてこれまでの通所介護の利用が保障できるような体制確保を改めて求めるものです。
答弁:サービスお提供は利用者の自立にむけた、きめ細かい適切なサービスを提供している。H28年度から、日常生活動作の改善ができる骨・関節系疾患などの方は「自立支援型担当者会議」を引き続き開催しメニューを決定してゆく。それ以外は、利用基準を作成し包括支援センター、ケアマネがサービス調整できる体制を構築する。
緩和型サービスをはじめ総合事業の推進は、きめ細かく対応し、生活機能の維持向上に最も適切なサービス提供をするため導入したもの。持続可能な介護保険制度と地域包括ケアシステム確立してゆくためにはいずれも必要な制度改正である。サービス事業者も、中長期的に参入や経営を検討してゆくもの。市として適切なサービスが提供されるよう、人員、設備の基準を設定し厳格に審査してゆく。
「国への基本報酬の要望」は、財源構成が法律で規定されており、介護報酬の引き上げは保険料の上昇や利用者負担増に影響することから、市として国へ働きかけを行う予定はない。
きめ細かな「自立支援」サービスが今後、機能してゆくのか現在の要支援者の総合事業の対象者は50人程度ですが、その他に、現在、これまでの従来の介護保険サービスを継続できている方々もたくさんおられます。
今後、再認定などで、これらの方々も新総合事業の対象者となってきます。箕面市では、市の理学療法士の体制や「自立支援型担当者会議」で、これまできめ細かな対応がなされていると理解しますが、要支援1.2の認定者が箕面市で約1800人と、今後、大量の要支援者がこの総合事業のサービスと移行されてきたときに、このきめ細かな「自立支援」のサービスが、機能してゆくのか疑問です。
総合事業の状況の検証と体制の確保を!
今後も、その状況をしっかり検証して、体制をつくってゆくことを要望して、介護予防・日常生活支援総合事業についての1項目目の質問を終わります。
介護予防・総合事業についての一般質問の内容おわり