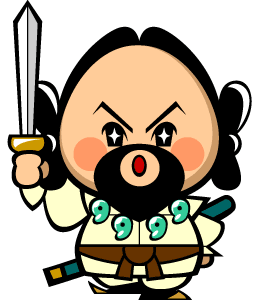 PART1はこちら。
PART1はこちら。
積立も目標額にほぼ達し、さあそろそろ建て替えるべ、となった途端にあの震災。鳥居が傾いてしまったので、業者をよんでわざと倒壊させている。こうなるともう待ったなし。
神道に暗い人間にとって、神社の建て替えがどんな経緯をたどるのかはもちろんさっぱりわからない。これは大方の人がそうだろうと思う。伊勢神宮のように20年ごとに建て替える場合はおなじみのことだろう。でも、田舎の小さな社の場合は数世代に一回経験するにすぎないわけで
「いい経験だ」
という年長者のつぶやきも、まるっきりギャグというわけでもないのだ。
で、今月の初めにこんな文書が。
【仮殿遷座祭のお願いとご案内】
かりどのせんざさい?なんだそりゃ。意味するところは、神社の「御」を仮殿に奉安する儀式。この場合の「御」は稲荷神社のご神体をさし、暫定的な移設先である仮殿は自治会の公会堂。そのお引っ越しのときに、村の中を氏子が行列するんですって。
それはまあ、なにかの儀式はあるだろうと思ったが、行列とは意表をつかれた。しかも服装は礼服指定。おお、黒ネクタイ以外で礼服を着るのって久しぶりだなあ。
ということで当日、公会堂集合は午後6時。日曜日なのにどうしてもっと早めに集めないのかな……すぐに判明。ご神体は暗くならないと外に出ないそうなのである。へー。しかも、行列の際には、ご神体を抱いた神主さんの四方を布でできたバリケードみたいなので完全遮蔽するのだ。
中心にあるものを秘匿することで畏怖させる……これが神道の極意みたい。
当日の進行表がまた趣深い。とにかくなじみのない単語がいっぱい。
『氏子奉仕員』
『修祓』
『参進』
『奉戴』
『遷御』
『大麻(たいまじゃないよ)』
『絹垣』
『召立』
……うわーわからない。そして「わからないこと」が即ち「ありがたいこと」につながるのは、あらゆる宗教に共通してもいるんだろう。以下次号。
















