

▲ 今週のみけちゃん
▼ 筑紫洲 (つくしのしま) でもぶどう記録;第47週

■ 今週のよその猫



■ 今週の筑豊境


■ 今週のメタセコイア

■ 今週のお「魚」:鯨 = 大きな魚
古くは鯨が哺乳類ではなく魚と考えられていたため、その大きさが普通ではなかったことから、「京(兆の1万倍の単位)」のような計り知れない魚ということで「魚」と「京」をあわせて「鯨」となったといわれています(google)。

北西太平洋産 イワシ鯨(wiki)

食感は基本的のやわらかかった。マグロのよりはやや肉感がある。
■ 今週のˈbʌfeɪ/

すからーくグループの「しゃぶ葉」に初めて行った。「しゃぶ葉」は食べ放題のしゃぶしゃぶ屋さんだ。<荊の簪を挿した御方さま>はすかいらーくグループの株を持っていて、おいらは優待券の恩恵に与かれる。これまで、「しゃぶ葉」に行ったことがなかった。理由は、<荊の簪を挿した御方さま>がお肉が苦手だからだ。おいらが、どうしても行きたいというので、奢ってもらった。選んだコースは一番簡素な豚バラ+鳥のみのもの。<荊の簪を挿した御方さま>はお肉を食べないのだが、同席の人は同一メニューを注文すべしとのことで二人前を注文。

豚バラは一皿、約50g。

 豚バラは一皿、約50g。10皿食べた。鳥が一皿。
豚バラは一皿、約50g。10皿食べた。鳥が一皿。
■ 今週借りて読んだ本

堂本正樹、『回想 回転扉の三島由紀夫』。2005年の刊行。もう20年前だ。堂本正樹[wiki]は、三島由紀夫の8歳年下の「寝友」。ここで「寝友」とは親友のもじりで、褥を共にする友ということだ。松村剛の「造語」とのこと。この本に書いてある。ただの同性愛の恋人同志であったばかりでなく、切腹愛好家同志であった。腹を裂き、腸が飛び出す切腹の凄惨な状況の絵を出汁にして二人で昂奮しあい、切腹ごっこをしていたというのだ。
果たして、堂本正樹は映画『憂国』(三島由紀夫が切腹を演じる映画)の演出を行った。
『回想 回転扉の三島由紀夫』には三島との出会いからのことが書いてある。おいらが、興味深かったのは、堂本正樹の「外人嫌い」。ここで、外人とはただ外国人を指すのではなく、端的に進駐軍兵士のことだろう。堂本が三島と出会ったのは昭和24年(1949年)、まだ占領下である。最近、おいらが認識したことは、敗戦後、占領下では進駐軍の同性愛者が占領下日本(Occupied Japan)で大いに羽目をはずしていたことである。その当時、米国、特に米軍では同性愛は宗教上、そして法的にも、厳しく禁じられていた。それでも、同性愛者たちはいたはずだから陰で秘かにやっていたのだろう。それが、占領地日本の巷に出ると米国のように厳しく禁じられていないので、同性愛の米軍関係者は、大いに楽しんだらしい。男の街「娼」もいた。以前、TBSラジオ、「安住紳一郎日曜天国」でゲストの「伝説のオネエ・吉野ママ」(google)が敗戦直後、進駐軍兵士相手のハッテン場があったと証言していたのを聴いた記憶がおいらにはある。「男のパンパン」と云っていた。進駐軍同性愛者たちは、権力を背景に、「クラブ」を日本人とつくったりした。そういう同性愛クラブに三島は関係があった。鎌倉での「外人の乱痴気パーティーに三島と堂本が参加したことを堂本は書いている。こういう背景で敗戦後日本の同性愛者世間では「外人」が少なからずいたのだろう。それを堂本正樹は嫌ったと報告している。堂本が初めて三島に会った場面を描く一文章が興味深かったのでコピペする;
そこに、三島由紀夫はいた。
蒼い縞のワイシャツを着、白い艶のあるネクタイをし、同じく白いズボンを穿いていた。シャツの袖口からは、芝翫論を見せてくれた人と同じく剛毛が覗く。
頬の剃り跡が青く、顎にくびれがあり、しかもしゃくれた顔は、進駐軍の兵隊を思わせた。(堂本正樹、『回想 回転扉の三島由紀夫』、第一章 八歳違いの「兄貴」)
堂本正樹は能と歌舞伎の愛好者で、その深度は深く、三島は能をよくわかっていなかったと報告している。
当時は慶応の旧制中学の学生、その後、慶応の国文に進み、中退とある。戦時中は鎌倉に疎開していた。ところで、堂本正樹は1933年生まれ、江藤淳、愚記事で江藤淳が、三島由紀夫を「殺した」のか?とある江藤淳は自称1933年生まれ、本当は1932年生まれで似たような年齢であるから、同じく鎌倉に疎開していた江藤と堂本は鎌倉ですれ違っていたかもしれない。ただし、堂本正樹の実家は裕福だったらしく敗戦後も能や歌舞伎を楽しんだ。この頃、江藤淳が能や歌舞伎を楽しんだとは伝えられていない。当時、江藤が熱中したのは西洋古典音楽であり鎌倉から日比谷公会堂に通ったことが報告されている。そもそも江藤の著作に能や歌舞伎が出てくるのだろうか?ピンとこない、というか出てこないのだよ。能はともかく、この頃から歌舞伎=サブカルチャー嫌悪?
なぜこの本を借りて読んだかというと、三島論に引用されているから。つまり、三島のあの死の動機を「腹を切って血まみれになって、至高のために身を挺して、死ぬこと」という側面もあったとの説の根拠が堂本正樹の証言なのだ。
三島論ではなぜ三島由紀夫はああいう最期を遂げたのか?への回答として、セバスチャンコンプレックスであるとしている(澁澤龍彦 1971、井上隆史2020、 愚記事)。さらに佐藤秀明、『三島由紀夫』(岩波新書 2020)で、「前意味論的欲動」という鍵語で三島由紀夫の作品、言動を読み取る。「前意味論的欲動」とは、「悲劇的なもの」と「身を挺している」のふたつの情動を駆動するものらしい。
難しい鍵語によらず、端的に三島由紀夫の「前意味論的欲動」とは、「腹を切って血まみれになって、至高のために身を挺して、死ぬこと」である。事実、最期にそうした。
腹を切って血まみれになって死ぬことを三島が作品化したのは『憂国』である。その前の作品の『鏡子の家』に血まみれになって死ぬことが出ていた。 (愚記事)
三島にとって死とは社会からの退場というばかりでなく、即物的に自分の肉体が棄損されることを想定し、かつそれを願望していたらしいこと。今、思えば、三島は死体趣味的なところがある。ただの死体趣味ではなく、死体が「棄損」される状態。何かといえば、豊饒の海の3巻目の「暁の寺」でインドはガンジス川の火葬に立ち会う場面。屍が次々と火に委ねられていく場面、炎の中での遺体の動きなどが「いきいき」と描かれている。何のことはない、三島は猟奇的な死体愛好者なのだ。やはり、「病気」だ。「憂国」などではないのだ。
■ 今週見た YouTube 計4時間
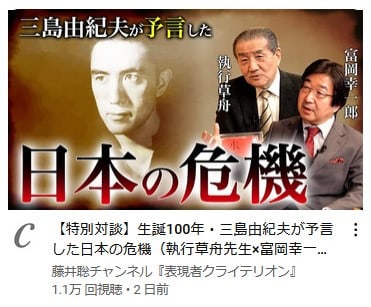
【特別対談】生誕100年・三島由紀夫が予言した日本の危機(執行草舟先生×富岡幸一郎先生)前編、後編
執行草舟の話を富岡幸一郎が聞くという計4時間の動画。全部みた。そもそも、執行草舟は怪しい、というのが、おいらの「偏見」だ。胡散臭い。そして、富岡幸一郎。おいらは、富岡幸一郎を、江藤淳や西部邁を知って数年後に知った。当時は、この「兄ちゃん」が江藤淳や西部邁を「渡り歩き」、ついには執行草舟にたどり着くとは想像もしなかったが。


 顔がきれいなんです。生前の三島に会っていたら「ほだしを掛けられた」かも?
顔がきれいなんです。生前の三島に会っていたら「ほだしを掛けられた」かも?
■




















