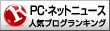躰道部OB会名称の由来について説明
躰道部OB会の名称「忨沁会(げんしんかい)」の由来について説明をした。
東京国際大学体育会躰道部は、昭和40年(1965年)10月6日から、玄制流空手道部として宗家であります祝嶺正献最高師範の承諾のもとに大学のクラブ活動としてスタートしました。創部の時には一期生の20名が参加。
名称は、玄制流空手道部 ⇒ 空手躰道部 ⇒ 躰道部 と変更しました。
一期生が卒業する昭和44年(1969年)3月に、躰道部OB会を組織するにあたり、その名称については、現在カナダで活躍中の辻内健君が中心となり皆で検討をして、「忨沁会(げんしんかい)」と命名しました。
その名称の由来は、
大学の校歌の歌詞の中で、「秩父連邦遥かなり」と「清き入間のせせらぎよ」との関連付けした。
『忨』(げん)は、玄制流の「玄」の音を入れることと肉体の元気さを表現すること。そして、大学から展望できる秩父の山々を表わすことで、りっしんべんを使用したのです。
『沁』(しん)は、精神の心を表現する意味で用いました。そして、大学の傍に入間川が流れていることで水を意味するさんずいを使用したのです。
躰道の基本理念である「精神と肉体の同時育成」の意味も含めて、OB会の名称に盛り込むことで、「忨沁会」と命名をしました。
東京国際大学躰道部OB会は、躰道の創始者である祝嶺正献最高師範の掲げる躰道の理念を基本に忘れることなく、社会で還元できる活動をすることを目的にその名称について「忨沁会(げんしんかい)」と命名したのです。
(12月2日記)
躰道部OB会の名称「忨沁会(げんしんかい)」の由来について説明をした。
東京国際大学体育会躰道部は、昭和40年(1965年)10月6日から、玄制流空手道部として宗家であります祝嶺正献最高師範の承諾のもとに大学のクラブ活動としてスタートしました。創部の時には一期生の20名が参加。
名称は、玄制流空手道部 ⇒ 空手躰道部 ⇒ 躰道部 と変更しました。
一期生が卒業する昭和44年(1969年)3月に、躰道部OB会を組織するにあたり、その名称については、現在カナダで活躍中の辻内健君が中心となり皆で検討をして、「忨沁会(げんしんかい)」と命名しました。
その名称の由来は、
大学の校歌の歌詞の中で、「秩父連邦遥かなり」と「清き入間のせせらぎよ」との関連付けした。
『忨』(げん)は、玄制流の「玄」の音を入れることと肉体の元気さを表現すること。そして、大学から展望できる秩父の山々を表わすことで、りっしんべんを使用したのです。
『沁』(しん)は、精神の心を表現する意味で用いました。そして、大学の傍に入間川が流れていることで水を意味するさんずいを使用したのです。
躰道の基本理念である「精神と肉体の同時育成」の意味も含めて、OB会の名称に盛り込むことで、「忨沁会」と命名をしました。
東京国際大学躰道部OB会は、躰道の創始者である祝嶺正献最高師範の掲げる躰道の理念を基本に忘れることなく、社会で還元できる活動をすることを目的にその名称について「忨沁会(げんしんかい)」と命名したのです。
(12月2日記)