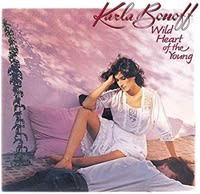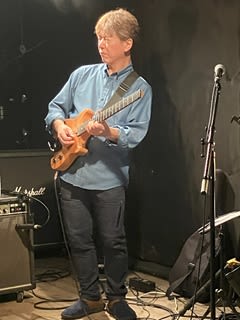










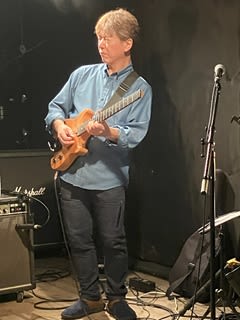







最近特殊詐欺の電話がかかってきた。
ある日の午後、僕のスマホに着信があった。「050」で始まる全く知らない番号からである。海外からかけてきてるような感じもして、怪しさ300%なので、出来れば着信があっても出たくないのだが、たまにお客様からの電話だったりする事もあるので、一応出たのである。
出ると、いきなり相手の男(中年のオジサンと思う)が「MFCオーナー(もちろん、実際には本名^^;)さんの携帯ですか?」と尋ねてくる。個人情報は割れてるらしい。何の電話かも分からないし、仕方ないので「そうです」と認め、そのまま話を聞いてみると、電話をかけてきた男は福井県警の者ですと名乗り、訳分からん事を話し始めた。
オジサン曰く、「犯罪に関わる事なので、出来れば周囲に人がいない場所に移動して下さい」なんて言った後に続けて「いわゆる振り込め詐欺を働いていた男が福井県警に身柄を拘束された。その男の名はホリウチツヨシ(ご存知ですか?と聞かれた)、自宅捜査をしたところ何十枚というキャッシュカードが押収され、その中にMFCオーナー名義のPayPay銀行のキャッシュカードがあった。これは本人が身分を証明するものを提示しないと作れない物であり、他人が偽装するのは難しい。実際に、このキャッシュカードの口座に被害者が振込しており、犯罪に使われた事は間違いないので、口座名義人も共犯者という扱いとなる」なんて言う訳だ。いきなりきたか。
男は続けて、「貴方は犯罪に加担していない、という事を証明しなければならない。我々も疑っている訳ではない。なので、身分を証明出来る物を持参の上、すぐに福井県警に来れますか?」などと無理難題言うので、無理です、と返すと、「では、捜査担当者と電話でお話して捜査に協力して貰う事は出来ますか?」なんて言うので、「この話が本当なら、こちらに警察が来るべきでは?」と答えたら、「それは管轄が違うので出来ない」とかブツブツ言いつつ、「協力して頂けないと貴方を共犯として起訴しなくてはならなくなります。それでもいいのですか?」と、ついに最後のカードを切ってきたみたいな感じだったので(笑)、「好きにして下さい。法に従いますから」なんて事を言ったら、電話は切れた。
一応、僕にも特殊詐欺云々の知識はあるし、いかがわしい電話番号でもあったので、電話に出た時点で詐欺を疑ってはいた。ただ、話を聞いてしまったのは、相手が福井県警の名前を出したからだ。僕が福井県に縁もゆかりもなければスルーするところだが、福井県に縁もゆかりもあるもんで^^;、もしかして、自分の知ってる人に関わる事なのかも、とつい思ってしまったのである。結局関係なかったけど。
電話をかけてきた男は、僕の本名のみならず現住所も知っていたので、個人情報は掴んでいるらしい。恐ろしい世の中だ。話を聞く前から詐欺と疑っていた事もあり、相手の問いには、あまりまともに答えてないけど、福井県というのが気になって、詐欺と疑いつつ疑い切れないような、なんかもやもやした物を感じながら、男との会話を続けていた。会話の途中に何回か、本当に警察の人なんですか?と言ってしまったけど、相手は動じる事はなく「本当ですよ」と軽く言うだけだった。そりゃそうだよね(笑)
結局、相手が一方的に話して電話を切った感じになった訳だが、冷静に考えてみると、相手が僕に何をさせたかったのか、がよく分からない。仮に、相手の「福井県警に来れるか」という問いに対して「行きます。すぐ行きます」と答えていたらも相手はどう反応したのか。この手の特殊詐欺というのは、最終的にはターゲットから金を巻き上げるのが目的と思うが、今回の電話での会話を思い返してみても、どごで僕が金を振り込む展開になるのか、さっぱり見当がつかない(笑)
詐欺の電話を切ったあと、たまたま妻から電話があったので、たった今の詐欺電話の事を話すと、福井県警に直接電話して確認してくれたみたいで、福井県警からは「詐欺です。近頃多いんです。福井県警の名前を使われています。その手の電話には絶対反応しないで下さい。050で始まる番号および番号非通知には、絶対に出てはいけません」と言われたらしい。正真正銘の詐欺電話だったというオチだった訳だ。
前述したけど、端から詐欺と思い込んでいたけど、反面、もしかして本当かも、なんて思ってたのは事実。僕の名前とか住所とか、本当の事も散りばめてきたからね。勝手にキャッシュカードを作られる、なんてのもありそうな話だし(笑) 詐欺師は100%嘘を述べるのではなく、10%くらいは本当の事を混ぜるらしい。その方が信憑性を打ち出せるんだそうな。ま、何とか踏み止まれて良かったかも。
という訳です。話には聞いていたけど、実際に体験するとは思わなんだ。ほんと、言われているように、まともに話をせず、すぐに裏を取った方がいい、というのはやはり正しい対応なんだな、というのを実感した。でも、実際に経験すると、パニックになってしまうかも。ほんと気をつけないと。明日は我が身と皆さん思ってた方がいいと思います。
治にいて乱を忘れず。大事です(しみじみ)