本日の音楽はハイドンで行きまぁ~す♪
YOUTUBE(↑)をクリックしてくださいね。
我が家のワンコ、ドガティ君。ジャック・ラッセル・テリアだ。

ほんの一か月ほど前に静岡県のブリーダーさんから、鎌倉七里ガ浜の我が家に来たばかり。
我が家の先住犬はアイリッシュ・セターの茶々之介氏だった(たいへん寂しいことながら、過去の話)。

現在のドガティ君と同じ月齢の頃(それは2004年のことだが)、大変手のかかるしかも大型犬だった茶々之介氏と比較すると、ドガティ君はあまり手がかからず聞き分けも良いため、「お利口」と言われている。
さて、我が家のドガティ君はどうしてドガティと名付けられたか?
近所の人に「この子の名前はドガティです」と言うと、よくその名前の由来について質問される。
だからここでそれを説明しておく。
ドガティはDOUGHERTYと綴る。
これはアイルランド系の姓である。ファミリー・ネームであって、ファースト・ネームではない。
いくら相手を姓で呼ぶことが好きな日本人でも、犬の名前に姓をつけることはない。
しかし敢えて私と妻はこのジャック・ラッセル・テリアをDOUGHERTY(ドガティ)と呼ぶことにした。
アイルランド系の姓であるDOUGHERTYは、もともとはもっと複雑な綴りである。なにせ英語ではないのだ。
しかし英語になると(そして特にアメリカになると)、敢えてカタカナで表現すればドハティとかドカティとかドーティなどと発音され、そのため綴りもどんどん変化し、UもGもなくなり、DOHERTYなどと書かれたりすることもある。
実はそういう姓を持った、そして私がとても世話になったアメリカ人がいるのである。
ドガティの名前はその人(男性)からもらったものだ。
ドガティ氏のおじいさんはアイルランドからアメリカに移民として入った。

【コークの港を出てアメリカを目指す人たちの画 Howstuffworks.com】
そしてそのそのおじいさんはゲーリック(ケルト(の言葉))の発音を大事にして、アメリカにおいて自分の姓を名乗る時もそれで通した。
つまり彼のおじいさんはアメリカに渡ってからも、ドハティなどとは名乗りも綴りもせず、音的には「ドガティ」と名乗り英語としてはDOUGHERTYと綴ったのである。
私はその話を、私が世話になったドガティ氏(移民三代目)から聞いた。
いい話だなぁ・・・と思ったのが、今から8年くらい前のことだ。
そしてその後我が家で新たにジャック・ラッセル・テリアを飼うことになり、名前を決める際、面白い名前だからそれにしようということになった。
改めて、私は私が世話になったそのアメリカ人であるドガティ氏に連絡し、「日本でさえ犬を姓で呼ぶことなど一般的にはないのだが、新しく家族になるジャック・ラッセル・テリアを私はあなたの姓である「ドガティ」と呼ぶことにする」と連絡した。
アメリカのドガティ氏からは「ありがとう。私の姓をその犬の名前にしてくれるって、とても名誉なことと思うよ。一度そのドガティ君に会いたいものだ」との答えがあった。
ドガティ氏自身もアメリカでルーシーと呼ばれるスプードル(なんらかのスパニエルとプードルを掛け合わせたワンコ)と暮らす愛犬家である。
*****************************************************
ところで最近のデイリー・メイル紙のウェブサイトにおかしな記事が載っていた。
英国のエチケット専門家であるウィリアム・ハンソン氏(なんとも怪しい人だが、いろんな職業があるものだ)が、英国の社会階層とその愛犬(が純血種である場合)の犬種にみられる一般的傾向を説明している。

そもそも、大昔から純血種なんて犬は存在していたわけではなく、ほとんどが人為的にむりやり作られたものだ。
ドガティ君が属するジャック・ラッセル・テリアなんてその代表格である。
初期のジャック・ラッセル・テリアは獲物を追って穴に入り込むことができるという特殊な目的のためにつくられたらしい。
話を戻すと、純血種のうち、過半数は英国で作出されていて、ウィリアム・ハンソン氏の解説は極めて英国的なお話なのだ。
ちなみに上流階級が飼う犬は労働犬であることが一般的だ。
労働とはこの場合農業を指すわけではなく、狩猟を指す。
だから牧羊犬などではなく、狩猟犬が上流階級に好まれる。
その中で最高なのがラブラドール・リトリバーである。しかもクリームではなく、黒でないといけないらしい。
さらに面白いのは、ラブラドールと同じ目的で使われるゴールデン・リトリバーは、見た目がファンシーすぎて上流階級的ではないらしい。
茶々之介氏のアイリッシュ・セターなども同様で、それらは中流階級的なのだそうだ。
また上流階級が好むのは大型犬とは限らない。
小さくても「狩猟」ということと結びついた犬種が好まれている。
女王がウェルシュ・コーギー・ペンブロークをお好きなのは有名な話。
ドガティ君のジャック・ラッセル・テリアもその部類である。
このように(↓)。

ちなみに、この鼻持ちならないウィリアム・ハンソン氏の解説によれば、上流階級がその愛犬に利用する首輪はシンプルなものでなければならないらしい。
実用的でシンプルなもの。
ドガティ君、君の首輪はそれに近い(それがどうした?)。

ドガティ君のは単に頑丈というだけだが。
大阪府八尾市にある岡野製作所の頑丈な首輪だ。
一般的に、首輪についている金属製のプレートに愛犬の名前を打ち込むことが行われる。
しかしその行為は上流階級的ではないという。
ハンソン氏によれば、上流階級はここに自分の姓と電話番号だけを打ち込むのだそうである。
上流階級はこういう面では非常に合理的である。たしかに愛犬の名前をここに打ち込んでもあまり意味がない。
ドガティ君用には、首輪に最初からとりつけられた金属製プレートにそれをするのではなく、アルミの迷子札を別途つくり、それを首から下げさせている。
そこにはおちゃ家の姓と電話番号が3つ打ち込んである。

その点もドガティ君グッズは英国上流階級的だ(だから何?)。
ハンソン氏はおそらくこの本を参照しているのものと、私は推測している。
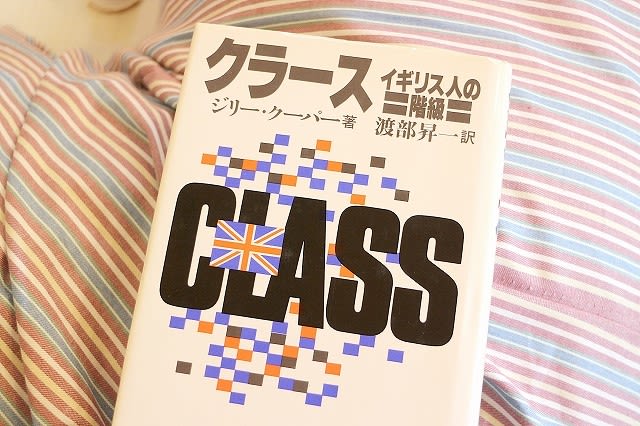
もう40年近く前に広く英国社会階層について書かれた本で、そこに社会階層とその愛犬の関係を説明している部分があるからだ。
その一部に、ハンソン氏の記述と非常に近いものがある。

ちなみにこの本によれば、上流階級の好きな音楽はモーツアルト、ヴィヴァルディ、ハイドン、パーセルらしい。
日本人が好きなブラームスやベートーベンは中流階級的だそうだ。
そんなわけでこの記事の冒頭にハイドンのYOUTUBEを貼り付けている。
日本の本であるが、こんなのもある。
飯田操氏の本だ。
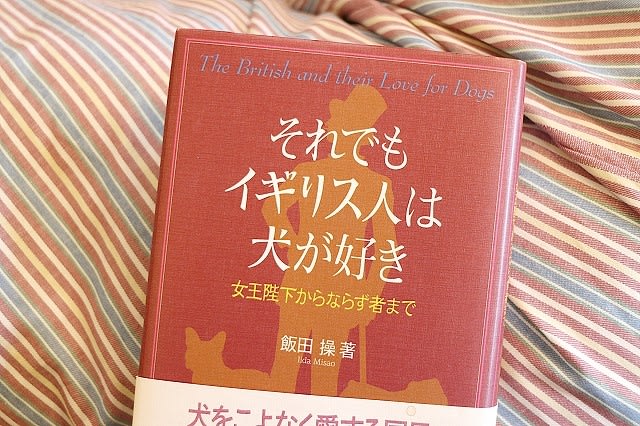
これは学術的に冷徹に英国の犬の文化や歴史を分析したもので、ここで書いてきたようなことを深く掘り下げることができる本だ。
さらに下田尾誠氏のこれ。

これもまた学術的な本である。
ここにもジャック・ラッセル・テリアに関する解説がある。
ちなみに下の画像にある赤いハイライトを施したのは私ではない。

私はこの本を古書店で購入している。この本の以前の持ち主によるハイライトらしい。
まったく別の話になるが、おいしいおいしいマトン・カレー。

自慢しちゃう。
おいしいですよ。
クローブやカルダモンがきいた大人のカレーだ。

とってもスパイシー。
YOUTUBE(↑)をクリックしてくださいね。
我が家のワンコ、ドガティ君。ジャック・ラッセル・テリアだ。

ほんの一か月ほど前に静岡県のブリーダーさんから、鎌倉七里ガ浜の我が家に来たばかり。
我が家の先住犬はアイリッシュ・セターの茶々之介氏だった(たいへん寂しいことながら、過去の話)。

現在のドガティ君と同じ月齢の頃(それは2004年のことだが)、大変手のかかるしかも大型犬だった茶々之介氏と比較すると、ドガティ君はあまり手がかからず聞き分けも良いため、「お利口」と言われている。
さて、我が家のドガティ君はどうしてドガティと名付けられたか?
近所の人に「この子の名前はドガティです」と言うと、よくその名前の由来について質問される。
だからここでそれを説明しておく。
ドガティはDOUGHERTYと綴る。
これはアイルランド系の姓である。ファミリー・ネームであって、ファースト・ネームではない。
いくら相手を姓で呼ぶことが好きな日本人でも、犬の名前に姓をつけることはない。
しかし敢えて私と妻はこのジャック・ラッセル・テリアをDOUGHERTY(ドガティ)と呼ぶことにした。
アイルランド系の姓であるDOUGHERTYは、もともとはもっと複雑な綴りである。なにせ英語ではないのだ。
しかし英語になると(そして特にアメリカになると)、敢えてカタカナで表現すればドハティとかドカティとかドーティなどと発音され、そのため綴りもどんどん変化し、UもGもなくなり、DOHERTYなどと書かれたりすることもある。
実はそういう姓を持った、そして私がとても世話になったアメリカ人がいるのである。
ドガティの名前はその人(男性)からもらったものだ。
ドガティ氏のおじいさんはアイルランドからアメリカに移民として入った。

【コークの港を出てアメリカを目指す人たちの画 Howstuffworks.com】
そしてそのそのおじいさんはゲーリック(ケルト(の言葉))の発音を大事にして、アメリカにおいて自分の姓を名乗る時もそれで通した。
つまり彼のおじいさんはアメリカに渡ってからも、ドハティなどとは名乗りも綴りもせず、音的には「ドガティ」と名乗り英語としてはDOUGHERTYと綴ったのである。
私はその話を、私が世話になったドガティ氏(移民三代目)から聞いた。
いい話だなぁ・・・と思ったのが、今から8年くらい前のことだ。
そしてその後我が家で新たにジャック・ラッセル・テリアを飼うことになり、名前を決める際、面白い名前だからそれにしようということになった。
改めて、私は私が世話になったそのアメリカ人であるドガティ氏に連絡し、「日本でさえ犬を姓で呼ぶことなど一般的にはないのだが、新しく家族になるジャック・ラッセル・テリアを私はあなたの姓である「ドガティ」と呼ぶことにする」と連絡した。
アメリカのドガティ氏からは「ありがとう。私の姓をその犬の名前にしてくれるって、とても名誉なことと思うよ。一度そのドガティ君に会いたいものだ」との答えがあった。
ドガティ氏自身もアメリカでルーシーと呼ばれるスプードル(なんらかのスパニエルとプードルを掛け合わせたワンコ)と暮らす愛犬家である。
*****************************************************
ところで最近のデイリー・メイル紙のウェブサイトにおかしな記事が載っていた。
英国のエチケット専門家であるウィリアム・ハンソン氏(なんとも怪しい人だが、いろんな職業があるものだ)が、英国の社会階層とその愛犬(が純血種である場合)の犬種にみられる一般的傾向を説明している。

そもそも、大昔から純血種なんて犬は存在していたわけではなく、ほとんどが人為的にむりやり作られたものだ。
ドガティ君が属するジャック・ラッセル・テリアなんてその代表格である。
初期のジャック・ラッセル・テリアは獲物を追って穴に入り込むことができるという特殊な目的のためにつくられたらしい。
話を戻すと、純血種のうち、過半数は英国で作出されていて、ウィリアム・ハンソン氏の解説は極めて英国的なお話なのだ。
ちなみに上流階級が飼う犬は労働犬であることが一般的だ。
労働とはこの場合農業を指すわけではなく、狩猟を指す。
だから牧羊犬などではなく、狩猟犬が上流階級に好まれる。
その中で最高なのがラブラドール・リトリバーである。しかもクリームではなく、黒でないといけないらしい。
さらに面白いのは、ラブラドールと同じ目的で使われるゴールデン・リトリバーは、見た目がファンシーすぎて上流階級的ではないらしい。
茶々之介氏のアイリッシュ・セターなども同様で、それらは中流階級的なのだそうだ。
また上流階級が好むのは大型犬とは限らない。
小さくても「狩猟」ということと結びついた犬種が好まれている。
女王がウェルシュ・コーギー・ペンブロークをお好きなのは有名な話。
ドガティ君のジャック・ラッセル・テリアもその部類である。
このように(↓)。

ちなみに、この鼻持ちならないウィリアム・ハンソン氏の解説によれば、上流階級がその愛犬に利用する首輪はシンプルなものでなければならないらしい。
実用的でシンプルなもの。
ドガティ君、君の首輪はそれに近い(それがどうした?)。

ドガティ君のは単に頑丈というだけだが。
大阪府八尾市にある岡野製作所の頑丈な首輪だ。
一般的に、首輪についている金属製のプレートに愛犬の名前を打ち込むことが行われる。
しかしその行為は上流階級的ではないという。
ハンソン氏によれば、上流階級はここに自分の姓と電話番号だけを打ち込むのだそうである。
上流階級はこういう面では非常に合理的である。たしかに愛犬の名前をここに打ち込んでもあまり意味がない。
ドガティ君用には、首輪に最初からとりつけられた金属製プレートにそれをするのではなく、アルミの迷子札を別途つくり、それを首から下げさせている。
そこにはおちゃ家の姓と電話番号が3つ打ち込んである。

その点もドガティ君グッズは英国上流階級的だ(だから何?)。
ハンソン氏はおそらくこの本を参照しているのものと、私は推測している。
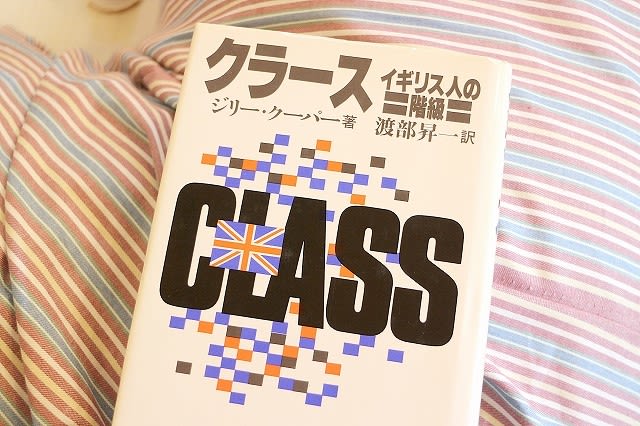
もう40年近く前に広く英国社会階層について書かれた本で、そこに社会階層とその愛犬の関係を説明している部分があるからだ。
その一部に、ハンソン氏の記述と非常に近いものがある。

ちなみにこの本によれば、上流階級の好きな音楽はモーツアルト、ヴィヴァルディ、ハイドン、パーセルらしい。
日本人が好きなブラームスやベートーベンは中流階級的だそうだ。
そんなわけでこの記事の冒頭にハイドンのYOUTUBEを貼り付けている。
日本の本であるが、こんなのもある。
飯田操氏の本だ。
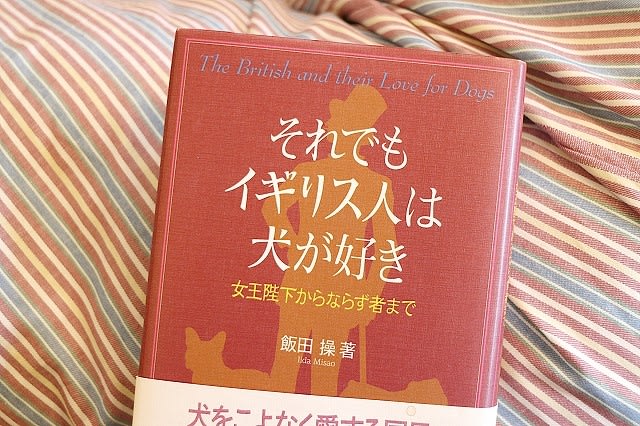
これは学術的に冷徹に英国の犬の文化や歴史を分析したもので、ここで書いてきたようなことを深く掘り下げることができる本だ。
さらに下田尾誠氏のこれ。

これもまた学術的な本である。
ここにもジャック・ラッセル・テリアに関する解説がある。
ちなみに下の画像にある赤いハイライトを施したのは私ではない。

私はこの本を古書店で購入している。この本の以前の持ち主によるハイライトらしい。
まったく別の話になるが、おいしいおいしいマトン・カレー。

自慢しちゃう。
おいしいですよ。
クローブやカルダモンがきいた大人のカレーだ。

とってもスパイシー。

















