書店の店頭で見つけた。
共同通信社が取材、配信したものを文庫化したものだそうだ。
本文庫の発行は2015年6月1日
この取材は、2010年4月~2011年2月に行われたらしいが、
現状は全く変わっていない。
本書の構成は
第1章 お金なくても学びたい―定時制高校で学ぶ若者の実態
第2章 貧困の連鎖を断ち切れ―給食費や学校納付金の未納問題から子どもの家庭の実態にせまる
第3章 保健室からのSOS―朝食を食べてこない子の背景に見る家庭の実態
第4章 幼い命育む砦に―保育園における園児と保護者の実態
となっている。
いずれの章も、実態とその現場の大人が子どもたちと保護者を支援する取り組みも伝えている。
だから読んでいる途中、一定救われた思いがした。
第1章の定時制高校に通う子どもたちは
『お金がなくても勉強したい』『高校だけは卒業しないと将来につなげない」
と必死に頑張っている。
高校生でありながら、同時に家計も支え手の一人でもある。
朝、昼、深夜 の3つのバイトを掛け持ちで学費と生活費を稼ぐ。
当然居眠り、遅刻、健康を害するなど
バイトも長続きしない
本人の任に期さないが 周りには本人の気のゆるみと映り、首になる
文字通り体力の限界を超えて働き
体をボロボロにし、
それでも高校を卒業したいと必死に働いている。
民主党政権が高校の無償化を実施したが、
授業料は無料でも、給食費などのその他の費用は有料で、それも子どもには重い負担である。
自民党・公明党政権は そうした子どもたちの現状に追い打ちをかけるように
所得制限を設け 教育の機会均等を投げ捨て
生保世帯の全日の高校生の奨学金を所得認定する。
冷たい仕打ちが
貧困対策法の実行に責任を負うべき国と自治体の福祉の部署で行われているのだ。
第2章 貧困の連鎖を断ち切れでは
大阪市の中学校の弁当代未納問題から実態が告発されている。
請求しても払ってもらえない。
こうした地域の学校では
貧困の連鎖の解消と子どもの社会的自立の支援を教育課程の中心に据え、
地域とのネットワークを活用し支援に取り組んでいる
救いを感じるゆえんである。
子どもの家計の実態を知り、就学援助の手続きの支援
保護者の精神疾患にもよりそい、受診をさせることで
家庭の自律も支援する取り組みなど
これらは
学校現場に各校1人ずつのSSW(スクール・ソーシャルワーカー)の必要性を如実に示している。
学校給食命綱ともなる子ども時代
大阪市は
弁当と給食の併用だったが
保護者負担の公平の観点から給食を廃止し全員弁当持参に変えた
結果
弁当を持ってこられない子は業者弁当を注文することに
(わが東村山市の方式と酷似)
そしてこの章冒頭の弁当代未納につながるのである。
取材の中で担当教諭が
「給食は、栄養面だけでなく精神面でも安定して周りの子と一緒に食事ができる。
経済的な貧困は、人間関係をつくれず孤立するもっと深い貧困へと子どもたちを追いやる」
と語っているが全く同感である。
第3章 保健室からのSOS では
小学校の保健室に
朝御飯を食べてこなかった児童たちが養護教諭の到着を待っている風景から始まる。
ベテランの養護教諭は
学校の保健室はこどもたちのSOSに気付く始発点
だという。
そして、本気で子どもの貧困に向き合う。
保健室で給食の残りのパンと牛乳を食べさせ、
家庭にも介入して家族にもお節介をやき
福祉に繋げるなど、
学校があげて一人の児童、生徒のしあわせを願って支援をしていた。
学校も決して暇ではない
が、
目の前の子どもの抱えた問題を見過ごさず、その解決へ支援の手をチームで差し伸べる」。
そこに救いがある。
貧困のために大事な子ども時代を奪ってはいけない
と養護教諭は取り組みを続ける。
第4章 幼い命育む砦に は
シングルで子どもを育てる母親の二重三重の仕事や健康、精神的困難の実態を明らかにしている
そして
保育園がその子どもの命を守る砦としてはたしている役割を紹介している。
家族で車に寝泊まりし生活をしている家族
養護施設に結局預けられる子ども達
それでも
お母さんと暮らすことを望む子どもたち
シングルで孤独に耐えながら子育てする母親
それを保育園がつなげ
シングルマザーの会を園で立ち上げ
お互い励ましあう関係を構築するとりくみ
ここでも
一人一人の子どもの幸せのために頑張ってくれる保育士たちがいることに救われる。
子どもの貧対策法は生まれや育ちで子どもの将来が決まってはならない
とその理念で謳っている。
しかし、
子どもの貧困対策大綱が決定されても
貧困を減らす数値目標や対策は具体化していない。
そして現に
生まれや育ち、家庭の所得格差が、子どもの上に大きな影を落し
将来の希望を持てない子どもたちが大勢存在しているのである。
各省の終わりに有識者からの提言なども掲載している。
この本を読みつつ
わが東村山市の子どもの実態とリンクさせ
わが東村山市においても、配置されたSSWが子どもの生きづらさに心を寄せ
家庭の支援も含めて
一人の子どもが幸せになることができる支援を期待したいと切実に思った。
教育委員会、学校関係者、議会の皆さんが絶対読むべき書籍であるとおもう。
共同通信社が取材、配信したものを文庫化したものだそうだ。
本文庫の発行は2015年6月1日
この取材は、2010年4月~2011年2月に行われたらしいが、
現状は全く変わっていない。
本書の構成は
第1章 お金なくても学びたい―定時制高校で学ぶ若者の実態
第2章 貧困の連鎖を断ち切れ―給食費や学校納付金の未納問題から子どもの家庭の実態にせまる
第3章 保健室からのSOS―朝食を食べてこない子の背景に見る家庭の実態
第4章 幼い命育む砦に―保育園における園児と保護者の実態
となっている。
いずれの章も、実態とその現場の大人が子どもたちと保護者を支援する取り組みも伝えている。
だから読んでいる途中、一定救われた思いがした。
第1章の定時制高校に通う子どもたちは
『お金がなくても勉強したい』『高校だけは卒業しないと将来につなげない」
と必死に頑張っている。
高校生でありながら、同時に家計も支え手の一人でもある。
朝、昼、深夜 の3つのバイトを掛け持ちで学費と生活費を稼ぐ。
当然居眠り、遅刻、健康を害するなど
バイトも長続きしない
本人の任に期さないが 周りには本人の気のゆるみと映り、首になる
文字通り体力の限界を超えて働き
体をボロボロにし、
それでも高校を卒業したいと必死に働いている。
民主党政権が高校の無償化を実施したが、
授業料は無料でも、給食費などのその他の費用は有料で、それも子どもには重い負担である。
自民党・公明党政権は そうした子どもたちの現状に追い打ちをかけるように
所得制限を設け 教育の機会均等を投げ捨て
生保世帯の全日の高校生の奨学金を所得認定する。
冷たい仕打ちが
貧困対策法の実行に責任を負うべき国と自治体の福祉の部署で行われているのだ。
第2章 貧困の連鎖を断ち切れでは
大阪市の中学校の弁当代未納問題から実態が告発されている。
請求しても払ってもらえない。
こうした地域の学校では
貧困の連鎖の解消と子どもの社会的自立の支援を教育課程の中心に据え、
地域とのネットワークを活用し支援に取り組んでいる
救いを感じるゆえんである。
子どもの家計の実態を知り、就学援助の手続きの支援
保護者の精神疾患にもよりそい、受診をさせることで
家庭の自律も支援する取り組みなど
これらは
学校現場に各校1人ずつのSSW(スクール・ソーシャルワーカー)の必要性を如実に示している。
学校給食命綱ともなる子ども時代
大阪市は
弁当と給食の併用だったが
保護者負担の公平の観点から給食を廃止し全員弁当持参に変えた
結果
弁当を持ってこられない子は業者弁当を注文することに
(わが東村山市の方式と酷似)
そしてこの章冒頭の弁当代未納につながるのである。
取材の中で担当教諭が
「給食は、栄養面だけでなく精神面でも安定して周りの子と一緒に食事ができる。
経済的な貧困は、人間関係をつくれず孤立するもっと深い貧困へと子どもたちを追いやる」
と語っているが全く同感である。
第3章 保健室からのSOS では
小学校の保健室に
朝御飯を食べてこなかった児童たちが養護教諭の到着を待っている風景から始まる。
ベテランの養護教諭は
学校の保健室はこどもたちのSOSに気付く始発点
だという。
そして、本気で子どもの貧困に向き合う。
保健室で給食の残りのパンと牛乳を食べさせ、
家庭にも介入して家族にもお節介をやき
福祉に繋げるなど、
学校があげて一人の児童、生徒のしあわせを願って支援をしていた。
学校も決して暇ではない
が、
目の前の子どもの抱えた問題を見過ごさず、その解決へ支援の手をチームで差し伸べる」。
そこに救いがある。
貧困のために大事な子ども時代を奪ってはいけない
と養護教諭は取り組みを続ける。
第4章 幼い命育む砦に は
シングルで子どもを育てる母親の二重三重の仕事や健康、精神的困難の実態を明らかにしている
そして
保育園がその子どもの命を守る砦としてはたしている役割を紹介している。
家族で車に寝泊まりし生活をしている家族
養護施設に結局預けられる子ども達
それでも
お母さんと暮らすことを望む子どもたち
シングルで孤独に耐えながら子育てする母親
それを保育園がつなげ
シングルマザーの会を園で立ち上げ
お互い励ましあう関係を構築するとりくみ
ここでも
一人一人の子どもの幸せのために頑張ってくれる保育士たちがいることに救われる。
子どもの貧対策法は生まれや育ちで子どもの将来が決まってはならない
とその理念で謳っている。
しかし、
子どもの貧困対策大綱が決定されても
貧困を減らす数値目標や対策は具体化していない。
そして現に
生まれや育ち、家庭の所得格差が、子どもの上に大きな影を落し
将来の希望を持てない子どもたちが大勢存在しているのである。
各省の終わりに有識者からの提言なども掲載している。
この本を読みつつ
わが東村山市の子どもの実態とリンクさせ
わが東村山市においても、配置されたSSWが子どもの生きづらさに心を寄せ
家庭の支援も含めて
一人の子どもが幸せになることができる支援を期待したいと切実に思った。
教育委員会、学校関係者、議会の皆さんが絶対読むべき書籍であるとおもう。












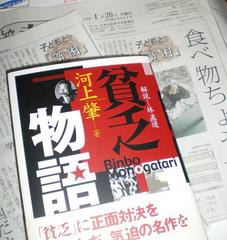
 大正時代の経済学者、歴史の時間に学んだ 河上肇先生が書かれた
大正時代の経済学者、歴史の時間に学んだ 河上肇先生が書かれた

 良いお天気が続いています
良いお天気が続いています さて いま 仕事の合間を縫って
さて いま 仕事の合間を縫って 読み返して 小学校 中学校時代の自分の気持ちを思い出しました
読み返して 小学校 中学校時代の自分の気持ちを思い出しました なかでも エレナ・ポーターの『スー姉さん』 という本は
なかでも エレナ・ポーターの『スー姉さん』 という本は 私が 本というものを初めに手に入れたのが
私が 本というものを初めに手に入れたのが いまでも バッグの中には何かしら本が入っています
いまでも バッグの中には何かしら本が入っています