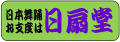自分のお教室に生かすために…
ボディーに黒留袖の着せ付けをしているのはKさん。
日頃の彼女は、お客さまも多い「素敵な喫茶店」のオーナー。
仕事の他には「きもの好き」が集まり、「着付け教室」もされています。
「生徒さんにもっと多くのことを教えてあげるために、着付けをもっと深く学びたい…」と「きつけ塾いちき」にお越しになり、特に着せ付けを中心に学ばれています。何と向学心のある方でしょうか。
担当は木下室長で、笑いの絶えない教室のようです。
Kさんは、「本当に楽しくお勉強させて頂いています」とのこと。
これまで「きつけ塾いちき」は、お望みの着付け技術を、お好きな時に提供してまいりました。
ですから、他の着付け教室の先生方もお勉強にお越し頂いているのです。
学ぶという事には、「時間や年令・着付け教室の違い」など関係ありませんからね。
K先生、がんばって下さい。今後もみんなで応援させて頂きます。

 ●
● ●
●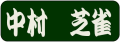 ●
●
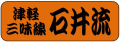 ●
● ●
●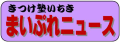 ●
●
 ●
● ●
●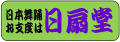
ボディーに黒留袖の着せ付けをしているのはKさん。
日頃の彼女は、お客さまも多い「素敵な喫茶店」のオーナー。
仕事の他には「きもの好き」が集まり、「着付け教室」もされています。
「生徒さんにもっと多くのことを教えてあげるために、着付けをもっと深く学びたい…」と「きつけ塾いちき」にお越しになり、特に着せ付けを中心に学ばれています。何と向学心のある方でしょうか。
担当は木下室長で、笑いの絶えない教室のようです。
Kさんは、「本当に楽しくお勉強させて頂いています」とのこと。
これまで「きつけ塾いちき」は、お望みの着付け技術を、お好きな時に提供してまいりました。
ですから、他の着付け教室の先生方もお勉強にお越し頂いているのです。
学ぶという事には、「時間や年令・着付け教室の違い」など関係ありませんからね。
K先生、がんばって下さい。今後もみんなで応援させて頂きます。

 ●
● ●
●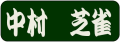 ●
●
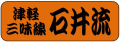 ●
● ●
●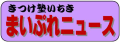 ●
●
 ●
● ●
●