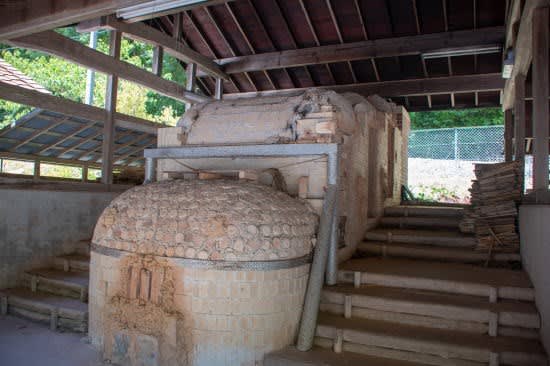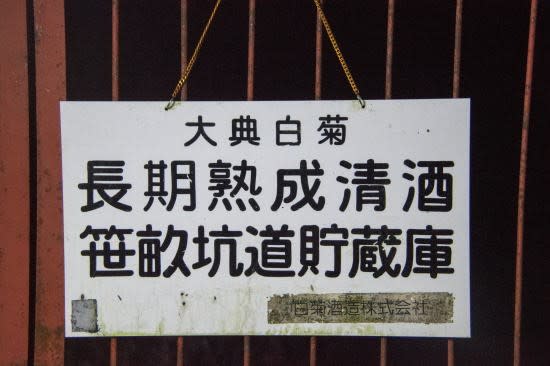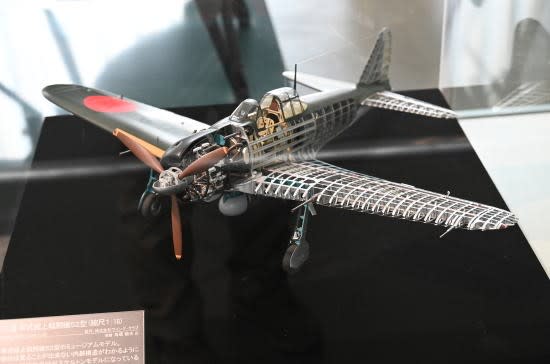訪問日:令和4年11月4日(金)
奥津渓の紅葉を楽しんだ後、蒜山高原を訪ねました。ナビの行き先を設定すると、なぜかいったん北上し、鳥取三朝町に向かいました。
目的地のジャージーランドに着くと、残念ながらジャージー牛の放牧はありませんでした。ちょっと残念ですが仕方ありません。
そのかわり、コスモスが斜面にきれいに咲いているではありませんか。これは予想していなかったのでとてもラッキーでした。
コスモス畑の撮影を堪能したあと、鳥取県境の鬼女台に向かいました。駐車場はいっぱいで少し空きを待つ状態でしたが何とか入れることができました。この頃から北方面に雲がかかるようになりました。烏ヶ山(からすがせん)は見渡せますが、点前に雲がかかり被写体としては残念な気象条件です。
本当は、大山南壁の絶景ポイント鍵掛峠まで足を延ばしたかったのですが、あまり期待できそうにありません。
結局、江府町御机(奥大山)の茅葺小屋を撮影したあと、帰途につきました。

残念ながら放牧はもう行われていないようでした。

上蒜山の紅葉

遠くにジャージー牛がいればどこまでも歩く道

ススキと上蒜山

ひるぜんジャージーランド 売店の濃厚なソフトクリームが有名
(コスモス畑)

何とこの季節にコスモス畑

背丈の低いコスモスです

コスモス畑と青い空

ところどころヒマワリが咲いていました

少女とコスモス

堪能しました

乗馬を楽しむ人がいました

地面を覆うイチョウの落ち葉
(鬼女台)

烏ヶ山ははっきり見えるのですが、手前に雲がかかり残念

烏ヶ山のアップ 急峻な山です
(鏡ヶ成・奥大山休暇村)

雲が頭上を覆い始めました

マツムシソウも終わりです
(江府町御机の茅葺小屋)

大山もすっかり雲に隠れて見えません

帰りに突然陽が射してきました
奥津渓の紅葉を楽しんだ後、蒜山高原を訪ねました。ナビの行き先を設定すると、なぜかいったん北上し、鳥取三朝町に向かいました。
目的地のジャージーランドに着くと、残念ながらジャージー牛の放牧はありませんでした。ちょっと残念ですが仕方ありません。
そのかわり、コスモスが斜面にきれいに咲いているではありませんか。これは予想していなかったのでとてもラッキーでした。
コスモス畑の撮影を堪能したあと、鳥取県境の鬼女台に向かいました。駐車場はいっぱいで少し空きを待つ状態でしたが何とか入れることができました。この頃から北方面に雲がかかるようになりました。烏ヶ山(からすがせん)は見渡せますが、点前に雲がかかり被写体としては残念な気象条件です。
本当は、大山南壁の絶景ポイント鍵掛峠まで足を延ばしたかったのですが、あまり期待できそうにありません。
結局、江府町御机(奥大山)の茅葺小屋を撮影したあと、帰途につきました。

残念ながら放牧はもう行われていないようでした。

上蒜山の紅葉

遠くにジャージー牛がいればどこまでも歩く道

ススキと上蒜山

ひるぜんジャージーランド 売店の濃厚なソフトクリームが有名
(コスモス畑)

何とこの季節にコスモス畑

背丈の低いコスモスです

コスモス畑と青い空

ところどころヒマワリが咲いていました

少女とコスモス

堪能しました

乗馬を楽しむ人がいました

地面を覆うイチョウの落ち葉
(鬼女台)

烏ヶ山ははっきり見えるのですが、手前に雲がかかり残念

烏ヶ山のアップ 急峻な山です
(鏡ヶ成・奥大山休暇村)

雲が頭上を覆い始めました

マツムシソウも終わりです
(江府町御机の茅葺小屋)

大山もすっかり雲に隠れて見えません

帰りに突然陽が射してきました