本日は、NYダウが1日で22.6%(当時の水準で508ドル)も暴落した1987年10月19日の(いわゆる)ブラック・マンデーからちょうど30年になる。現在の水準に当てはめると、1日でNYダウは5230ドルほど下げたことになる勘定だ。下げ相場に際し損失を一定限度に抑えるように設計された金融商品の広がりが、内部要因として売りが売りを呼ぶ市場環境につながり思わぬ大暴落を現出させたとされる。
米国の財政と貿易収支の「双子の赤字」が問題視され、ドル暴落論が語られ警戒されていた時代だった。ドル安を避けるために、欧州と米国で金利水準を巡る協調行動がとられていたが、インフレに過敏ともいえる反応を示すドイツ連銀が金利を引き上げたことが、国際的なカネ巡りのバランスを崩し、結局、米国株の大暴落につながっていったと記憶している。
18日は、前日の取引時間中に初めて2万3000ドルを突破したNYダウは、この日も8営業日連続でザラバの過去最高値を更新する大幅高となり、2万3157ドルで終了。終値でも初めて2万3000ドルを突破した。これで今年に入り51回目の過去最高値更新となった。
ちょうど米国では7-9月期の決算発表が続いており、FRBによる利上げで収益環境が改善した金融株の好決算がここに来て株価指数を押し上げたが、米税制改革実現に向けた協議が前進していると伝えられたことも、投資家のリスク選好姿勢を強めさせ(リスク・オン)株高につながっている。バブルを警戒する声をもかき消す勢いの株高は、危機時の逃避先とされている金市場では売り圧力の高まりとなっている。
コンピューター・プログラムというよりさらに進化したAIがコントロールする自動売買が当時と比較にならないほど拡大している現在、足元の超ど級の強気相場は、「もうは、まだなり(“もう”ここまで、これ以上は上がらない、は“まだ”上がる)」という相場格言を地で行く展開とはいえ、これこそが“カネ余りとプログラム自動売買の組み合わせ”で作り出された相場と思っている。判断材料となっている変数が短時間で想定以上に変わったりすると、一転して売りの共振現象を引き起こすのだろう。「麦わら帽子は冬に買え」とばかりに、金市場に逆張り的な買いを入れるAIは存在しないのか。
そのカネ余り環境を徐々に終息させようという政策は、米国ではご存じのように既に始まっている。「潮が引いて初めて誰が裸で泳いでいたかがわかる」と言ったのは、オマハの賢人ことかのウォーレンバフェット翁。
米国の財政と貿易収支の「双子の赤字」が問題視され、ドル暴落論が語られ警戒されていた時代だった。ドル安を避けるために、欧州と米国で金利水準を巡る協調行動がとられていたが、インフレに過敏ともいえる反応を示すドイツ連銀が金利を引き上げたことが、国際的なカネ巡りのバランスを崩し、結局、米国株の大暴落につながっていったと記憶している。
18日は、前日の取引時間中に初めて2万3000ドルを突破したNYダウは、この日も8営業日連続でザラバの過去最高値を更新する大幅高となり、2万3157ドルで終了。終値でも初めて2万3000ドルを突破した。これで今年に入り51回目の過去最高値更新となった。
ちょうど米国では7-9月期の決算発表が続いており、FRBによる利上げで収益環境が改善した金融株の好決算がここに来て株価指数を押し上げたが、米税制改革実現に向けた協議が前進していると伝えられたことも、投資家のリスク選好姿勢を強めさせ(リスク・オン)株高につながっている。バブルを警戒する声をもかき消す勢いの株高は、危機時の逃避先とされている金市場では売り圧力の高まりとなっている。
コンピューター・プログラムというよりさらに進化したAIがコントロールする自動売買が当時と比較にならないほど拡大している現在、足元の超ど級の強気相場は、「もうは、まだなり(“もう”ここまで、これ以上は上がらない、は“まだ”上がる)」という相場格言を地で行く展開とはいえ、これこそが“カネ余りとプログラム自動売買の組み合わせ”で作り出された相場と思っている。判断材料となっている変数が短時間で想定以上に変わったりすると、一転して売りの共振現象を引き起こすのだろう。「麦わら帽子は冬に買え」とばかりに、金市場に逆張り的な買いを入れるAIは存在しないのか。
そのカネ余り環境を徐々に終息させようという政策は、米国ではご存じのように既に始まっている。「潮が引いて初めて誰が裸で泳いでいたかがわかる」と言ったのは、オマハの賢人ことかのウォーレンバフェット翁。



















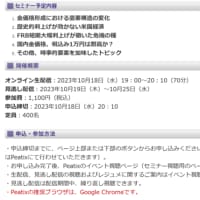






人間は心理や環境に振り回されるます。でもコンピューターは冷暖房完備、暑さ寒さなどない環境で働いています。こんな恵まれた条件化で働いている市場参加者がいると相場つきもちょっと変わるのかもしれませんね。