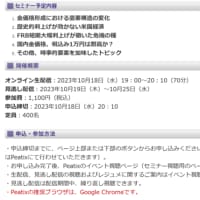確かにFOMC議事録の出口論議の意見対立は意外性があった。件の12月の会合では追加緩和を決め、結果が出るまで緩和の手は緩めず・・・的な声明文の内容だったし、バーナンキ議長の記者会見でもハト派的な方針が並んでいたからだ。もっとも中銀としては有るまじき政策に突っ込んでいるわけで、常に反対意見は存在してきた。今回は政策実行のさじ加減で見通しの食い違いが表面化したわけだが、食い違いすなわち早期撤収を主張したFOMCメンバーの数に驚くことになった。ただし、「崖」問題が表すように、米国景気はサポートがあってはじめて緩やかな成長を続けているわけで、ここにきて住宅部門が底打ちとは言われるものの、サポートなしでは心もとないというのは事実である。こうした状況で手綱を緩めてしまったことが、回復の勢いを削いで更なる悪化を招いたというのが1930年代後半に起きたことで、バーナンキ議長の中では「やってはいけない事」の筆頭だろう。
思えば昨年も、春先に株が買われる中で(当時は)追加緩和後退観測の下で金が売られる局面があった。先月12月のFOMCにて失業率をターゲットに据え、資金供給に伴うFRBの資産膨張の歯止めにインフレ率を使うことも決めた。その時から雇用統計の注目度がさらに上がることになったが、その12月の失業率が先ほど発表されたが、0.1ポイント前月より悪化となった(前月速報値が7.8%に修正され、横ばい。市場予想を0.1%上回る)。まだまだ紆余曲折を経ることになりそうだ。
思えば昨年も、春先に株が買われる中で(当時は)追加緩和後退観測の下で金が売られる局面があった。先月12月のFOMCにて失業率をターゲットに据え、資金供給に伴うFRBの資産膨張の歯止めにインフレ率を使うことも決めた。その時から雇用統計の注目度がさらに上がることになったが、その12月の失業率が先ほど発表されたが、0.1ポイント前月より悪化となった(前月速報値が7.8%に修正され、横ばい。市場予想を0.1%上回る)。まだまだ紆余曲折を経ることになりそうだ。