「信州カラマツを宝に」シリーズは、2月3日の15回目をもって終了しました。
ロシアが高い関税を掛けたことにより、国内の木に脚光が集まり、長い不遇の時代ほ経ていたカラマツも伐られるようになりました。
それでも、搬出費用が高いので、山主に木の代金がたくさん還元されはしません。
木材価格が低迷していた時期、本来なら山全部を伐って、植林をして更新されなければいけない時も、あくまで間伐と称してオロヌキをしていたと思うのです。
本来なら皆伐したら、そこに植林をしなければなりません。
植林した後、下草刈りなど手がかかる、そうなんですお金がかかるのです。
僅かばかりの木の代金では賄えません。
いろんな補助金をもらったとしても、持ち出しになるでしょう。
広葉樹林なら、切り株から芽が出てきて再生されますが、カラマツにはそれがありません。
じゃあ自然に任せればとは簡単に言えません。
禿げ山は災害を起こします。
山を覆っていた土が雨で流されて、岩山になったら、そこに草木は生えません。
そして資源としての木材が必要なのです。
戦後我が国は世界中から木材を輸入して凌いできました。
我が国は木の文化だったから。
札びらを切ってよその国の資源を買える時代は終わりました。
ここのところ、木材価格は高騰しました。ひさしぶりにです。
太陽光発電で、道路脇の山林が軒並みパネルでおおわれてもいたりします。
かっては、木を伐れば植林がセットだったのですが、植林されない山が増えたのです。
赤堀さんも、植林されているのは、全体の3~4割と書いています。
私たちの親の年代は、持山の整備に通いました。
私たちの年代はそれがありません。ここに住んでいない不在地主も多いのです。
愛着もないし、自分の山がどこにあるかも知らないでしょう。
そんな時、売れます、という言葉がかかってきます。
周囲の山一帯を伐りたいからね。
私、伐られた山を見れば、ついつい植林されているかチェックしてしまうのです。
植林されていないことが心配なのです。
赤堀さんは、「伐ったら植える」をされた小海町の方を取り上げていました。
植林後10年間の保育作業は森林組合が請け負うシステムで。
かっては森林組合が全部把握していたのですが、その仕組みが解体されてしまったのですね。
県の林務部が試験的に植栽をしていると赤堀さんが、最終回で書かれていました。
これがとっても興味深かったのです。
試験地で植栽密度を通常の2~4倍で植栽。
いままでは、植林コストを下げるために、少なく植えることが奨励されていたからです。
本数を増やして、カラマツの主要用途の一つの杭材を10年程度で効率よく収穫することを目指す。
前にも書きました。北海道は平らな所に植えて、大根のように収穫していたと。
長野県は戦後の植林は山のてっぺんまで植えました。
そのため伐採コストもばかにならなかったのです。
これからは、従来の発想を止めて、大根のように収穫して、今の需要にそうことが求められていると思います。
でもねえ、この試験地まだ植えられて2年とのこと、先が長いです。
でも、カラマツを植林しない時期が結構あったから、私としてはうれしいです。
退屈な記事でごめんなさい、でもどこかに書き残して置きたいと、ついつい長く書いてしまいます。
カラマツを語り始めると、3日間はしゃべっていられる私です。
お読みいただきありがとうございました。
ブログランキングに参加しています。お帰りにポチッとしていただけるとうれしいです
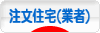 にほんブログ村
にほんブログ村
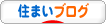 にほんブログ村
にほんブログ村
いつもありがとうございます。















