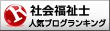重症心身障害児施設に長年従事してきた医師による書。
後半は、重度の障害を抱えたひとたちの支援に奮闘した小林提樹、草野熊吉、糸賀一雄についても紹介している。
特に後半部分は、先駆者たちの働きについて、教科書で「点」として覚えていたことが「線」となってつながり、障害者福祉の発展について再考できた。
引用
・医療処置でも介護でも、「する人」が「される人」に一方的におこなうということではなく、「する人」「される人」が協力しあって、関係しあって成り立っていくものであろう。
・(医療が)「健康管理」の名目で生活を制限し、その結果「健康増進」が妨げられている。


障害の重いひとたちは、「理解する」ということは困難であっても、「感じている」。-本書ではそのようなメッセージが根本にある印象を受けた。
理解しているからウンヌンではなく、人の感情は「快」か「不快」。それをできる限り「快」にしていくことが専門的なケアであると、あらためて考えさせられた。
筆者も説いているが、「生きているのが辛くないのか」と「生」の存在そのものに着眼するのではなく、より快適に「生」を育めるサポートが必要なのである。
後半は、重度の障害を抱えたひとたちの支援に奮闘した小林提樹、草野熊吉、糸賀一雄についても紹介している。
特に後半部分は、先駆者たちの働きについて、教科書で「点」として覚えていたことが「線」となってつながり、障害者福祉の発展について再考できた。
引用

・医療処置でも介護でも、「する人」が「される人」に一方的におこなうということではなく、「する人」「される人」が協力しあって、関係しあって成り立っていくものであろう。
・(医療が)「健康管理」の名目で生活を制限し、その結果「健康増進」が妨げられている。


障害の重いひとたちは、「理解する」ということは困難であっても、「感じている」。-本書ではそのようなメッセージが根本にある印象を受けた。
理解しているからウンヌンではなく、人の感情は「快」か「不快」。それをできる限り「快」にしていくことが専門的なケアであると、あらためて考えさせられた。
筆者も説いているが、「生きているのが辛くないのか」と「生」の存在そのものに着眼するのではなく、より快適に「生」を育めるサポートが必要なのである。
 | 重い障害を生きるということ (岩波新書) |
| クリエーター情報なし | |
| 岩波書店 |