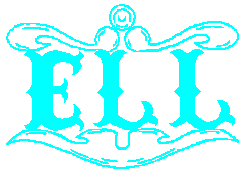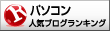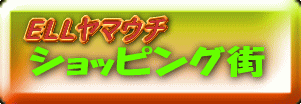日々のパソコン案内板
【Excel関数】 No.1(A~I) No.2(J~S) No.3(T~Y)
【Excelの小技】 【HTMLタグ&小技】
【PDFの簡単セキュリティ】
【複数フォルダーを一括作成するんならExcelが超便利だよ!!】
【アップデートが終わらない!? Windowsの修復ツールを使ってみる方法】
【削除してしまったファイルやデータを復元する方法ー其の一(以前のバージョン)】
【削除ファイルやデータを復元する方法ー其の二(ファイル履歴)】
【Excel振替伝票の借方に入力したら貸方に対比する科目を自動記入】
【手書きで書くように分数表記する方法】
【Web上のリンクさせてある文字列を選択する方法】
【Excel2010以降は条件付き書式設定での文字色にも対応!】
【Windows10のWindows PowerShellでシステムスキャンの手順】
IT関連の目覚ましい進化に完全について行けなくなりつつあります・・・
今や、個人や企業の情報もクラウドなどとネット上に保存する方法も・・・
パソコンの中に保存していても危険なのに、ネット上で大丈夫なのだろうか・・・等々、
このような世界の話になると、とんと頭が回らなくなってしまいます。
何か、ネット社会が風船のようにドンドンと大きくなりつつあるような感じで、
これがいつの日にか、割れてしまいそうな気さえします・・・
一般のユーザーが、どこまでセキュリティーについて考えているのかさえも疑問です・・・
新しい機能が出てきたから、「便利そうやし使うて見よか」
こんな感じのユーザーがほとんどじゃないのでしょうか・・・多分私もそうやと思います。
でも、その心理の隙間を突いてくるのがウイルスを作る攻撃者なのですよね。
今朝は、ネット社会の危険性に関する責任についてのコラムを紹介してみようと思います。
~以下、12月12日読売新聞朝刊より抜粋~
今や、個人や企業の情報もクラウドなどとネット上に保存する方法も・・・
パソコンの中に保存していても危険なのに、ネット上で大丈夫なのだろうか・・・等々、
このような世界の話になると、とんと頭が回らなくなってしまいます。
何か、ネット社会が風船のようにドンドンと大きくなりつつあるような感じで、
これがいつの日にか、割れてしまいそうな気さえします・・・
一般のユーザーが、どこまでセキュリティーについて考えているのかさえも疑問です・・・
新しい機能が出てきたから、「便利そうやし使うて見よか」
こんな感じのユーザーがほとんどじゃないのでしょうか・・・多分私もそうやと思います。
でも、その心理の隙間を突いてくるのがウイルスを作る攻撃者なのですよね。
今朝は、ネット社会の危険性に関する責任についてのコラムを紹介してみようと思います。
~以下、12月12日読売新聞朝刊より抜粋~
子どもの頃、バレーボールがなんとなく苦手だった。隣の子との間に来たボールをつい譲り合い、結局、2人の間にポトン。そして、互いに顔を見合わせる。<今の私のせい? アンタじゃないの?>―――と。
社会人になり、そんな「お見合い」シーンは至る所にあるものだと知った。
最近、企業や役所のサイトで急増中の「見るだけ感染」もそうだ。サイトにこっそり細工して、何も知らずに閲覧した人のパソコンをウイルス感染させる恐ろしい攻撃で、この春以降、4000件も見つかった。
ただ、その多くは、サーバー管理ソフトを更新せず、古いバージョンのまま使う――といった、ちょっとした「穴」を攻撃者に狙われたケースだ。問題は、その穴を埋める一手間を誰が担うか、なのである。ある通販サイトの場合、通販会社、サイト制作会社、サーバー提供業者が各々、「うち以外の誰かが対応する」と考え、結局、改ざん発見から半年後の今もそのままだ。
似たようなことは、メール共有サービス「グーグルグループ」での内部情報公開問題でも感じた。初期設定は「だれでも閲覧できる」だが、グーグルは「利用者が設定を変えるはず」と考え、利用者は「グーグルが安全な設定にしているはず」と思ったのだ。複合機やウェブカメラなど、ネットにつながるIT家電が増える中、同様の問題は今後も起きていくだろう。
セキュリティーの責任は誰にあるのか。便利なサービスでも、使う前にまず考えたい。新しい分野なだけに、誰もボールを追わない「空白地帯」は多そうだ。
社会人になり、そんな「お見合い」シーンは至る所にあるものだと知った。
最近、企業や役所のサイトで急増中の「見るだけ感染」もそうだ。サイトにこっそり細工して、何も知らずに閲覧した人のパソコンをウイルス感染させる恐ろしい攻撃で、この春以降、4000件も見つかった。
ネットの穴 誰のせい?
編集委員
若江 雅子
若江 雅子
ただ、その多くは、サーバー管理ソフトを更新せず、古いバージョンのまま使う――といった、ちょっとした「穴」を攻撃者に狙われたケースだ。問題は、その穴を埋める一手間を誰が担うか、なのである。ある通販サイトの場合、通販会社、サイト制作会社、サーバー提供業者が各々、「うち以外の誰かが対応する」と考え、結局、改ざん発見から半年後の今もそのままだ。
似たようなことは、メール共有サービス「グーグルグループ」での内部情報公開問題でも感じた。初期設定は「だれでも閲覧できる」だが、グーグルは「利用者が設定を変えるはず」と考え、利用者は「グーグルが安全な設定にしているはず」と思ったのだ。複合機やウェブカメラなど、ネットにつながるIT家電が増える中、同様の問題は今後も起きていくだろう。
セキュリティーの責任は誰にあるのか。便利なサービスでも、使う前にまず考えたい。新しい分野なだけに、誰もボールを追わない「空白地帯」は多そうだ。