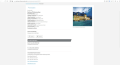久しぶりにカラヤン指揮の録音で感動した。この「悲劇的序曲」は間違いなく名録音である。この程度なものは頻繁にある筈なのだが、しかしその楽譜の読みや細かな作り方が見事だと思う。この録音は1970年で教会での録音だろう。
勿論得意のドラマの作り方も決まっているのだが、それ以上に演奏に緊迫感もある。背景事情はよくは知らないが、こういう演奏をして録音をしていたといういい例である。
実はそのLPの後ろのトラックに入っているハイドンの主題による変奏曲が1976年の録音で翌年の大阪国際フェスティヴァルで聴いている。それでどうしても両曲を続けて針を下ろすことが多かったと思うが、改めてそうして聴いてみるとその数年間でも演奏の様式が大きく変わっている。後者はフィルハーモニーでの録音の様だ。
「悲劇的序曲」の教会録音はオフマイクで音が混濁して仕舞っているのだが、それ以上にそこで演奏している状況があって、フィルハーモニーでの濁りの無い音響での演奏とは異なる。全く演奏が異なる。実際に翌年はそうしたゆったりと快適なブラームスや「英雄の生涯」などが演奏されたのだった。カラヤン演歌の真骨頂である。
それと頭の中で比較しながら、ガルミッシュ・パルテンキルヘンでの演奏を聴いていた。当然ながら座付管弦楽団にフィルハーモニカーの切り上がった弦の音も管楽器の巧さもない。だからその歌いまわしの巧さや標準配置での掛け合いを愉しんでいた。どうしても鄙びた感が生ずる。その意味からは、ペトレンコもまだやることが沢山あった。その分、指揮自体は以前にも益して自由に激しくなってきている。一つは座付管弦楽団を即興的に限界まで持って来る危険を厭わなくなっている事、一つは崩れない一歩手前までも持ってこれるところがまだベルリンでは出来ていない指揮だ ― 「トリスタン」ではそうした際が何度も試される。
あと五回しかミュンヘンで振らないが、今から最後の「トリスタン」の終止迄どんどんと限界を掠めてくると思う。それを実感して、ベルリンで今後どのようになって来るかを予測したいのだ。そのような期待を具体的にするようになったのはマーラーの第七番交響曲のCDを聴いてからで、これが本当の指揮芸術、管弦楽芸術なのである。
昔話に戻れば、1977年の日本はとんでもない年度だった。先ずはベーム指揮ヴィーナーフィルハーモニカーがベートーヴェンの田園、運命を3月に演奏、5月にはコンセルトヘボーが常任指揮者のハイティンクでブラームスの3番、6月になってクレメルが「ショスタコーヴィッチの想い出」を日本初演、その週末にはシカゴ交響楽団がショルティ指揮マーラーの交響曲五番や「海」や幻想交響曲を演奏、そしてカラヤン指揮のブラームスツィクルスなどをベルリナーフィルハーモニカーが演奏。大交響楽団の演奏実践の歴史的頂点がショルティ指揮に輝いた時だった。
参照:
さしかかる転換点 2021-07-13 | 文化一般
ヘルマン・レヴィの墓の前で 2021-07-06 | マスメディア批評
勿論得意のドラマの作り方も決まっているのだが、それ以上に演奏に緊迫感もある。背景事情はよくは知らないが、こういう演奏をして録音をしていたといういい例である。
実はそのLPの後ろのトラックに入っているハイドンの主題による変奏曲が1976年の録音で翌年の大阪国際フェスティヴァルで聴いている。それでどうしても両曲を続けて針を下ろすことが多かったと思うが、改めてそうして聴いてみるとその数年間でも演奏の様式が大きく変わっている。後者はフィルハーモニーでの録音の様だ。
「悲劇的序曲」の教会録音はオフマイクで音が混濁して仕舞っているのだが、それ以上にそこで演奏している状況があって、フィルハーモニーでの濁りの無い音響での演奏とは異なる。全く演奏が異なる。実際に翌年はそうしたゆったりと快適なブラームスや「英雄の生涯」などが演奏されたのだった。カラヤン演歌の真骨頂である。
それと頭の中で比較しながら、ガルミッシュ・パルテンキルヘンでの演奏を聴いていた。当然ながら座付管弦楽団にフィルハーモニカーの切り上がった弦の音も管楽器の巧さもない。だからその歌いまわしの巧さや標準配置での掛け合いを愉しんでいた。どうしても鄙びた感が生ずる。その意味からは、ペトレンコもまだやることが沢山あった。その分、指揮自体は以前にも益して自由に激しくなってきている。一つは座付管弦楽団を即興的に限界まで持って来る危険を厭わなくなっている事、一つは崩れない一歩手前までも持ってこれるところがまだベルリンでは出来ていない指揮だ ― 「トリスタン」ではそうした際が何度も試される。
あと五回しかミュンヘンで振らないが、今から最後の「トリスタン」の終止迄どんどんと限界を掠めてくると思う。それを実感して、ベルリンで今後どのようになって来るかを予測したいのだ。そのような期待を具体的にするようになったのはマーラーの第七番交響曲のCDを聴いてからで、これが本当の指揮芸術、管弦楽芸術なのである。
昔話に戻れば、1977年の日本はとんでもない年度だった。先ずはベーム指揮ヴィーナーフィルハーモニカーがベートーヴェンの田園、運命を3月に演奏、5月にはコンセルトヘボーが常任指揮者のハイティンクでブラームスの3番、6月になってクレメルが「ショスタコーヴィッチの想い出」を日本初演、その週末にはシカゴ交響楽団がショルティ指揮マーラーの交響曲五番や「海」や幻想交響曲を演奏、そしてカラヤン指揮のブラームスツィクルスなどをベルリナーフィルハーモニカーが演奏。大交響楽団の演奏実践の歴史的頂点がショルティ指揮に輝いた時だった。
参照:
さしかかる転換点 2021-07-13 | 文化一般
ヘルマン・レヴィの墓の前で 2021-07-06 | マスメディア批評