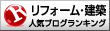家の近くにある神社。
小学校へ通うのに毎日通った神社。
昼でも暗く、不審者が出るので小学校の通学路には
指定されていなかった。
それでも内緒で通っていた。
※画像は先週の土曜日(11/29)とそれ以前に撮っていたものを
使用。

叡山電車の修学院駅を降りて白川通りに出て一本北側の道に
ある道標。

道標のある道を東へ300mぐらい進むと、参道入り口の鳥居が
ある。

鷺森神社は紅葉の隠れ名所。
この参道は春の桜の時期もきれい。


本殿。
御祭神:素盞嗚尊(すさのおのみこと)
由緒(京都府神道青年会のHPより)
鷺森神社は最初比叡山麓、赤山明神の付近に祀られていたが応仁の
乱の兵火で罹災し、今の修学院離宮の山林中に移され、離宮造営に
あたり霊元帝の思召しにより現在の鷺の杜に社地を賜り、元禄2年
(1689)6月御遷座になり修学院、山端の氏神社として今日に至って
いる。


末社。

北側にある鳥居。
ここを抜けて、修学院離宮~赤山禅院がいつもの散歩コース。

手水舎。


狛犬。

縁結びの石。八重垣。
「八雲たつ 出雲八重垣妻籠に 八重垣つくる その八重垣を」
御祭神の素盞嗚尊が詠まれた和歌にちなんで「八重垣」と名付け
られている。

拝殿。

南側入り口には鳥居は無いが、そのかわり御幸橋がある。
この石橋は元修学院離宮の正面入口に架設されていたもの。
鷺森神社の社宝として永遠に残されることになった。

南側の通路は細くて夜は真っ暗になる。
懐中電灯がないと歩けないくらい。
ここを通ると曼殊院道に出られる。

修学院離宮の門から100mほど西へ行ったところにある
お旅所。
・・・・・
この神社は敷地も広大で、憩いの杜のような感じ。
休日には拝殿に腰掛けてゆっくりと時を過ごす人も
多い。
小学校へ通うのに毎日通った神社。
昼でも暗く、不審者が出るので小学校の通学路には
指定されていなかった。
それでも内緒で通っていた。
※画像は先週の土曜日(11/29)とそれ以前に撮っていたものを
使用。

叡山電車の修学院駅を降りて白川通りに出て一本北側の道に
ある道標。

道標のある道を東へ300mぐらい進むと、参道入り口の鳥居が
ある。

鷺森神社は紅葉の隠れ名所。
この参道は春の桜の時期もきれい。


本殿。
御祭神:素盞嗚尊(すさのおのみこと)
由緒(京都府神道青年会のHPより)
鷺森神社は最初比叡山麓、赤山明神の付近に祀られていたが応仁の
乱の兵火で罹災し、今の修学院離宮の山林中に移され、離宮造営に
あたり霊元帝の思召しにより現在の鷺の杜に社地を賜り、元禄2年
(1689)6月御遷座になり修学院、山端の氏神社として今日に至って
いる。


末社。

北側にある鳥居。
ここを抜けて、修学院離宮~赤山禅院がいつもの散歩コース。

手水舎。


狛犬。

縁結びの石。八重垣。
「八雲たつ 出雲八重垣妻籠に 八重垣つくる その八重垣を」
御祭神の素盞嗚尊が詠まれた和歌にちなんで「八重垣」と名付け
られている。

拝殿。

南側入り口には鳥居は無いが、そのかわり御幸橋がある。
この石橋は元修学院離宮の正面入口に架設されていたもの。
鷺森神社の社宝として永遠に残されることになった。

南側の通路は細くて夜は真っ暗になる。
懐中電灯がないと歩けないくらい。
ここを通ると曼殊院道に出られる。

修学院離宮の門から100mほど西へ行ったところにある
お旅所。
・・・・・
この神社は敷地も広大で、憩いの杜のような感じ。
休日には拝殿に腰掛けてゆっくりと時を過ごす人も
多い。