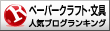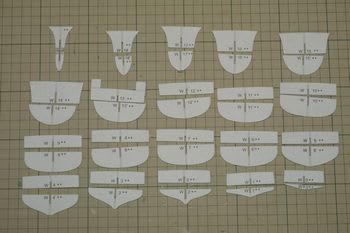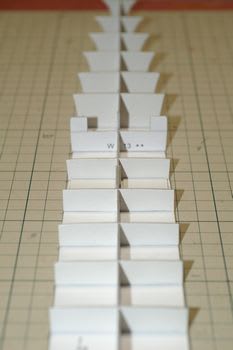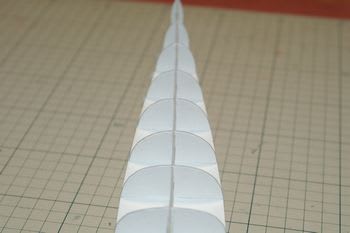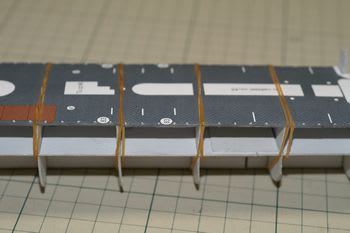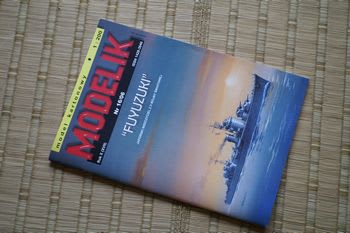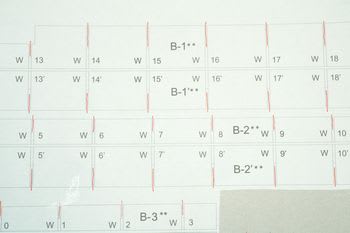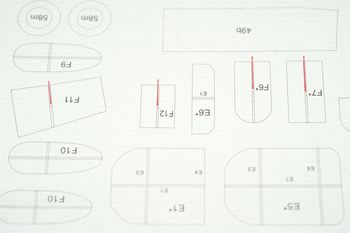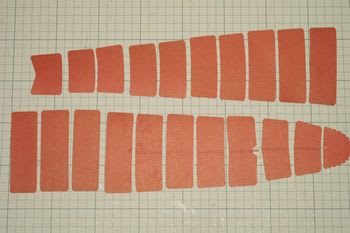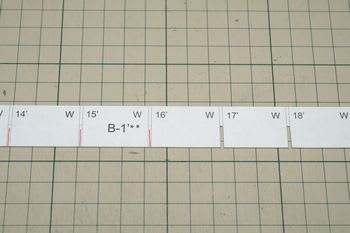明治時代から昭和初期の歴史について、何かものすごく興味がある。
なぜ興味があるかというと、マスコミがあまり取り上げないからである。
原爆、空襲、沖縄決戦とか終戦間近の悲惨な光景を伝えることは、使命で
あるとも考える。
こんなことを言っては失礼だが、色々なところで特集で組まれているので、
かなり見すぎてしまってる。
自分としてはどちらかというと、なぜ日露、日清、第一次、第二次大戦
が始まってしまったのかという点に引き寄せられる。
ということで、天気も良いので、明治天皇陵と乃木神社を訪ねてみた。

カブとスクーピーで、まず乃木神社へ。
京都乃木神社の公式HPには以下のように書かれている。
『乃木神社は乃木希典大人之命(ノギマレスケウシノミコト)を祀る神社です。
京都に乃木神社が創建されたのは、明治天皇の崩御に際しての殉死の一言に
あります。
「うつし世を神去りましし大君の御あと慕いて我は逝くなり」の辞世の句を
残して殉死されたので、京都の桃山御陵の隣に建てられたのです。』

樹齢3千年、幹の直径2m以上といわれる台湾阿里山の檜、1幹で造られ
た神門。
大きな1枚板の門。


日露戦争で活躍した巡洋艦”吾妻”の主錨をモニュメントにした旧海軍将兵
慰霊碑。
吾妻はフランスから購入した最初期の装甲巡洋艦


日露戦争時に旅順柳樹房で第三軍司令部として使われた民家を移築した建物。

建物の中には「成長だるま」が飾られている。

乃木少年が長府(山口県)で父母妹達と慎ましい生活をしていた時代の旧宅。
足軽の家を借りて、家族7人が住んでいた。

拝殿と乃木将軍の愛馬。
拝殿は御霊を護って対峙する方向に建てられている。

乃木神社のお守りは「勝ちま栗」。「負けま栗」でなくて良かった。
小さな祠の中に、御影石でできた栗が鎮座してる。
境内には色とりどりの花もあり、休憩場所もある。時代背景が違うのか
訪れる人も少なく、穴場的な良い場所と思う。

カブとスクーピーを乃木神社に置いといて、明治天皇桃山御陵へ。
京都市内にこんなとこがあったのかーって感じの杉木立の道。

明治天皇陵。
広い。少し東へ行くと昭憲皇太后(明治天皇皇后)の御陵がある。ほとんど
同じ感じ。

ここから宇治方面が眺望できる。人が立ってる向こうは急な階段。

下からみるとこんな感じ。トレーニングで来ている人が多い。


帰りのついでに伏見桃山城へ。
乃木神社、明治天皇桃山御陵と「坂の上の雲」を訪ねてみたが、東郷平八郎、
秋山好古、真之ゆかりの地も行ってみたい。
まずは横須賀の三笠記念公園かな。
なぜ興味があるかというと、マスコミがあまり取り上げないからである。
原爆、空襲、沖縄決戦とか終戦間近の悲惨な光景を伝えることは、使命で
あるとも考える。
こんなことを言っては失礼だが、色々なところで特集で組まれているので、
かなり見すぎてしまってる。
自分としてはどちらかというと、なぜ日露、日清、第一次、第二次大戦
が始まってしまったのかという点に引き寄せられる。
ということで、天気も良いので、明治天皇陵と乃木神社を訪ねてみた。

カブとスクーピーで、まず乃木神社へ。
京都乃木神社の公式HPには以下のように書かれている。
『乃木神社は乃木希典大人之命(ノギマレスケウシノミコト)を祀る神社です。
京都に乃木神社が創建されたのは、明治天皇の崩御に際しての殉死の一言に
あります。
「うつし世を神去りましし大君の御あと慕いて我は逝くなり」の辞世の句を
残して殉死されたので、京都の桃山御陵の隣に建てられたのです。』

樹齢3千年、幹の直径2m以上といわれる台湾阿里山の檜、1幹で造られ
た神門。
大きな1枚板の門。


日露戦争で活躍した巡洋艦”吾妻”の主錨をモニュメントにした旧海軍将兵
慰霊碑。
吾妻はフランスから購入した最初期の装甲巡洋艦


日露戦争時に旅順柳樹房で第三軍司令部として使われた民家を移築した建物。

建物の中には「成長だるま」が飾られている。

乃木少年が長府(山口県)で父母妹達と慎ましい生活をしていた時代の旧宅。
足軽の家を借りて、家族7人が住んでいた。

拝殿と乃木将軍の愛馬。
拝殿は御霊を護って対峙する方向に建てられている。

乃木神社のお守りは「勝ちま栗」。「負けま栗」でなくて良かった。
小さな祠の中に、御影石でできた栗が鎮座してる。
境内には色とりどりの花もあり、休憩場所もある。時代背景が違うのか
訪れる人も少なく、穴場的な良い場所と思う。

カブとスクーピーを乃木神社に置いといて、明治天皇桃山御陵へ。
京都市内にこんなとこがあったのかーって感じの杉木立の道。

明治天皇陵。
広い。少し東へ行くと昭憲皇太后(明治天皇皇后)の御陵がある。ほとんど
同じ感じ。

ここから宇治方面が眺望できる。人が立ってる向こうは急な階段。

下からみるとこんな感じ。トレーニングで来ている人が多い。


帰りのついでに伏見桃山城へ。
乃木神社、明治天皇桃山御陵と「坂の上の雲」を訪ねてみたが、東郷平八郎、
秋山好古、真之ゆかりの地も行ってみたい。
まずは横須賀の三笠記念公園かな。