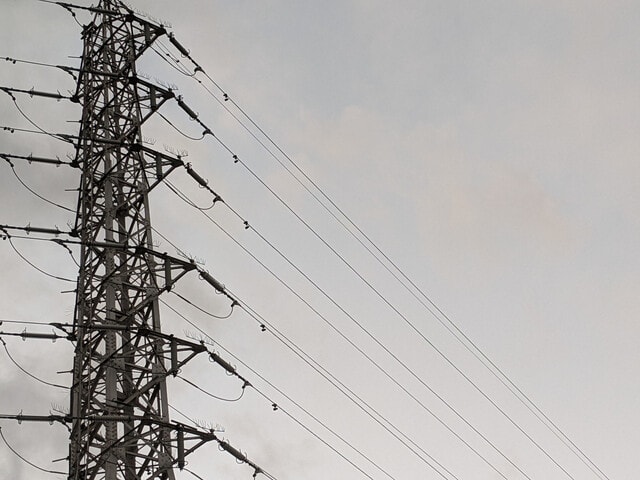で、わたしは本当のところ、こう思うのだ。死のまわりを取り囲んでいる、あの恐ろしい顔つきや道具立てが、死そのものよりも、われわれをこわがらせるのだと。そこでは、生の形式がまったく別のものになってしまっているのだ。母親や妻子たちは泣きさけび、びっくりして、身を固くした人々が弔問におとずれる。青ざめて、泣きはらした顔の召使いたちが、控えている。日のささない部屋には、ローソクがともされて、枕元は、医者や司祭たちに取り囲まれている。 要するに、まわりはすべて、恐怖と戦慄なのである。われわれはもう、屍衣にくるまれて、埋葬されてしまったも同然なのだ。子供というのは、それが友だちであっても、仮面をつけているとこわがるものだけれど、われわれも同じだ。だから、人からも、物からも、仮面を取り去る必要がある。仮面をはいでみれば、その下には、召使いやら女中やらが、少し前に、なんの恐れもなしに通りすぎていったのと、まったく同じ死が見いだされるだけなのだ。人や物がものものしく集うための準備をする暇もない死、これこそが幸福な死ではないか。
で、わたしは本当のところ、こう思うのだ。死のまわりを取り囲んでいる、あの恐ろしい顔つきや道具立てが、死そのものよりも、われわれをこわがらせるのだと。そこでは、生の形式がまったく別のものになってしまっているのだ。母親や妻子たちは泣きさけび、びっくりして、身を固くした人々が弔問におとずれる。青ざめて、泣きはらした顔の召使いたちが、控えている。日のささない部屋には、ローソクがともされて、枕元は、医者や司祭たちに取り囲まれている。 要するに、まわりはすべて、恐怖と戦慄なのである。われわれはもう、屍衣にくるまれて、埋葬されてしまったも同然なのだ。子供というのは、それが友だちであっても、仮面をつけているとこわがるものだけれど、われわれも同じだ。だから、人からも、物からも、仮面を取り去る必要がある。仮面をはいでみれば、その下には、召使いやら女中やらが、少し前に、なんの恐れもなしに通りすぎていったのと、まったく同じ死が見いだされるだけなのだ。人や物がものものしく集うための準備をする暇もない死、これこそが幸福な死ではないか。
――「エセー」第一章第一九章(宮下志朗訳)
「呪怨」は最初の映画の半分ぐらいしか観てないんだが、下の世話が自分で出来ない老人宅にヘルパーが訪ねるところからはじまり、その荒れ果てた家の様子を長々と描いていて、――ホラーの人的本体・白い子どもや黒い女性が出てくる前に恐怖感がすごい。これが「リング」にはない恐ろしさを出していて、観客に、誰の家でもそういう呪われた家に住んでいるかんじを与えていてリアルである。「リング」は死そのものに対する恐怖を描いているのだが、「呪怨」は未来に対する恐怖そのものの予感を描いている。もっとも、モンテーニュのいう、恐ろしさが派手な「仮面」に頼っているのは、これらの映画でも一緒である。そして、この「仮面」は、その形象それ自体がおおげさに変形し暴走することによって「死」を物象化させ、人命の軽視のみならず死への過大な恐れを生み出すのである。モンテーニュは、この長い章で、さまざまに昔から死がホラー化して人間の生を狂わせる様をしめすためにであろう、それに抵抗した良識があったことを細々と例証してゆく。モンテーニュは死のホラーから逃れるためにこれほどの努力をしなければならなかったのであり、どうみても真に死に神にとりつかれていた。
私も思春期に、祖父や祖母が亡くなって、この経験は、これは非常にわたしの進路に影響を与えたと思うのである。死に神にとり憑かれていない文士や学者はわたくしは信用しない。生をコントール出来ると思っているのが死に神にとり憑かれていない者の特徴である。
みんな言ってることだろうが、――不老不死を目指してがんばる話が無惨な結末を迎えることを忘れはてているのはまずいのではないかと思う。今の医学は、治療ではなく、滑稽な不老不死思想と安心安全思想の結合であって、きわめて人文学的な分野になっている。目の前に生死を置いているのだからむしろ文学はそこにあるようなきがしないでもないぐらいであるが、彼らはおそらく、メフィストフェレスに魂を売り渡す前の、ファウストみたいなもので、生をコントロールできると思っている節がある。
コロナでそれを逆にアピールしようとした医学界、ひいては現代社会は、コロナ以上にコントロール不能な戦争や指導者に振り回されている。よのなかうまく出来たものである。
群集は地獄である。〔略〕群集のなかに息づまらない人は、結局常に奴隷である。群集のうちに息づまる人間はやむなくもう一つのもの――孤独の方へ行く。孤独は正に煉獄である。
――佐藤春夫「芸術家の喜び、其他」
思うに、群衆の中の孤独とか言っているうちはまだ平和だったのだ。芥川龍之介が「奉教人の死」でさんざ警告していたというのに、なぜかそのあとの群衆への眼差しは、自分だけはコントロールできているという幻想に向かったような気がする。いまでも、群衆と化した、大学生の学歴への自意識の塊が差別の対象の死を願って生を謳歌しようとしている。
例えば、地方の大学をどうするかみたいな話は定期的に話題になるが、――わたくしの経験から言っても、地方の山の中の小さい大学っていいのである。静かだし、ほんと、勉強も青春もやり直すことができる感じがある。だいたい日本の大学は首都圏のやつは特にでかすぎる。あれでは学生が群衆化しておかしくなるのは当たり前だ。
「チーム**」とかいう科白が平気で吐かれるようになれば、民主主義なんて簡単に死ぬのだ。左翼の組織論に限らず、もっと一般的にも組織のあり方こそが問題だったのに、群衆と化した孤独な人間たちが言う、個人よりもチームでやった方が良いみたいなデマに社会が乗っ取られて、いろいろなものが死んだのだ。
わたくしにとって、山の中での小さい単科大学での学生時代は、音楽と文学に集中できた第二の高校時代という感じであった。マンモス校のそわそわした蒙昧な雰囲気での堕落は、むしろ大学に入る前の予備校と大学院時代に経験したと思う。そういえば、そのまえの高校時代は、荒れがなくなった中学時代というかんじだったようなきがする。幸運にも私は学生時代を引き延ばすことができたが、これはこれで結果的にはよかった気がする。日本の社会は納得できないことが多すぎるので、それを納得するためにものんびり学生時代をながながと過ごしてよかった学生は案外多いのではなかろうか。それを許さない親たちが多いのは、お金の問題もあるが、みずからの苦労からくる嫉妬と怨恨である。
もしかしたらもう研究があるかもしれないが、――わたくしが大学生だった頃、留年して大学七年生、八年生になっているひと、大学の音楽団体にも政治的なセクトにもかなりいたが、こういう人たちが将来どうなったか、そもそも大学時代、どうやって食ってたのか、研究してみる価値はありそうだ。いまもいることはいるが、存在が消されているような雰囲気だけど、むかしは堂々と闊歩してたイメージである。大学が四年間で卒業させろみたいな政策を強制されるようになってから、実質的になにが変わったのか考えてみる必要はある。しかし、これもどうせ、大学生を個人ではなく、学年ごとの群れで考えるような非人間的な発想の帰結に過ぎない。別に個々の人間が変わっているわけではない。彼らが抵抗勢力でも劣っているわけでも優れているわけでもないということである。