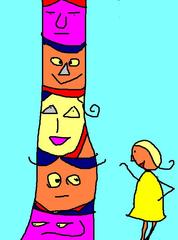ストラヴィンスキーの三大バレエのうち私が一番好きなのは「ペトルーシュカ」であるが、他の二曲もしょっちゅう聴いているような気がする。そもそも私は、世界の中で一番の芸術国家はドイツとかアメリカとかではなく、ましてや日本などではなく、ロシアだと思う。トルストイ、ドストエフスキー、チェーホフ、カンディンスキー、ムソルグスキー、チャイコフスキー、ストラヴィンスキー、ラフマニノフ、プロコフィエフ、ショスタコーヴィチ、リヒテル、ホロヴィッツ、レーニン、スターリン、ラスコーリニコフ……すごい、すごすぎるっ。
ストラヴィンスキーは根本的にロシア五人組の末裔であり、最後の輝きであると思う。チャイコフスキーのような西洋かぶれに人気で押され気味だったロシア国民楽派が、その弟子を巴里に送り込み、ついにヨーロッパの音楽を変えるに至った。つまりこれは、ソ連のベルリン侵攻とおなじようなものなのではなかろうか。……というのは冗談だとしても、ストラヴィンスキーの三大バレエの時期というのは、とにかく攻め込む気合いがすごいと思う(笑)まさにセンス抜群の野蛮人の襲撃である。
ロシアの芸術を楽しむなかで私が想像しようといつも思うのは、はたして彼らが生きていた、左翼用語で言うところの「封建」的なものとはどういうものであろうか、ということである。それは私が思いも及ばないものであろう。
で、気に掛かるのは、我々の住んでいる社会のことである。私も80年代以降の「ポストモダン」とかいうのに騙されていたのか、自分の棲んでいる世界がいかに藤村や啄木が住んでいた世界と変わっていないのかに気付いていなかった。私の周りを観察するにつけても、「家」にまつわる事象が関わると、普段は「21世紀市民」(笑)みたいに振る舞っている人間でも突然様変わりするし、普段は自分は時代遅れじゃけえと隠棲していた連中が突然居丈高になったりするのである。特に結婚に連なるゴタゴタはあまりに酷い。調べたわけではないから全くの私の妄想であるが、最近の若者の結婚を邪魔しているのは、コミュニケーション能力の低下とかではなく、親とか親戚とか、突然出現する仲人面の人間とかではなかろうか。この人たちは、他人の事柄を支配して喜ぶ趣味がある。私もさまざま他人の結婚式やら披露宴に出てきたが、出席者の中に混じっている、「この二人は俺が育てた」面をして偉そうにしゃべっている人間が多くて辟易する。極言すれば、こういう行事は、当事者や当事者の親をさらし者にして、「ほぼ赤の他人」が恩を売った気になる行事である。(葬式では、死んだ本人がいないだけに(笑)もっと酷いつばぜり合いがある。)底意地の悪い書き方をしているようだが、……こんな面倒なことになるくらいならやめとくわ、という人間が出てきても不思議はないと思う。信頼できる人間が集まってくるのはいいが、
普段本人に恩売るほど能力のない「恩を売りたがる人間」というのが集まってくるのはたまらない。日本の「家」というのは、こんな感じの恩の売り合い、足の引っ張り合いで成り立ってきたのではないか。親戚同士の助け合いのためだ、というのは少しは本当かも知れないが、本当にそうであろうか?本当にそうであったら、近代社会で延々繰り返されてきた貧困や困窮は存在していたであろうか?利益のありそうなときには特定の人間に群がり困った時には助けないのが日本の姻戚関係ではないか?どうもそんな気がする。そうであるからこそ、嫌われないように右顧左眄術が横行するし、案外(どころの話ではないが)金のやりとりが主たるコミュニケーションである。贈与ですらない単なる「取引」だ。頼んでもいないのに世話を焼いて(いるそぶりをし)しまいにゃ金を要求する、俺を結婚式に呼んだ呼ばないで陰口をたたく(←そんなお前だから呼ばないんだよ、早く気づけ)……こんなんじゃ、根本的に他人の幸福は考えない社会になって当然である。……ちなみに、差別問題とか家の格式問題みたいな亡霊が突然蘇るのもこういう時である。まったく、どの人間だってもともとはどこの馬の骨だかわからん奴が先祖の癖して、一体何様のつもりなのだ。
私は、こういう問題を回避したところの芸術や思想を認めないつもりで勉強しようと思っている。例えば、少し前内田樹氏がブログで、「人間は競争に勝つために徹底的にエゴイスティックにふるまうことで能力を開花させる」という考えの輩が多いことを難じ、人の役に立つということを労働観としておくべきみたいなことを言っていたが……(http://blog.tatsuru.com/2011/10/20_1207.php)私もそう思う。が、そうは思うものの、「エゴイスティックにふるまう」人達が、「競争に勝つため」にそうなっているかは本当のところはわからないと思う。私の推測では、「人の役に立つ」という顔をしながら「恩を売るだけ」の近しい人間を振り払うための行為である可能性があると思う。私はなぜ日本の若者が内田氏の言うような振る舞いをせずには居られなくなったのか分析が必要であるように思う。あるいは、「エゴイスティックにふるまう」のは、昔からの「恩を売る」人間の特徴でもあったわけだから、そいつらの生まれ変わりである可能性もある。私はその可能性の方が高いと思っているのであるが。生まれ変わった彼らは「恩を売る」のもめんどうになってしまったわけである。