

秋模様。彼はキリギリスではない。
「ブルジョアって、わるいものなの?」
「わるいやつだ、と僕は思う。わびしさも、苦悩も、感謝も、みんな趣味だ。ひとりよがりだ。プライドだけで生きている。」
「ひとの噂だけを気にしていて、」Kは、すらと湯槽から出て、さっさとからだを拭きながら、「そこに自分の肉体が在ると思っているのね。」
「富めるものの天国に入るは、――」そう冗談に言いかけて、ぴしと鞭打たれた。「人なみの仕合せは、むずかしいらしいよ。」
――太宰治「秋風記」
世界の歴史を妙に半端な形で世界中で学ぶようになってから、そこそこほとんどの国が嘘つき野郎であることが判明し、いくら健忘症の国民でもそこそこ悪行をおぼえているようになった。で、なにかやらかすと「おまえオオカミ少年の話をしらんのか」をお互いに言い合ってるうちにオオカミが来て、そのときだけ「赤ずきんをたべたオオカミの気持ちも考えろ」とか言い合うみたいな事態になる。笑いが止まらない――が、じぶんも狼少年だから仕方がない。しまいにゃ酷暑である。

その晩、その木曾福島の宿に泊つて、明けがた目をさまして見ると、おもひがけない吹雪だつた。
「とんだものがふり出しました……」宿の女中が火を運んできながら、気の毒さうにいふのだつた。「このごろ、どうも癖になつてしまつて困ります。」
だが、雪はいつかう苦にならない。で、けさもけさで、そんな雪の中を衝いて、僕たちは宿を立つてきたのである。……
いま、僕たちの乗つた汽車の走つてゐる、この木曾の谷の向うには、すつかり春めいた、明かるい空がひろがつてゐるか、それとも、うつたうしいやうな雨空か、僕はときどきそれが気になりでもするやうに、窓に顔をくつつけるやうにしながら、谷の上方を見あげてみたが、山々にさへぎられた狭い空ぢゆう、どこからともなく飛んできてはさかんに舞ひ狂つてゐる無数の雪のほかにはなんにも見えない。そんな雪の狂舞のなかを、さつきからときをり出しぬけにぱあつと薄日がさして来だしてゐるのである。それだけでは、いかにもたよりなげな日ざしの具合だが、ことによるとこの雪国のそとに出たら、うららかな春の空がそこに待ちかまへてゐさうなあんばいにも見える。……
――堀辰雄「辛夷の花」
堀辰雄の「辛夷の花」は奈良に花を見にいこうとして木曽で雪に降られた作者の随想か何かである。汽車のなかで、春の空がなんちゃらと、妄想している語り手であるが、妻や周りの人間たちには辛夷の花がみえはじめる。しかし、彼にはなかなか見えない。さすがにうまい文章だが、堀辰雄ってなんかオチが形式的というか何というかそういうところある。
僕はもう観念して、しばらくぢつと目をあはせてゐた。とうとうこの目で見られなかつた。雪国の春にまつさきに咲くといふその辛夷の花が、いま、どこぞの山の端にくつきりと立つてゐる姿を、ただ、心のうちに浮べてみてゐた。そのまつしろい花からは、いましがたの雪が解けながら、その花の雫のやうにぽたぽたと落ちてゐるにちがひなかつた。……
観念の目を閉じると、彼には「心のうち」が開ける。そして雪と花の幻想が生じる。藤村ならこうはいかない。知識人の労働者階級へのコンプレックスが、戦後のある時期から急速に失われたことは確かであろうが、もう堀辰雄なんかにもあった現象であるような気がする。堀には、なぜ辛夷の花が妻や乗客にみえるのかわからないのだ。彼等には、少しでも見えたものの姿がありありと見えるに過ぎない。堀は木曽のV字谷のつくる空の果てしなさみたいなものに騙されている。しかし、そのかわりに最後に心の目にはその姿がようやくみえる。山根龍一氏が指摘していたが、坂口安吾にもあったような、遠近法の狂いは、山村と平野との交通によってもたらされた。作家の目の懲らしようというより、その地形の違いが、列車の運行によって連続的に体験されることが重要であろう。

ああ新しき時代は遂に全く破壊の事業を完成し得たのである。さらばやがてはまた幾年の後に及んで、いそがしき世は製造所の煙筒叢立つ都市の一隅に当ってかつては時鳥鳴き蘆の葉ささやき白魚閃き桜花雪と散りたる美しき流のあった事をも忘れ果ててしまう時、せめてはわが小さきこの著作をして、傷ましき時代が産みたる薄倖の詩人がいにしえの名所を弔う最後の中の最後の声たらしめよ。。
――永井荷風「第五版すみだ川之序」
芥川龍之介の「文芸的な、余りに文芸的な」をきわめてまじめに読んでみることが必要だ。そこには、破壊に対するいいようのない悲しみがあった。そのとき、可能だったのは、世界を無理矢理に美としてみることであり、しかも、芸術のほうがその世界をうまく描くことができるという背反を生きることである。もう「私」はない。久しぶりにマーラー聴いた。この人の音楽は、個人の救済が世界を救うみたいな、――セカイ系みたいなかんじで捉えられることもあるとおもうけど、はじめから自分とは関係ないものばっかり歌っているような気がする。きれいすぎるものだから。マーラー自身の意識はともかく、上の背反を生きたのだと思う。
この境地に立つためには、一般には、ほんとの自我の破壊を経験する必要があった。――戦争の悲惨さ、というより体験者と少しは一緒に暮らしてきた者の感想でいうと、ほんと戦前は悲しいことばかりだった、涙も引っ込む悲しいことばかりだったのだ、そのくらいは分かる。その意味で、戦争が、マーラーのように見えてくるというのは、戦後の文化に広く見られることである。
自分の子どもが何人も亡くなる経験をしているひとが多かった時代と今は違ってしまって当然だ。そういえば、マーラーの人生にとって、子どもの死(しかもそれを自分の曲が予言していた)の経験は大きかった。わたしの十代までの人生で一番の経験は自分の病気でもなんでもなく家族の死だったように思うが、これが現代の学生のいくらかにみられるように、親の離婚とかが一番の体験だと大きく人生観が変わると思う。

自誠明謂之性。自明誠謂之敎。誠則明矣。明則誠矣。
――誠なるによりて明かなる。之を性と謂う。明かなるによりて誠なる。之を敎と謂う。誠なれば則ち明かなり。明かなれば則ち誠なり。とまあ、どこから明らかにしたらいいんですかといいたくなるような論理である。自然に誠が自らによって明らかである奴と、努力しなければ明らかになってこない奴がいる。結局、誠であることとそれが明らかであることは両面ではあり、相互によって体現される。どちらかが欠ければ一気に失われる。そういうものだから、もともと体現できる奴もまあいることになるわけだ。一方、誠を示さない努力は努力ではないので、そういうことをいくらやっていてもだめなのである。
たしかに、千本ノックをやたらやりゃいいというものではなく、やってるうちに、この体現のポイントを見出すことが重要である。
ところで、朝ご飯のあと、生まれて初めて「プリキュア」見ちゃったわけだが、かれらはかならず、よいことをできる努力が誠になって「変身」できる連中であって、まさに聖人である。だから、自分の聖人としての仕事以上に相手を爆発させたりはしない。こんな聖人をみて育った人間がどうなったか?→なぜか自己肯定が低い自信なさげな奴が増えている。よくみてみると、敵方が牛おじさんみたいな怪物で、なにが悪いのか説明がないのだ。現実には、聖人もやはり、自分だけでは聖人になれないのではなかろうか。孔子の生きていたコロは、明らかに悪い奴ばっかりだったので、孤独に修養すれば自然に聖人になれたのかも知れないが。

博学之、審問之、慎思之、明弁之、篤行之。有弗学、学之弗能弗措也。有弗問、問之弗知弗措也。有弗思、思之弗得弗措也。有弗弁、弁之弗明弗措也。有弗行、行之弗篤弗措也。人一能之、己百之、人十能之、己千之。果能此道矣、雖愚必明、雖柔必強。
他人が一度で出来たら自分は百度する。他人が一〇回でできたら自分は千回だ。千本のノックのはじまりである。まあわたくしも、出来ないなら何回やってみりゃ何か出来るようになるのではと思うクチである。体でおぼえろというのは、歳とってくるとあんがい真実だと分かるのだ。体が衰えてくると、すべて忘れるからである。われわれは頭で判断しているのではないのだ。
唐沢富太郎だったかの本に、明治時代、旧制高校や大学で学帽が制定されたのは、学生の遊里への侵入を防ぐためだったとか書いてあったが本当なんだろうか。ありうる話だ。優等生たちは、勉強を頭だけでやるのではないのを知っている。つい体も動いてしまうのだ。この調子で遊郭に行き、勢い余って革命でも起こされたらたまらない。明治維新の後だから、まだ、知行合一こそ勉学の最高の能率であることを明治政府のチンピラ共がおぼえていたのである。

その時ふと思いついて、長者ははたと膝を叩きました。また家来達に言いつけて、大きな日の丸の扇をこしらえさせました。畳二枚ほどもある大きな扇で、まん中に大きく金の日の丸を書いたものでした。それで雷の神を招き落とそうというのです。
さて、ある日、空にむくむくと入道雲が出てきて、それがふくれ上がり延び広がり、やがて空一面まっ黒になって、ざあーっと大粒の雨が降り出し、ごろごろと雷が鳴り始めた時、長者は庭の隅のあずまやの中に出ていきました。そして、庭の大木に仕掛けた網の綱を足でふまえ、いざといえばすぐにその綱を引っ張って網を落とすようにして、それから、大きな金の日の丸の扇をあずまやの軒から差し出して、空に向かって両手であおぎながら、雷の神を招き落とそうとしました。
扇には油が引いてありましたから、いくら雨に濡れても平気でした。ざーざーっと降る雨の中にも、金の日の丸はぴかぴか光りました。雨が少し小止みになって、雷が激しくなってきますと、ぴかりとする稲妻の蒼白い光りを受けて、濡れた金の日の丸が、なお一層輝いてきました。
雷の神は空の黒雲の中からふと、金の日の丸を見つけました。
「おや」
そして自分の好きなそのぴかぴかした赤いものにひかされて、そこへ落ちようとしかけましたが、仕掛けがしてあることを思い出しました。
「うっかりあすこへ落ちたら大変だ」
――豊島与志雄「雷神の珠」
映画「ノープ」というのはあまり評判がよくないようだが、円盤が実はクラゲみたいな生き物で、人を食いに来る、しかもなぜか動物を使ったショーをやってるひとたちの上に常駐していて、かれらだけを狙ってる、みたいな意味不明のところが面白い。豊島与志雄の話がこのあとどうだったかは忘れたが、そもそもわれわれの想像力は、目に見える範囲のものであって、いまみたいなやたら「世界観」みたいなカスみたいなものをともなっているのは限らないのだ。神話が民族や国家レベルに対応したものになるのは、なにか別のからくりが働いたときであろう。
その意味で、坂口安吾の「夜長姫と耳男」は、狭い村の話でしかも神話的であり人間的である。

地方局のアナウンサーのしゃべりを聞いていて「AIほんと気持ち悪いな」と言ってたら、「これ人間だよ」と細に訂正されたわたくしですが、みなさんいかがお過ごしでしょうか。
巨人の星でもあしたのジョーでもそうだけど、恵まれなかった者がなんとか恵まれた者に勝つために、体が壊れる必殺技を繰り出してほぼ死ぬということをわすれ、やたら必殺技を繰り出すフィクションが精神のブルジョアジーを作り出している。いまこそ、――左門豊作とか山田太郎は貧乏なのになんで太ってんのかに注目すべきである。栄養が偏って太るのである。しかし彼等は必殺技をつかってやせたりはしなかった。地道に、恵まれた者たちを追い抜いた。
地道な道すらないので有名な「タッチ」は、野球の場面すらほとんどないみたいな感じで伝説になっていた作品である。九〇年代になってからよんだら確かにそうだった気がするが、死んだ弟の魂がいざというときに乗り移る「死者による魂の加速」(夏目房之介)はある種のスポ根そのものかもしれないのである。あれだよな、当時もPLや天理などの宗教学校が強かったみたいなのはタブーに属するのであろうか。この八十年代のいいかげんな霊魂・生命主義みたいなものがたぶん、地道な努力に入れ替わり始めていた。そしていまの「生命安心安全至上主義」に至る訳であるが、まったく別物になってしまっているのも確かである。死者の魂はいわば生きているからである。そのかわり、安心安全の魂ははじめから死んでいる。
民権論者とて悉皆老成人に非ず。あるいは白面の書生もあらん、あるいは血気の少年もあらん。その成行決して安心すべからず。万々一もこの二流抱合の萌を現わすことあらば、文明の却歩は識者をまたずして知るべし。これすなわち禍の大なるものなり。国の文明を進めんとしてかえってこれを妨ぐるは、愛国者の不面目これよりはなはだしきはなかるべし。
論者つねにいわずや、一国の政府は人民の反射なりと。この言、まことに是なり。瓜の蔓に茄子は実のるべからず。政府は人民の蔓に生じたる実なり。英の人民にして英の政府あり、仏の人民にして仏の政府あり。然らばすなわち今の日本人民にして今の政府あるは、瓜の蔓に瓜の実のりたるのみ。怪しむに足らざるなり。
ここに明鏡あらん。美人を写せば美人を反射し、阿多福を写せば阿多福を反射せん。その醜美は鏡によりて生ずるに非ず、実物の持前なり。人民もし反射の阿多福を見てその厭うべきを知らば、自から装うて美人たらんことを勉むべし。無智の人民を集めて盛大なる政府を立つるは、子供に着するに大人の衣服をもってするが如し。手足寛にしてかえって不自由、自から裾を踏みて倒るることあらん。あるいは身幅の適したるものにても、田舎の百姓に手織木綿の綿入れを脱がしめ、これに代るに羽二重の小袖をもってすれば、たちまち風を引て噴嚔することあらん。
――福沢諭吉「学者安心論」
明鏡は、安心してのぞき込んでいればよい鏡ではない。反射は、反抗であり抑圧である。

ボールがゴムまり、バットには手ごろの竹片がそこらの畑の垣根から容易に略奪された。しかし、それでは物足りない連中は、母親をせびった小銭で近所の大工に頼んでいいかげんの棍棒を手にいれた。投網の錘をたたきつぶした鉛球を糸くずでたんねんに巻き固めたものを心とし鞣皮――それがなければネルやモンパ――のひょうたん形の片を二枚縫い合わせて手製のボールを造ることが流行した。横文字のトレードマークのついた本物のボールなどは学校のほかにはどこにも見られなかった。しかしこの手造りのボールがバットの頭にカーンとくる手ごたえは今でも当時の健児らの「若かりし日」の夢の中からかなりリアルに響いてくるものの一つである。ミットなどは到底手に入らなかった。この思い出を書いている老書生の左手の薬指の第一関節が二十度ほど横に曲がってしまったのはその時代の記念である。先日彼がその話をある友人に持ちだしたら僕もそうだといって彼以上にいっそうひどく曲がった薬指を見せて互いに苦笑した。
彼が高等学校にはいって以来今日まで通って来た道筋はしかしスポーツの世界とはあまりにかけ離れていた。そうして四十年近い空白を隔てて再び彼の歴史のページの上にバットやボールの影がさし始めたのはようやく昨今のことである。
昨年のある日の午後、彼は某研究所にある若い友人を尋ねたが、いつもの自室にその人はいなかった。そこらの部屋を捜しあるいたが、尋ねる人もその他の人もどこにも見えなかった。おしまいにある部屋のドアを押しあけてのぞくと、そこにはおおぜいの若い人たちが集まって渦巻く煙草の煙の中でラジオの放送を聞いているところであった。それはなんの放送だか彼にはわからなかった。ただ拡声器からガヤガヤという騒音が流れだしている中に交じって早口にせき込んでしゃべっているアナウンサーの声が聞こえるだけであった。聞いてみるとそれは早慶野球戦の放送だというのであった。
彼はなんだかひどくさびしい心持ちがした。自分の周囲には自分の知らぬ間に自分の知らぬ新しい世界が広大に発展していて、そうして自分にもっとも親しい人たちの多数はみんなその新しい世界に生きている。そうとは知らず彼は古い世界の片すみの一室にただ一人閉じこもっていて、室外の世界も彼と同様に全く昔のままで動いているような気がしていたのである。ところが、すすけた象牙の塔はみじんに砕かれた。自分はただ一人の旧世界の敗残者として新世界のただ中にほうりだされたような気がしたのである。
――寺田寅彦「野球時代」
これは明治二〇年代に選ばれし学生だった人間が、野球時代=大衆時代の到来に疎外感をおぼえる話だが、こういう構造は戦後もある意味反復された。そこらの棒で玉を打っていた子どもがのちに職業野球人になり、大衆社会のなかで大変な思いをするのは、野村や王や長嶋、張本から落合あたりまでが経験したことである。そのあとは、清原にみられるような大衆社会への過剰適合と混乱を経て、イチロー大谷の職業野球人とは異なる「アスリート」みたいなカテゴリーが成立して、大衆社会との距離の置き方をも発明した。
慶応高校が優勝したので、いろんな意見がネット上にもみられたようだ。「エンジョイベースボール」が腹立つとか「丸坊主にして出直せ」みたいな意見の一方で、「丸坊主軍国主義はいいかげん滅びよ」とか「ついに新しい時代来た」みたいなものがでてくる対立である。早稲田ならこうならない(せいぜい「大チャンフィーバー」とか「ハンカチ王子」ぐらいだ)のに慶応だとなぜかこうなるのが不思議であるが、――いや全く不思議ではない。
わたくしもつい、「慶応の歌、若吉っていう若旦那の話だったらいいね」とか「わたしの育ったところは塾も予備校もなかったが、都会に行くと慶應義塾とか大学(就職予備校)とかがあってさすがだ」みたいなことを思ってしまったのである。
しかし、そもそも、今回の慶応だってほかの高校と大差ないのだ。長髪だからといってビートルズよりも短髪だし甚平ではなくユニフォームをちゃんと着ている訳だし、表情だって普通に高校球児の顔つきだ。地方大会だって空気を読めない進学校が勝ち進むことだってあるじゃないか。優勝したら一〇七年ぶりとかいうけど十分野球エリート校なのだ。県大会で一勝もできんところだってたくさんあるのだ。
寺田寅彦の言うように、野球というのは、必然性と不確定性が混じり合う、すごく奇妙なスポーツである。PLが格下に負けたり、と思うと圧倒的に勝ったりと、何が起こるかわからないわりに、ちゃんと実力の世界なのである。寺田寅彦は、「物質確定の世界と生命の不定世界との間にそびえていた万里の鉄壁の一部がいよいよ破れ始める日」を幻視しちゃうけど、たしかに野球は空中に飛んでいる球を蠅たたきのようにたたいて空中にまた飛ばすみたいなとても不確定な世界で、玉も凶器ではないが当たったら死ぬ可能性がある。見ている観客も同じなのだ。だから讃えられるのも、必然性から飛び出した常軌を逸したなにかになりがちなんだろう。「アストロ球団」というのは本質的に野球的かもしれない。V9の巨人とか、いつも勝つだけの落合中日とかが嫌われたのもその理由だ。だからといってそのこと自体が異常な称賛の対象なのである。これは判官贔屓とかいうものではない。
そういう不確定な世界を安定的に人気商売にさせていたのは物語である。マンガを代表とする物語のバリエーションのおかげもあって戦後の庶民の娯楽に君臨してたわけだ。そこには成功譚も道徳譚もあり、階級闘争も性別の戦いもあったがそれをそれなりに昇華してたと思う。が、昨今、それが緩んじゃったら、坊主対長髪、昭和対令和みたいな幻の二項対立に巻き込まれやすくなってしまった。今回の騒動はそれを示している。
昭和12年、全体主義下の大衆社会において書かれた吉野源三郎の「君たちはどう生きるか」では、エリート予備軍の主人公が早慶戦の実況のまねごとやって遊んでいる。寺田寅彦の時代とはちがい、野球は大衆的になりつつもわりと階級に対応したブルジョア風味を帯びていた。それが目立たなくなったのは、長嶋が巨人に入団して以降のことだろうが、叢生した「いろんな意味でのどん底大衆が野球で徒党を組んでのしあがる」虚構が大量に読まれながら空気を塗り替えていった結果である。清原氏あたりまでは「電気屋の息子が天下とった」みたいな語られ方があった。実態はともかく階級闘争じみた戦いは、戦いだから暴力を含んだ荒っぽい物語になるし、それを内面化していたやつらは高校球児でも多いだろう。根性論というのは一部そういうものだったのである。それが、根性論=暴力容認みたいな風に自律していってしまった。
90年年代にはそんな雪崩が起こっていたが、さすが「はだしのゲン」の中沢啓治だけは抵抗の精神を示している。暴力が愛である時代があったことを示している?「広島カープ誕生物語」はなんと1994年なのである。つい最近じゃねえか。「君たちはどう生きるか」でプロレタリアートの代表みたくでてくる浦川君が豆腐屋だったが、ここでは豆腐屋に婿入りしたカープき★がいが主人公である。
職業野球もいつのまにかプロ野球に変化していた。思うに、人生をかけて甲子園優勝→プロ野球で活躍みたいな「日本の庶民の夢」みたいなものが後退し、「君たちはどう生きるか」の全面化してない大衆社会におけるように、高校野球とか大学野球への熱狂と職業野球へのマニアックな趣味が分離してゆくこともありうるかもしれない。そういえば、以前、落合が「自分が最後の職業野球という意識の持ち主」みたいなこと言っていた。だから彼は給料を上げることを目標においていた。しかし、たぶん清原ぐらいになると、完全に夢の自己実現としての野球という意識が濃厚であるように思われる。(これを他人の夢の実現にずらすと「タッチ」になる――)それはお金をかせいで生活のための野球とはちょっと違うものである。だからこそたぶん彼は夢の中のように放蕩してしまったのだ。これは人気も出る生き方だけど、長く持つとは限らないし、大衆たちの期待する像に自分を当てはめつづけることになる。これはしんどい。
興味深いのは、慶応高校には、レギュラーではないが、清原氏の息子がいたということである。父が甲子園でピンポン球のようにホームランを打ちまくっていたときに実況が「甲子園は清原のためにあるのか」と叫んだのは有名だが、――あれが何十年もたって違う陰影をもつというのがあれである。これは必然でもあり偶然でもある。

もう一つの鉢からは、青い色の花が咲きました。しかし、このほうは、珍しく、元気がよくて、幾つも同じような花を開きました。そのうえ、ほんとうになつかしい、いい香りがいたしました。
のぶ子は、青い花に、鼻をつけて、その香気をかいでいましたが、ふいに、飛び上がりました。
「わたし、お姉さんを思い出してよ……。」こう叫んでお母さまのそばへ駆けてゆきました。
「わたし、あの、青い花の香りをかいで、お姉さんを思い出したの、背のすらりとした、頭髪のすこしちぢれた方でなくって?」といいました。
「ああそうだったよ。」と、お母さまは、よくお姉さんを思い出したといわぬばかりに、我が子の顔を見て、にっこりと笑われました。
――小川未明「青い花の香り」
ブルジョアジー的なものはどこにでも転がっている。明日は、甲子園大会で長髪ブルジョア慶応と野球エリート坊主仙台育英との戦いということでマスコミがなにやら攻勢をかけている。まずは、このバイナリに突入する前に、その形成を回避しなくてはならないが、つい全体を一色に染めるか、ばらばらでいいといいながら抜けがけを容認するか、みたいになりがちである。そもそも我々は後ろも先もじっくり眺めることが重要である。――芥川賞が大騒ぎなのは、野球の甲子園が大騒ぎと一緒なところある、もっと後のあれがあるのに。。。と言う気分である。
野球にも幸運を持ったひとすなわち天才はおり、作家でもそうだ。甲子園で優勝する類いである。例えば、牧野富太郎は天才だったが矢田部良吉は秀才で、みたいな記事があったが、それは間違いで、天才は矢田部良吉のほうである。むしろ牧野の方が秀才の異常性が表れている。清原より落合が異常だったのと同じである。
ときどきネット上でも「トロッコ問題」が問題になるのだが、――まず止まりゃいいし、んで「塵労に疲れた彼の前には今でもやはりその時のように、薄暗い藪や坂のある路が、細細と一すじ断続している。」(芥川龍之介「トロッコ」)としか言いようがない。もちろん我々は止まれないからだ。だからといって意識上の停止を否定すると、過去も未来もなくなるのである。
問題は、われわれの人生を超えた長さを社会がどうあつかうかのほうだ。例えば、日本の封建制については勉強したことがないが、跡継ぎ問題が大きい要素なのはわかる。父方の祖父はたぶんめんぱ屋の跡継ぎとして養子に入って結局国鉄職員になった。これが祖父の性格にも影響したし子どもたちや孫の性格にも影響したはずであると思う。そこには日本の資本主義の変容とラディカリズムの意識の関係がほのみえる。わたしの業界に引きつけて言うと、祖父とそれ以降の子どもたちのメンタリティは、近代文学と学生運動的なものの連続と断絶を示しているようだし、その果てにはフールでラディカルな資本の論理への環流する準備まであるわけだ。それは流民的である。対して、跡継ぎを必死につくらなきゃいけない医者とか地主とか会社の場合は、別の心的な論理が働き続ける。そこには、度しがたい権威主義を持つ可能性がある同時に、資本のコントロールから離れているだけ別のゆるやかなヒューマニスティクな知的探求が同居する可能性がある。それは貴族的なものである。母方の方はそんな匂いがするのだが。。。周囲を見渡してみるに、最近は、権威主義的な阿呆が増えたように思うので、もう無理だと思うが、その可能性をまだ戦後までは引きずっていたのだ。戦後の、貴族的ヒューマニズムと流民的ラディカリズムの結合はその可能性のなかで起きた。

夏休みは暑すぎるから休んでいるのだが、なんだろ、我々は休むの能力が下手になっているのにくわえて、そもそも休んだからといって休みにならない気温というものがある。
庭の雑草が暑すぎて枯れてきている。太陽最強
なにゆえわしの庭の蛙はクーラーなしでも大丈夫なのか。100字以内で答えよ
↓
蛙は肺で呼吸せず、皮膚から酸素を吸収することができます。水分を保持しやすく、湿度が高い環境を好むため、庭の湿度が高い場合、クーラーなしでも適応できる可能性があります。(チャットGPT)
スケバンで可
「スケバン刑事」というのは原作しか読んだことがないが、すばらしい作品であった。この前YouTubeで斉藤由貴主演の第Ⅰ話だけみたが、楽しい作品であった。とにかく、スカッとすることが世の中大事である。で、作中で「まさかスケバンのお前が刑事だとはだれも思わないからな」と脚の細い男が言ってたけど、結構、現実のスケバンというのは警察的権力だろうと思われる。

私は彼がすこしでも、みすぼらしさ、いやらしさを見せると、テコでも彼をつきのけ、つきとばす私の理知を知つてゐた。私は酒には酔へない。男の美しさ妖しさの花火には酔へる。その花火には、私の理知は無力であつた。
「オレは奥さんなんか、きらひだ。奥さんぢやない、ノブ子。ノブ子はきらひだ。然し、半分ぐらゐ、すいてやる。酒をおごつてくれるからさ。改めて、お礼申上げておくよ。今日は、総決算だ。さうぢやないか。オレみたいのノンダクレでも、毎日同じことをしてゐるうちには、いゝ加減、あきあきするよ。地獄へ行かう。散歩に、行つてみたくなつたんだ。オイ。ノブ子。からだをかせ」
――坂口安吾「花火」
田島列島というすごく上手な漫画家を発見したぞ(遅い)
大谷くんをドラゴンズに呼ぼう(震え声)
例のホームランバッターの息子はお母さん似だからむしろ「モデル**さんの息子」ではなかろうか。。
このまえ仮面ライダーみたいにバイクに乗ってるときにベルトに風を受けてエネルギーをためつつ出勤したらエネルギーをためすぎておなかいたくなっちゃった。
なんだろ、大学で大学院でも、低い山にしか登る気のない人間の子分にならないことだけは気をつけるべき。
わたくしの経験からいくと、目の覚めるような認識だと思ったものは大概間違っている。考えて見ると、それまで寝てた奴が「覚めた」といっても信用できないのは当然だ。たぶん夢を見ていたんだとおもうし、もしかしたらよく寝て体力が回復しただけかもしれないのである。
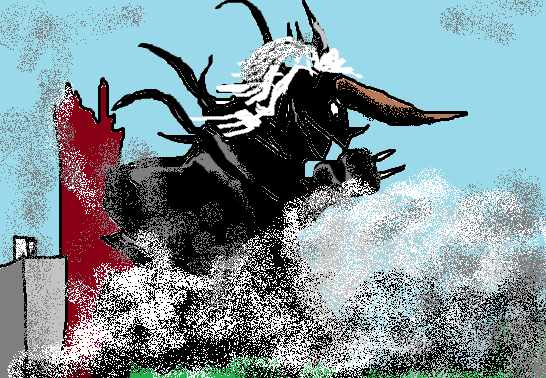
哀公問政。子曰、文武之政、布在方策、其人存、則其政与、其人亡、則其政息。人道敏政、地道敏樹。夫政也者、蒲盧也。故為政在人、取人以身、修身以道、修道以仁。
ここで蒲盧のイメージが少しでも浮かばなければ台無しであろうが、それが生える水辺にはいろんな生物が生きているだろうし、蒲の穂というのが、実際目にしてみるとなにか植物とは無縁ななんだか妙な雰囲気をただよわせる。因幡の白兎を包む挿話なんかはまだその扱いにも優しさがある気がする。わたしなど、なにか不気味なものを感じて火をつけかねない。
その不気味さにはなにか、人間の言葉とは無縁でしかも人工的な感じが混じっている。言葉は、おそろしいもので、機械から発されたものでも親近感がわいてくるということはある。例えば、チャットGPTみたいにすぐ答えてくれる輩はなかなかいない。内容が出鱈目でもすぐ答える奴はわたしの周囲では細しかいない。ひどいやつになると、妙なタイミングはかって難しいですとか、グループワークじゃないとしゃべれないですとかまだ書けてませんみたいな奴らばかりだ。というわけで、ちゃっとGPTに親近感がわいてきた、絶対そういう奴多いだろう。しかし、間違いを指摘すると「誤解が生じているようです」はないわな。結婚するまでになおして欲しい。
我々は勉強しすぎると、こんなプロセスにすら何かの生成を見出し、機械と生物がダブって見えてくる。そして人造人間の夢である。むかしはショッカーに拉致された科学者たちは毎日脅されながら人造人間を納品日までに死ぬ気でつくっていたかわいそうと思っていたが、最近は科研費の書類書いて審査を受け計画通りに嬉嬉として怪人たちを量産していたのだと確信できる。
――話がそれたが、チャットGPTも、中庸で優れた人間に喩えられる蒲の穂も、結局の所、支配の道具である。それが個人ではなく世界全体の幸福を願っているからだ。個人としての人間は、この量産される何者かと常に戦うことを宿命づけられているにちがいない。というわけで、最近の人間と機械の区別がつかない連中に対して、素朴な棒や石みたいなものが武器として見直されてくるかも知れない。
スケバンまで張ったこの麻宮サキが、何の因果か落ちぶれて、今じゃマッポの手先。笑いたければ笑えばいいさ。だがな! てめぇらみてぇに魂までは薄汚れちゃいねぇんだぜ!
むかし、こういうせりふが出てくるドラマがあった。女子がヨーヨーをなげたりして悪をやっつけるものである。銭形平次の現代版であるが、銭形平次が大事なお金をなげるところがおもしろかったのだし、ヨーヨーもぱかっと開いて菊の代紋が見えたりするのである。その意味では水戸黄門である。しかし、このサキの物語は戦後のそれであって、わたくしがとっさに思ってしまったのは、「転向左翼の啖呵かよ」――である。転向していようとしていまいと、左翼は、あくまでもこのような素朴な武器を用いるべきだ。正直なところ、左翼がパソコンをかちゃかちゃやるようになって堕落したとしか思えない。その武器が抵抗のそれではなく、世界を目指すデマゴーグに顛落していたのではなかろうか。
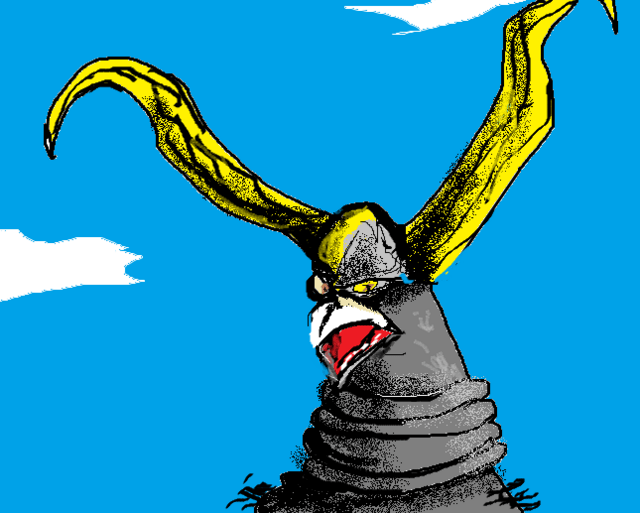
わたしはすごく眠くなる直前にむかって時間をかけて集中力があがっていく人間で、なにもやってないと大体前半はモウダメダみたいな感覚との戦いになるので、絵を描くとか飜訳するとか漢文読むところからはじめて文献名を入力するみたいな作業の果てにやっと本題に入る。しかしこれが不眠とかで体力が落ちてくると、この器械的な助走が失われてやばい感覚のまま本題に入らざるをえない。調子が良くなってくるといきなり本題に入ったり読書に入れる。授業はだいたい助走の部分に当たっている気がする。われわれのような職業の場合、お外での作業は本番ではない。
麻生海氏の『の、ような。』を少し読んだが、あるいみ、家族内で気を遣いあう地獄は、性悪ママ友を主人公が説教したりすることによって少々ましになっているようにみえる。主婦が、お外での活動に勤しむには理由があるのだ。
戦後文学にとってお外は、はじめは戦争であり自分そのものであった。しかし、大江や石原になってくると、子どものときにいろんな体験をしているけれども結構忘れている、あるいは作品によって昇華を行いすぎた。で、やたら暴力を描くようになった側面はある。それは不可避的な流れであって、しかしそれが吉本隆明みたいな思春期=戦中派にはゆるせなかった。吉本隆明のわりと知られた大江・石原批判である「もっと深く絶望せよ」をさっきちょっと再読したが、なんかもっと深い怨念が書かれていると勘違いしていた。そうでもない。これだったら、逆に、あまりに「自殺」「殺人」みたいな話題に赴いている大江・石原の方に、何か書かれていない深さがあるんじゃねえかと思ってしまうくらいである。吉本も、この時期はまだ、外部として、マルクスを分かりやすく使う部分があった。
野茂やイチロー以降は、お外を外部と感じない。いまや自意識の力こぶを入れずに大リーグで活躍する大谷がいる。今日、42号=厄年ホームランを打っていた。彼は顔がかわいい?から欺されているけど、でかい図体・ピッチャーやる・悪球打つ・帽子をぶんなげる、つまり完全に「ドカベン」の岩鬼
なのであるが、岩鬼は山田の外部として描かれていたから、あのキャラクターなのであって、いまは単にオオタニサンでいいのである。
外部と内部があった時代は、「影響」というのに特別なニュアンスがあった。つまり与えられた側からいうとなんかありがたいような気がするものであった。しかし、ほんとは与える側からすると水をこぼしたみたいなかんじなのだ。さっき読んだ有名なコミューン組織の本にはKJ法の本が参考文献にあがってて、まあそりゃそういうこともあると思った。この本には、コミュニズムというのは道徳的に「恥」の文化であると書いてあった。学生運動時代の後期には、敵が味方に、隣が遠くに、みたいな混淆がおこって、わけがわからなくなってしまっていたのだ。しかし、まだこれを葛藤として認識していた時代があった。
遠い記憶だと金田正一氏の『かねやんのズバリ勝つ』かなにかに、本妻以外の女性がいると批判されるのは民主主義になったからだみたいなことが書いてあった。フィンガー5の「くたばれジャイアンツ」というのもあった。なにかおかしい。私自身を振り返ってみても、なにか文化資本的に割り切れない感じがいつもあった。私の家には、マルクスも西田も藤村も確かにあったが、同時に中日スポーツがあった。どうかんがえてみも信濃毎日よりちゃんと読んだのである。「中日スポーツ」の全体的に滑っている駄洒落がよかった。――いまだって、学校では新聞よみなさいと指導してるし、新聞の文章をつかったもっともらしい教育法さえあるが、それが朝日読売毎日あたりの悪文を想定しているのがだめだと思うのだ、と庶民文化を愛でることはもう無理だ。
こういう居心地の悪さを克服しようとしてかしらないが、――野球関係の本というのは、昔だったら王選手の伝記とか、どことなく教養小説じみているところがあったのを、野村とか落合とかのそれにおいて、ビジネス書みたいな側面を拡大させて、ある種の修養的な文化に近づいている。一方で、2000年代までは『おしゃれ野球批評』みたいなおふざけ批評の伝統があり、金田正一氏の遊郭行ったなんだの自慢話の本なんかが特に70年代は結構あったはずで、スポーツ新聞にはかならずエロ小説が載っていた。これはいまでもあるのかしら?
最近知ったのは、まだ各地で精霊馬をつくっていること、あるいはみんなわりと精霊馬がスキということである。これはネットでばれた。わたしは、ポストモダンにこだわりすぎているのかも知れない。










