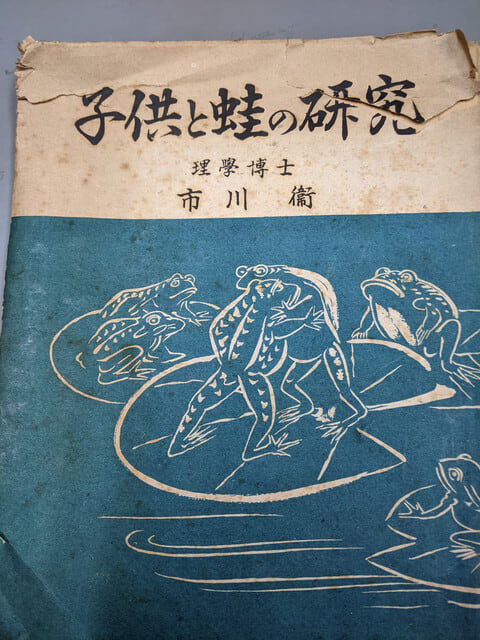『情況』のアジール特集で、東浩紀氏のインタビューが載ってた。この界隈の雑誌のなかに入ると左翼活動家みたいにみえるから不可思議である。もはや、創刊者の廣松渉が忠君愛国の人だったせいか、『情況』もある種の右翼マインドに接近しつつある。というか、何十年もたって、彼らが目指していた革新のイメージが、劇画の草むらの風景みたいなものにあって、その実現を雑誌の中で、文章の文体を含めたイメージを形成していったら、似たようなところにたどり着いたのであろう。団塊の世代はいろいろ言われることもあるが、確かに、文化の刷新を長い時間かけて成し遂げたことは確かである。――写真の撮り方、活字の組み方、ヤクザ映画とかのイメージとか、もろもろのイメージの集合の配置の仕方である。ある種の泥沼で、こんどはそこから変化は起こしにくくなる。七〇年あたりのパッションに溢れた不良たちはその泥沼の中で快楽に苦しんでいる。
ある意味で、「文化」の発するそういう泥沼から個人を残すためには文学賞か全集が必要だったのだ。菊池寛なんか、その辺よくわかっていた。個人全集から離れて初出雑誌にカエレみたいなのは研究の方法論としてはあるが、逆も必要なのだ。
東氏なんかも、そういう「文化」のなかでは、アジール形成の試みの一変種として片付けられてしまうのだ。氏は、だからこそ、以前からまんが的な表象を利用することも辞さなかったのである。もっとも、そんなやり方も、すぐに東氏の手を離れて一般化してしまったが。
アカデミズムの無味乾燥なスタイルは、価値中立という理念と相即的である。個人全集の果たすやり方をアジール的にやろうというのである。慣れちゃったので意味がなくなりつつあるのだが。
おれの家の前を舗装して虫たちを殺したモータリゼーションを憎んでいたところ、大学院に行ったらマルクス主義者を気取ってスポーツカーのっている人が結構いたので何もかもいやになったのが私の出発点であるといへよう。安部公房が安岡章太郎とF1みにいったのを読んでも腹が立たなかったのに、まったくどうしたことであろう。東氏が思想や哲学が娯楽になっている下の世代について語ってたいたが、わたくしは、むしろ上の世代に総括なぞはじめから眼中にない娯楽的なやつらがいて、それに反発した団塊ジュニアが過剰に真面目になってしまった面はあると思う。東氏もその面をもっているのである。
娯楽的と言えば、――昨日、夕ご飯食べながら「ぽつんと一軒家」見てたんだが、訪ねていくテレビの人間が、絶対に言ってはいけない言葉を何回か言っていた。それは、NGワードじゃない。旦那が足をつぶした思い出話があって、「そのときどんな気持ちだったのか」と奥さんの方に聞いてたのだ。これはありえない。こんなのが平気で流れているようでは、首相が「闘いの最前線にたち」とか平気で言うし、大学生や我々が頭が悪くなるのも当然だ。こういうありえん発言が目立ち始めたのはいつからかはわからんが、東日本大震災の頃目立ち始めたなと記憶している。近代文学をある意味でおわらしたのが第二次大戦であるように、言葉を失うというのは文字通りの意味であり得る。絶句した人間は、そも表象不可能なものに対して、自らも表象不可能、いや、単に空白に後退してしまうのである。安吾の「堕落」とか、その意味で自分のレベルで考えすぎなんだ。堕落して言葉を発見するなんてふうにならないんだ、大概は。三島由紀夫も言ってたし、誰かも言っていたと思うが、唯一の被爆国である我々は罪悪感から解放されているという事情があり、三島なんか「だから寧ろ核爆弾を我々は作れる」と言っていたわけだ。しかし、罪障感が存在している人間に対する逆説として、その理屈はわかっても、屈辱も罪悪も、原爆と敗戦の解放は解き放ったのである。それが普通の感覚なのである。
ヴァレリー曰く、「凶暴な人たち。文学の分野で暴力を振るう人は、全て喜劇的なジャンルに近づいてゆく。悪口を言うのは、叙情表現のなかで一番安易で最も伝統的なものだ。」
まさに、インテリの言葉である。