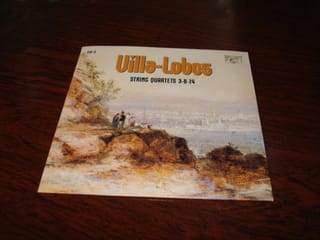須賀原洋行氏の作品はあまりよんでないけど、『非存在病理学入門』をやっと第4巻まで読み終えた。二年かかった。それは『ジョジョの奇妙な冒険』の最新刊まで読み終わるまでに二年かかったのとは違う。ジョジョの場合は単に手に入れるのに二年かかったのに過ぎない。『非存在病理学入門』の場合は、ギャグマンガなのに体調が悪いと読めなかったというのもあるし、面白いと思うのと書かれている内容が現実を想起させなんとなく憂鬱になるのが殆ど同時だった、という──つまり読みがたかったという理由だからである。
これはまさにある種の哲学書の読後感である。
ユーモアを身につけるためには形而上学を学ぶ必要があるのでなかろうか。
よくあることだと思うが、ユーモアを失うとき人は因果関係を追求している場合が多いのではないだろうか。人間が持つ勘違いや幻想を科学によって否定しようと躍起になっているタイプには、ときどきユーモアの欠如が甚だしい人がいる。彼らがユーモアを用いようとすると皮肉や自慢になってしまうのである。これは小学校高学年的な現象だと思う。
思春期はこんな状態を破壊するものではなかったのか。良くも悪くも形而上学というのは、「Ta meta ta physika」(自然学のあと)にくる。自然学を〈trans 超えて〉ではなく、〈meta あとに〉、という感覚、これが私は重要だと思うのである。大人になるというのは、思春期以前を忘却したり超克することではなく、自分がその〈あと〉であることを自覚することであろう。アリストテレスがどう考えていたのかは知らない。
以前、柄谷行人の「唯物論的ユーモア」という概念に飛びついた人達が異様にまじめくさっていたのは、上のような基礎的事情を忘却して、論敵に対するルサンチマンの解消にそれを使おうとしたからであろう。
『非存在病理学入門』のユーモアは確かに我々宮仕えたちの肺腑をえぐるところがあるであろうが、作者は「Ta meta ta physika」の気分かもしれない。そうでなければこれほど面白くは書けなかったはず、であろう。とはいえ、私はこの作者の気がふれたという噂を聞かないが──、そんな風に思ってしまうあたり、私もまだまだユーモアに欠けている節がある。
註)左の画像は、昭和一六年に日本評論社から出た三木清編の『新版現代哲学辞典』の「形而上学」の項目。この辞典は、どちらかというと『現代用語の基礎知識』のような体裁であり、独裁者の項目に若い面長の「スターリン」と「ヒットレル」の写真が載っている。