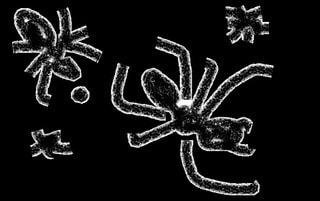何事も入りたたぬさましたるぞよき。よき人は、知りたる事とて、さのみ知り顔にやは言ふ。片田舎よりさし出でたる人こそ、万の道に心得たるよしのさしいらへはすれ。されば、世にははづかしきかたもあれど、自らもいみじと思へる気色、かたくななり。よくわきまへたる道には、必ず口重く、問はぬ限りは言はぬこそいみじけれ。
そうするとみんな黙らなくてはならなくなるのだが――、しかるに、兼好法師の思うほど人々は思いあがっておらず、結構上のような理由で賢くも黙っていると思うのだ。しかしそうなってくると、現実におこるのは、知っていることすらも減ってゆき、実際のところ、知ったかぶりではなくほんとうに知らないから喋ることが不可能になるのであった。我が国では、ほんとうはこっちの方が問題なのである。知ったかぶりの人間をそのまま放置しているコミュニケーション空間の方に責任がある。知ったかぶりにもいろいろあり、大概いやがられるのは、知ったかぶりの側面じゃなくてもともとの性格の方である。そしてかかる際に「人それぞれ」などと個をモノのように突然あつかいはじめるのがいけない。ほんとうはそれは個じゃなく我々に共通する劣等性の現れかも知れないのである。文芸は、そういう共通性をドラマのなかで暴いている。そこには社会的距離などは存在していない。
歳をとってくると、優秀な文学者達が、孤独なすずめに心打たれたり、小さい子達の親切に感動したりするようになったりするのだが、これはやはり老いなのである。自分が他の人間達と大して違わないことが分からず、ただ自分がモノと感じられているからであろう。コロナ禍で案外、年を重ねた人々が、路上で騒ぐ若者にやたら感心したりすることはありうることだ。昔の自分を想起するかも知れないが、そうではなく、あれは現在の自分の姿に過ぎないのである。
わたくしは、若者と老人がお互いに自分を投影しなくなったときが本格的に社会の融解であると思う。高齢化社会でもともとその気はあったわけであるが、コロナでそれこそ世代間の社会的距離が広まった。
さっき『パンデミック日記』(新潮社)という本を眺めていたのであるが、それは、文学者や文化人達のリレー日記である。しかし、これは実際リレーされたわけではなく、ただ編集されただけである。筒井康隆ではじまり蓮實重彦でおわるその日記は、巧妙に、衝突しない個をうまく離して配置してある。後半の、柄谷行人→宇佐見りん→平野啓一郎→坂本龍一のながれなんか、なんとなく編集者の優しい遊びが、みえるだけに、毒にも薬にもならないのだ。せめて、編集者は千葉雅也→柄谷行人→蓮實重彦のような組み合わせを仕掛けなければならないのではないかっ。そういうものこそ、社会的距離が消失する文壇というやつではないだろうか。
文人達は、コロナ禍であいかわらず孤独に仕事をしていた。それゆえか、そこにはほとんど生活の匂いというものがない。
はたして、日記というものは、そういうものでよいのであろうか。