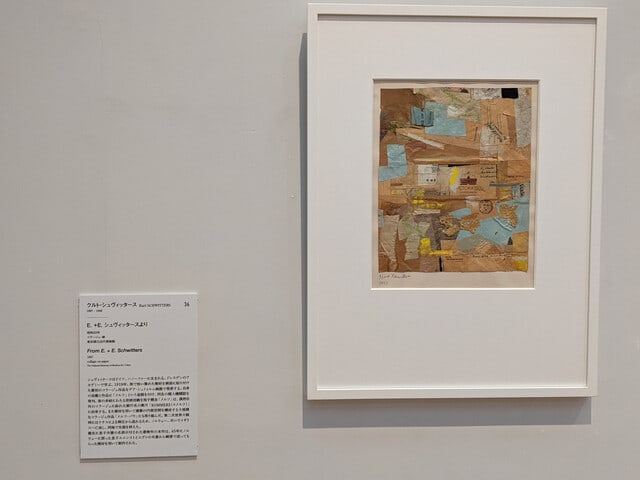「そういうこともありましょう。しかし、わたしに言わせると、九太夫さんたちはどこまでも江戸を主にしていますし、半蔵さまはまた、京都を主にしています。九太夫さんたちと半蔵さまとは、てんで頭が違います。諸大名は京都の方へ朝参するのが本筋だ、そういうことは旧い宿場のものは考えないんです。」
「だんだんお前の話を聞いて見ると、おれも思い当たることがある。つまり、おれの家じゃ問屋を商売とは考えていない。親代々の家柄で、町方のものも在の百姓もみんな自分の子のように思ってる。半蔵だって、本陣問屋を名誉職としか思っていまい。おれの家の歴史を考えて見てくれると、それがわかる。こういう山の上に発達した宿場というものは、百姓の気分と町人の気分とが混り合っていて、なかなかどうして治めにくいところがあるよ。」
「だいぶお話に身が入るようですね。」
と言いながら、おまんは軽く笑って、次ぎの間から茶道具を運んで来た。隠居所で沸かした湯加減のよい茶を夫にも清助にもすすめ、自分でも飲んで、話の仲間に加わった。
――「夜明け前」
「山の上に発達した宿場というものは、百姓の気分と町人の気分とが混り合っていて、なかなかどうして治めにくいところがある」というのはこれは木曽みたいなところに限らない。日本人に多くみられることじゃないかなと思う。で、木曽の特徴はむしろ木こりや職人が多かったところにあるんじゃないかと思う。荒っぽい内気さみたいな気質である。
能力はないから妄想でいうと――、わたくしが『夜明け前』みたいなのを半蔵の息子の代、すなわち曾祖父の代から書き始めたら、職人達の解体の陰惨なはなしにはじまり、戦時中の国鉄職員の悲劇を経て、発狂も許されない戦後の教師の、しのびがたきをしのぶカタルシス0の話になるであろう。――何がいいたいかというと、「夜明け前」は、対象となる幕末と木曽の位置、戦争がはじまったころの執筆時期、藤村の境涯が非常にぴったりくるような惑星直列なのである。簡単には真似は出来ない。
一億総評論家みたいなものはネットが原因ではない。もっとまえからそうだった。自意識上、評論家ですむ階級が多くなったということであろう。しかし、ここに新しい言葉を付与しようとする人間は評論家ではいられない。藤村は階級的変動の中にいながら、新しき言葉がないと新しい人生があったとはいえないと思っていた。結局、藤村の方が時代の言葉(「夜明け前」)をつくってしまった。ほんとは明治以降の体たらくをみて、「夜明け後」と言った方が良かったのであろうが、明けてないものは明けてないんだからしょうがなかった。
ニーチェなどの飜訳の手塚富雄は、三島由紀夫との対談で、日本では「西洋近代語を通じての教養」がニーチェにとっての古典文献学の代わりになって、「近代を古典と思った」と言っている。國文を出たわたくしはそうは実感されないが、三島も日本にはニーチェにとっての古典文献学は日本にはなかったと言っている。「近代を古典だ」と思っているのはやはりおかしい。近代はただの観念で、西洋語や漢文、日本古典(文献)学が古典である。これをきちんとしないから「夜」ができてしまったのである。
「スパイゾルゲ」観に行ったときには、まわりが爺婆ばかりでほんと安心できたが「スパイの妻」の場合は、出演している俳優のファンがまじっていたらしく内容もそうだが観客のそわそわぶりがまさにですね軍靴の足音的であったことはここではっきりと申し上げておきたいが、――結局、戦時下のトラウマこそが「夜」となってしまい、また「夜明け前」のまちがった認識ができあがっている。主人公の「妻」は、死屍累々たる神戸を、夫にも頼らず歩き出したように見えるが、ほんとはそうであるとは限らない。明けそうになりながら明けない海岸を走りながら「妻」はただ泣いていた。