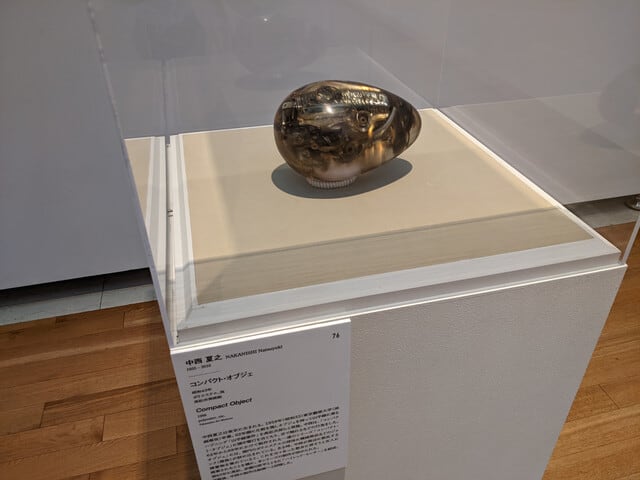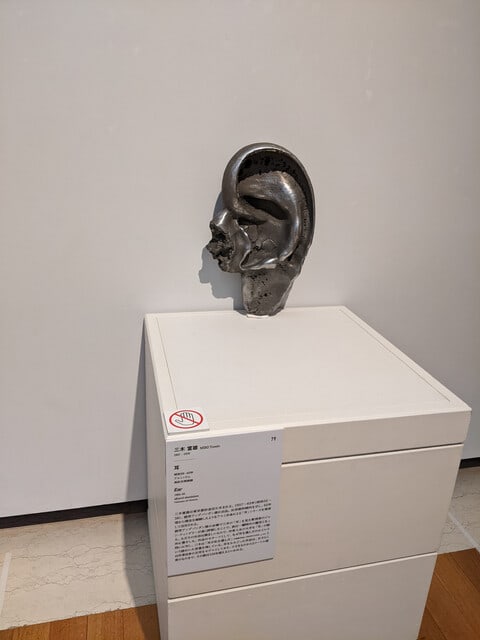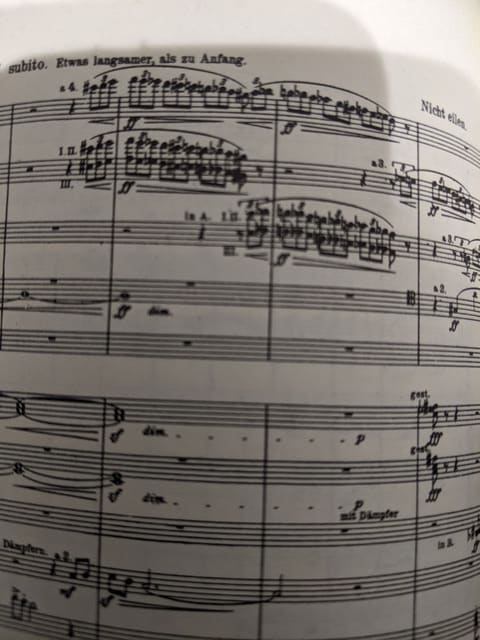国語教育者の口から聞けさうな事で、一度も聞いた事のないのは、「造語能力」に関した問題です。我々の責任の属してゐる明治以後の社会が果してどれほど自由な造語、発想法を発明しましたか。私どもの祖先のどの時代に対しても、実際恥がましく思はれるのは、此点です[…]
「べうほ(苗圃)をうくわい(迂回)して行きや、ぢつきせいはん(製板小屋)が見えるがのし」
此は、五十恰好の木樵りが大台ヶ原の山中で、道を教へてくれた時の語です。国語教育家は前代の人々に対して、どう申しわけがあると思ふのでせう。私は、国語調査会の事業が、なぜ此方面に伸びて行かないのかを訝しみます。漢字制限の申し合せは、確かによい結果を生みませう。併し、責任者自身すぐに実行にうつらないのはどうした事なのです。
――折口信夫「新しい国語教育の方角」
確かに造語能力を失った教師たちはどこに向かっていいのか分からない状態であったろう。目標を失えばわれわれは大概何かに縋るが、それが入試であった。それを通過儀礼とみなし、その先に自由をおいた。しかしいまや、――昔、大学は選抜された者達が自由を享受するところだったが、今は違ってて育てるところだみたいな意見が結構ある。もっとも、それは、昔に対する認識も今の当為もどっちもすごくおおざっぱで不真面目だ。大学でも、あせって目標をさだめて何かしようとする動きが結構あるが、大きいことを言うときに雑でもいいことにはならない。学問ではきっちり手続きを守ろうとするのに、それ以外でものすごく素人以下になるのをどうにかしたほうがよい。これは、理念をマンガのスローガンのように捉えているからであろう。冗談じゃない。純文学が衰えると、現実からなんとなく必要な理念が析出されてくることが分からなくなってしまうのである。
そういう理念への不信感が逆にスキルへの盲信をも生んでいる。模擬授業をたくさんやれば教師になれるとかかんがえるような頭脳の人間に教師なんかできるわけねえが、案外、それのほうが確実に見えるわけである。
スキルというのは、たいてい現実からの析出ではなく、部分への断念である。そのうらがえしで「共感」の絶対化が起こる。で、分かる部分だけに共感するみたいな現象がここ一年ぐらいで学生にもそうでない人にも増えた。で、当たり前だが、その分かる部分というのも断念であることすら忘れられた、誤読である。
一年前か、どこかの広報誌かなんかに載ってた記事で、どこかの家業のおじさんが「おれの考えてることをオードリー・タンも考えていた」とオードリータンの本を読んだ感想として書いてたのがあってすごく面白かった。こういうのは柄谷行人ぐらいしか言わないと思ってたが、これも、その実、現実からの析出の断念であり、部分の一致を自分の側からしか認識していないとこうなる。柄谷は、初期に一生懸命断念をしないように周りから監視されていたからよかったのだ。
漫画家たちは、そんな現実からの析出を諦められない。いっそのこと写しちゃえと言うことで、写真を下敷きに書いているのが例えば、浅野いにおである。彼の『零落』をよんで、こういう析出系である匂いを消して映画にしたい人はいるよなと思ったら、やっぱり映画になってた。主役がウルトラマンのひとであった。