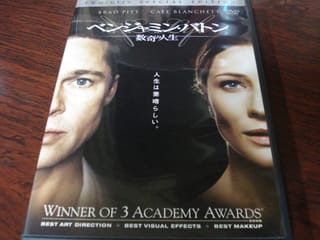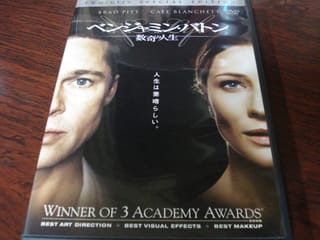
原作は読んでないので映画をみた感想であるが、私が興味深かったのは、老人として生まれだんだん若返ってゆくベンジャミンが、容姿が老人に近い思春期と容姿が思春期の思春期という、二つの思春期を送っていることであった。このあいだに挟まれた心身共に充実した時代に、ちょうど生涯の思い人と年齢的にも幸福な時期が重なりそれが黄金時代である(丁度ビートルズやアポロの頃)が故に、映画をみた(特に中高年の)方々は、結局この逆行の人生も大して現実の我々のものとかわらんなあ、あああの頃はよかったよ、と想ってしまうのであろう。若くても老いていてもそこには何かが欠けている、人生を山のようなものと考えるならばそうなるであろう。
考えてみると、老いた体が精神的成長とともに若返りつづけるなんぞ、不幸でも何でもなく理想の人生である。(普通は、体が丈夫な頃は精神が未熟で、やっとものの道理が見え始めたら体が動かなくなってしまう。最悪である。)とはいえ、この映画が訴えていることは、そういう軌道に乗った段階を挟み込む、人事不省の赤ん坊時代と死の直前にどのような状態があり得るかと云うことで……、その点、主人公はきわめて恵まれていた。はじめは捨てられていたが養老員の人に拾われ大事に育てられ(介護され)る、最後も認知症の子どもとして児童福祉局の人に拾われて愛する人の中で赤ん坊として死に至る。だから、結局、こりゃ社会的セフティーネットの自慢ばなしかよ、という感じもしなくはないのであって……というのは冗談だが、私は、最初の救済はともかく、最後は、主人公をのたれ死にさせるべきではなかったかと思った。
それはともかく、私が思ったのは、二つの思春期があるというのは、我々普通の人間もそうなのではないかということである。むしろ迷うのは二回目の方である。ベンジャミンは妻と子どもから離れバイクに乗って世界を旅していたらしい。この場面、突然ブラピのイメージビデオになっていて、「セブンイヤーズ・イン・チベット」を思い出させた。この映画、彼が遺した日記を彼を看取った最愛の人が臨終にあたってそれを娘(彼との間に出来た子どもである)に朗読させながら思い出す体裁になっているので、どっちかというと彼女の視点で描かれていると言っても良いのであるが、手紙に書かれていないところの
ブラピベンジャミンの世界遍歴もまたこれは大変なものであったはずである。成就する見込みのない人生を生きながら、世界の雑多さとでたらめさを吸収し続ける毎日である。自分探しどころじゃない。……しかし、この点も我々の日常と変わらない。