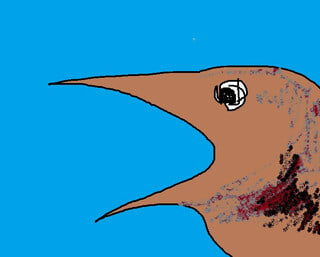次に弟、將に舞わんとする時に詠爲て曰く、
次に弟、將に舞わんとする時に詠爲て曰く、
物部の 我が夫子が 取り佩ける 大刀の手上に 丹畫き著け 其の緒は 赤幡を載せ 赤幡を立てて見れば 五十隱る 山の三尾の 竹を訶岐苅り
末押し縻ぶる魚簀 八絃の琴を調ぶる如く 天の下 治し賜える 伊邪本和氣 天皇の 御子市邊の 押齒王の 奴末
爾くして即ち小楯の連、聞き驚きて、床より墮ち轉びて、其の室の人等を追い出し、其の二柱の王子を左右の膝の上に坐せ泣き悲しびて、人民を集えて假宮を作り、其の假宮に坐せ置きて、驛使貢上りき。ここに其の姨、飯豊の王、聞き歡びて、宮に上らしめき。
履中天皇の皇子は、雄略天皇に殺された。その皇子の遺児である兄弟が地方で発見される話。いつの間にか、親と兄弟の殺し合いのアンソロジーと化している古事記である。だいたい赤の他人というものに対する愛憎はたかが知れているのであるが、家族のなかはそうはいかない。近代になっても、あいかわらず親族殺人で溢れかえっている我が国である。
たぶん、仏教か何かが知らんが何かが媒質となって、日本の各々の神話を統一的に絶対矛盾的に結びつけた古事記は、すべてを曼荼羅のように描こうとしているのかも知れないが、個人と個人の関係は、神話のように並べてくっつけましたみたいな風に行かないところがある。千手観音の手はたくさんあるが、我々にはそんなにないし、あれば手同士が喧嘩をしてしまう。
うちの実家のお墓は、先祖が八沢川だか木曾川だかから引っ張り上げてきたもので、墓石屋がつくったキャラメルみたいな形の中で、燦然と「ばかうけ」のような形で佇立している。墓というのは、魂入れという儀式によって墓になるのだが、墓はもともと記憶がある如くそこにある。なぜかというと、われわれより長く生きているからいろいろなものを見てきているからである。我が家も、祖父が養子だからどこから来たのか分からん人間であるけれども、石がなにやら知っている気がするという訳でそこにある。古墳やなにやらも、遠い祖先が労働にかり出され、公共事業だかの名目でヒドイ労働を押しつけられていたのだろうが、――おれがあれをつくった、という自慢話をかかる奴隷がすることはあるのであって、つまりつくることを意味として媒介にしたモニュメントはそれなりの意味をもって時間を超越するものである。
しかしながら、個人は――作品やモニュメントとは違う。古事記で描かれた一族達の殺し合いは、モニュメントだが、彼ら自体は人殺しや切られた肉片だ。しかし、古事記がそうであるように、我々はそれをモニュメントや歌でしかその悲惨さと悲しみを記すことができない。上の孤児達は、いずれも天皇になって中心に復帰してしまう。その中心とは曼荼羅の中心のようなモノだ。
思うに、天皇は近代に巻き込まれてしまったから、三島由紀夫の言うような、色好みの天皇はもとより、兄弟殺しの天皇までも、復活することはないだろうが――最近、古事記以前に帰ろうとするその萌芽はある。
中曽根康弘などの墓に大金をかける話が持ち上がっているのだが、これなんか、本当は公共事業でやればよいのだ。さすれば、それをぶちこわす勢力、自慢する勢力と、入り乱れて――我が国は古代に逆戻りだ。
「このたびは、御苦労さまでした。どうかカンベンして下さい」
と口々にあやまった。リンゴ園でそれを見た中平はいそいで家の中へ逃げこんで、壁の二連発銃をはずし、それを膝にのせてガタガタふるえて坐っていた。
久作はわが家へつくとノコギリを持って外へでた。人々は呆気にとられて見送った。彼はまっすぐリンゴ園へ登った。そして夕方までリンゴ園のリンゴの木を一本のこらず伐り倒したのである。中平は鉄砲を持って縁側まで歩いてはまた戻ってきてガタガタ坐っていたが、どうすることもできなかった。
その翌日から久作はミササギで仕事にかかったが、十日あまりで石を全部谷へ投げこみ、地ならしして、ミササギが畑になっていたのである。そこへ彼はカブをまいた。しかし、カブをまき終った晩、鎌で腹をさいて死んだのである。山へ戻ってからその日まで誰とも一言も話をしなかった。
――坂口安吾「保久呂天皇」
あくまで個人に憑かれていた坂口安吾は、天皇をこういう感じで描いた。この男は洞窟で天皇になったのだ。現実の天皇は洞窟にはおらず、古事記の中にいる。坂口のえがくものは、遙か未来か、遙か過去にしか存在していないに違いない。