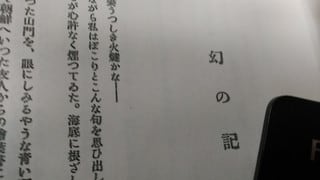御局は桐壺なり。
源氏物語はのっけから帝と女の関係を、玄宗皇帝と楊貴妃に比べていたわけで(やり過ぎだと思うけれども……)あるが、ここに来て、長恨歌の一節
芙蓉如面柳如眉
對此如何不涙垂
春風桃李花開日
秋雨梧桐葉落時
あたりを想起する人もいるのであった。作者は、誰でも知っている中国古典を用いながら顛末を予感させつつ、そんな予感を越えた酷い情景を描いてゆく。紫式部というのは、「おらっ、私にちょっかいをだすとぶん殴るよ」と言っておいて、間髪入れずにハンマーで殴りつけるような人であった。考えてみると、その点、マルクスなんか、一度は悲劇次は喜劇とか、余裕をもっているところが、いじめられっ子的である。二度目が喜劇であるわけがなかろうがっ
参う上りたまふにも、あまりうちしきる折々は、打橋、渡殿のここかしこの道に、あやしきわざをしつつ、御送り迎への人の衣の裾、堪へがたく、まさなきこともあり。またある時には、え避らぬ馬道の戸を鎖しこめ、こなたかなた心を合はせて、はしたなめわづらはせたまふ時も多かり。
かようにガバナンスがまったくなっていない宮中である。こんなことをされて桐壺の更衣が反撃できないのはあれとして、帝も帝である。このあと、更衣の部屋を自分の近くに移すという逆効果のあれをやってしまうのであるが、考えてみれば、それより前に、いじめの首謀者たちを
Я смотрю на народ, в душе весна,
Нет ни бедности, ни печали.
Расцветает, как сад, страна;
В нем садовник — товарищ Сталин.
人民を見やれば、心は春のよう
貧しさも、悲しみもなく
国は庭園の如く花盛る
この園の庭師こそ - 同志スターリンだ
https://voenpesni.web.fc2.com/songs/Pesnya_o_Staline_Khachaturyan.html
思うに、帝と桐壺更衣のラブっぷりをみて長恨歌を思い出すような暗い心性だからいじめをやってしまうのであろう。上のような精神ならば、いじめに対しては明るく人民の首をはさみで刈り取る庭師になれる。まったく恐ろしいことである。考えてみると、これは気候の違いの問題かもしれない。田舎のトイレに行ったら、恐ろしく糞の氷山が出来ていて、すってんころりんと臀部を強打したぜ大変だ、みたいな手紙をショスタコービチはどこかで書いていた。日本では、糞を渡殿にぶちまけても花を愛でても気温がたいして変わらないからだめなのだ。何が「春はあけぼの」だ。ロシアでは「雪解け」といえば本当に感動的だったのである。