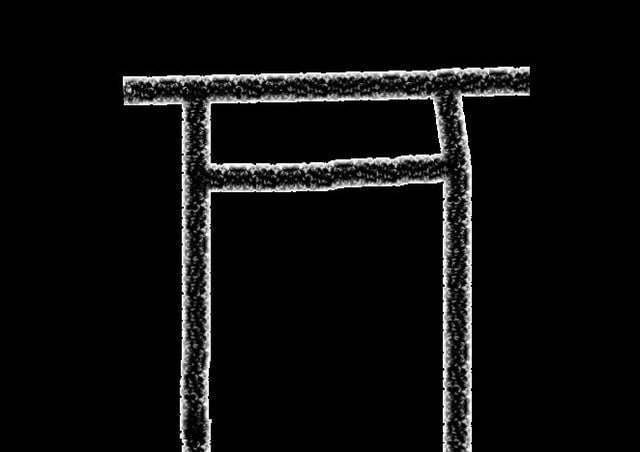藤壺は、よろづに思ほせど、ものものたまはず、帝の 御心を誤りにたればこそは、人は、かくは言ふらめ、かく言ふもしろく、御返し聞こえねど、立ち返り賜ひし御使ひも見えぬは、いかなるにかあらむ、このことは、げ、げに、さなりて、おとどものたまふやうになり給はば、我も尼なりなむ、何か、世に交じらむと思ほす。宮たちを見奉りておはす。若宮は、何心もなくて遊び歩き給ふ。
藤壺は、よろづに思ほせど、ものものたまはず、帝の 御心を誤りにたればこそは、人は、かくは言ふらめ、かく言ふもしろく、御返し聞こえねど、立ち返り賜ひし御使ひも見えぬは、いかなるにかあらむ、このことは、げ、げに、さなりて、おとどものたまふやうになり給はば、我も尼なりなむ、何か、世に交じらむと思ほす。宮たちを見奉りておはす。若宮は、何心もなくて遊び歩き給ふ。
藤壺も自分の息子が皇太子にならなければ尼になるぞと発言が生々しくなってゆく。これは必ずしも醜悪ではない。人間の真の姿があらわれるのは、自分が一方的な観察者でなくなったときである。
とりあえず疑問に思ったら発言して発言内容に責任をもつように行動した方がよいのは、それによって考えることが多くなっても、いろいろなことがわかるからだ。ただ命令にどれだけ従ったか、どれくらい仕事をしたかみたいなものだけでは、人のいろんな側面はみえない。人間に対する対処のあり方だけがそれを炙り出す。だから褒めるとか貶す前に、質問し意見を表明することが大事である。その反応で、どういう人間たちがどのように立ち回るかが観察出来る。それが可能なのは、自分が観察される対象になっているからだ。こういうときにしか面白い現象はあらわれない。
当事者性というのは、つねに観察者がなかば受け持っているものである。
昨今の組織の「評価」のありかたはそのことを無視して成り立っていることが多い。都合よく立ち回るずるい奴がいる大きな原因は「評価」をやってるからだ。しかもいまどきの言い方として、そのような現象に対して「評価はいいけどこいつクズやぞ」ではなく、「評価はいいけどこいつクズだよ、まあ評価はいいけど」になってしまう。大きな違いである。「評価」は組織の都合で相対化されていかようにもねじ曲がってしまうものである。本当は、最初の目的は組織そのものの評価を迫られていることから始まっているのであって、個人はどうでもよいからだ。しかし、そんなやり方では個人は育たない。
ほんとは小さいグループのボスがそういう不可視になりがちなズルしがちなクズを叩いて上に上がってこないようにしなければならないが、評価が一元化され統制化されるとそういう「教育」こそがノイズになりかねず、ますますクズがのし上がる次第となる。組織の中での仕事とは個人の仕事とみなされるものであっても、「全てが」一人でやってるものではない。だから、そもそも個人の評価をするという時点でかなり無理筋なことをやってることは明らかだ。のみならず、かかる無理だけでなく、――このような場合、かならずAはだめだけどBなら、みたいな自意識の形をとった認識=ルサンチマンを持ったタイプに評価(B)をあげる契機を与えてあげているようなものだ。かくして、……むかし「釣りバカ日誌」という夢物語みたいなものがあったが、いまや、あの主人公があいかわらず社長と仲良くしつつ評価を統括する側にまわり、自分を支えていたはずの地道な人材をいじめてるというかんじである。この主人公が、現実にルサンチマンを持っていないはずがない。
適材適所とかいうのはほとんどが実現出来ない理念であって、ある程度はAもBもできないと使い物にならない――というより、誠実に見ればAもBも繋がっているのだから分割が不能なのである。とにかく評価の規則のようなザルみたいなものに頼ると、本来うまいこと働いていたAとBを一体のものとしてみながらさしあたり分割しておくような能力が封印されてしまう。
革新勢力?が重要視していた法(規則)の創出みたいなものは、悪の禁止には向いていても、人を評価する方向では働きにくいというのはあると思う。
面接で不自然にニコニコにしてたり初対面でやたら目を合わせてくる人間を基本はじいた方がよいのは、常識というより、――目的のためにコミュニケーション能力みたいなものをつかってくるタイプだと見た方がよいからである。こんなのは、事務=手続きを官僚組織の肝と考える「公務員」的な人間にとっては常識であったはずだが、「評価」みたいな――通知表システムが始まったために、最近は教員にこびる生徒みたいな人間が増え始めている。それで思い出すのは、三島由紀夫である。
ある部分の学生運動も三島由紀夫も軍事にこだわっていたが、それには理由があった。旧日本軍というのがあまりにもあれで、エセ進学校じゃねえんだから軍隊としてありゃどうなんだよ、というのがあったと思うのである。彼らがやった戦いは、丸山眞男が言うまでもなく、学校的な「抑圧の移譲」みたいなものであって、名誉の死を覚悟する軍隊でもなければ、国=伝統を守るものでもなかった。前者は社会主義者、後者は三島のような右翼が持った不満であろう。彼らだけではない。一応、それこそままごとみたいなものだとはいえ、軍人の精神と名誉とは何か軍事作戦とは一体何ぞやというテーマでずっとサブカルの一部はやってきている。怪獣とかヒーローの可愛さにあまりに注目しすぎて、それがゆるキャラに脱線しようとも、そのテーマが消滅したことはない。しかし、最近はそのテーマの出してくる結論が、ギリシャ哲学経由でニーチェが褒めたような「友情」=名誉みたいなものとは似ても似つかないものになっている。私の誕生みたいなものにまで退行しているのである。基本設定が、人間でない状態から始まることが多いからだ。子ども番組が子育てどころではない、乳児からの離脱がテーマになってしまっている。
三島由紀夫が接触した自衛官の回想はいくつかあって読んで見たこともあるんだが、三島も最初、自衛官たちがある意味もう少し「受験生・官僚的な
感情的な阿諛追従の輩」だと思ってて、だからこそ感情的な回復が可能だと思ってたところがあるのではなかろうか。しかし目の前に居たのはもっと「公務員」みたいな人間だったのではないか。三島は、戦後の民主主義?がつくった大衆化されたなにか別ものをみたにちがいない。
しかし、まだ彼らは公務員的なものを大人とみなす、戦後の「理性の狡知」をおこなっていたような気がする。三島由紀夫は魂としての正しさはあるかもしれない。しかし彼の言っていることをそのまま口うつしに言いいはするが、教養もなく理性も働かない幼稚な輩がたくさん出てきたら国は滅んでしまう。そのために、魂のレベルでのシンクロは手続きを盾にして何もしないことを選ぶのが公務員である。私心を捨てよというのはそういうことで、評価が私心を復活させてしまった。それは、真の戦前回帰――ではない。目的を失った暴力の移譲である。