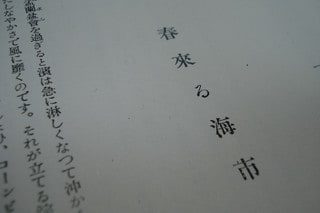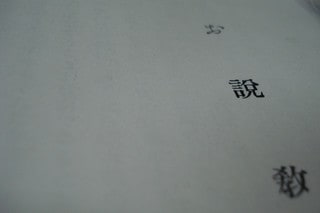コンビニで見かけたのだが、――三浦建太郎の「ベルセルク」がまだ終わってないことに気がついた。いま40巻である。ちょっとのぞいてみたら、主人公のいかつい男(名前忘却)がどこにも見当たらない。よくみると、犬がいて「ガッツさん」と呼ばれている。ああ、主人公はガッツだった。というか、いつの間に犬に……。どうやら、トラウマでおかしくなってしまった女の子(名前忘却)の意識の中に、なんか魔法使いみたいな二人組が入り込んでて、その意識の中では、ガッツさんは犬らしいのだ。
大願成就と聞いて、犬は嬉しくてたまらんので、三度うなってくるくるとまわって死んでしもうた、やがて何処よりともなく八十八羽の鴉が集まって来て犬の腹ともいわず顔ともいわず喰いに喰う事は実にすさましい有様であったので、通りかかりの旅僧がそれを気の毒に思うて犬の屍を埋めてやった、それを見て地蔵様がいわれるには、八十八羽の鴉は八十八人の姨の怨霊である、それが復讐に来たのであるから勝手に喰わせて置けば過去の罪が消えて未来の障りがなくなるのであった、それを埋めてやったのは慈悲なようであってかえって慈悲でないのであるけれども、これも定業の尽きぬ故なら仕方がない、これじゃ次の世に人間に生れても、病気と貧乏とで一生困められるばかりで、到底ろくたまな人間になる事は出来まい、とおっしゃった、…………………というような、こんな犬があって、それが生れ変って僕になったのではあるまいか、その証拠には、足が全く立たんので、僅に犬のように這い廻って居るのである。
――正岡子規「犬」
私は、10年前ぐらいから犬に関わる小説を集めていて、まだ論文に書いてないが、少しずつ読んでいる。わたくしが正岡子規をわりと好きなのは、上の文章を読んだからだが、ガッツさんは無事に老後を迎えられるであろうか。そういえば、ガッツさんはあんまり馬に乗っていなかった気がするが、馬に乗りすぎた御仁といえば、
聞こゆれば恥づかし、聞こえねば苦し
とただ言えばいいものを「むさしあぶみ」と書いてしまったので京の女に怒られた昔男がいた。よくわからんが、そもそも上の発言が、Aならば~、Aじゃなければ~云々という――理屈っぽすぎるものであった。それにしてはいってみたくなる類いのもので、
武蔵鐙さすがにかけて頼むにはとはぬもつらしとふもうるさし
と女。男はすかさず
とへばいふとはねば恨む武蔵鐙かかるをりにや人は死ぬらむ
と言い返す。最後に「死ぬ」と言ってしまったのは論理のなせるわざだ。もはや心情ではない。対して、「ベルセルク」は心情に拘りすぎている気がする。とはいえ、あまりに細密画ばっかり描いていたら、知らぬ間に近代じゃない世界を覗いていることはありうるのかもしれない。作家達は、われわれの大多数より先んじて、次の暗黒時代を生きる覚悟を決めているようである。