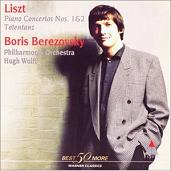最近、ロマン派の名曲が続きますが、本日もメンデルスゾーンの交響曲第3番をアップしたいと思います。これもかなり有名な作品なのですが、私の乏しいライブラリーにはメンデルスゾーンはヴァイオリン協奏曲と交響曲第4番「イタリア」しか入っておりませんでした。
この交響曲は「スコットランド」の別名で通っており、題名どおりメンデルスゾーンが当地を旅行した際に着想を得た作品とのことです。スコットランドと言えば天気が悪く、緑も少なそうなイメージを勝手に抱いてしまいますが、この曲もそれを裏付けるような陰りのある曲調ですね。とは言え、旋律自体は非常に美しく、交響曲として完成度の高い作品です。
第1楽章、いきなりメランコリックな弦楽アンサンブルから始まりますが、中間部以降は哀調の中に勇壮さを漂わせた魅力的な主題が最後まで続きます。第2楽章は陽気なスケルツォ風の親しみやすい旋律で、短調の本作品の中で異彩を放っています。第3楽章は一転してゆったりとしたアダージョで、弦楽の美しい響きが印象的です。第4楽章は木管楽器が哀調たっぷりの旋律を奏で、それにオーケストラが呼応するような形で進みますが、7分過ぎから急に転調して明るく雄大な曲想でフィナーレを迎えます。
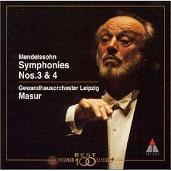
CDはクルト・マズア指揮ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団のものを買いました。このオケは18世紀から存在する世界でも最も伝統あるオケの一つで、何と19世紀半ばにはメンデルスゾーン自身が楽長を務めていたとか。ある意味、メンデルスゾーン作品を演奏するのにこれ以上ない陣容かもしれません。
カップリングは同じくメンデルスゾーンの交響曲第4番「イタリア」です。本作は20年ほど前にシノーポリ指揮でシューベルトの「未完成」とセットになったCDを購入していましたが、実は「未完成」ばかり聴いていていたためじっくり聴き込むのは今回が初めてです。第1楽章はイタリアの明るい太陽を思わせる華やかな曲調。この部分はTVCM等でもよく使われていますね。ただ、これがずっと続くと思うと肩すかしを食らいます。第2楽章は弦楽のピチカートをバックに物寂しげな主題を木管楽器が歌い上げます。第3楽章はゆったりしたメヌエット風で幾分か明るい印象。途中挟まれるホルンが牧歌的です。第4楽章はサルタレッロというイタリアの舞曲風のスタイルらしいですが、むしろ暗めの曲調で弦楽ユニゾンがどことなく不安を煽ったままフィナーレを迎えます。以上、出だしの脳天気さとは正反対の終わり方という変わった曲です。どちらもメンデルスゾーンの代表作として知られていますが、個人的には「スコットランド」の方がお気に入りですね。
この交響曲は「スコットランド」の別名で通っており、題名どおりメンデルスゾーンが当地を旅行した際に着想を得た作品とのことです。スコットランドと言えば天気が悪く、緑も少なそうなイメージを勝手に抱いてしまいますが、この曲もそれを裏付けるような陰りのある曲調ですね。とは言え、旋律自体は非常に美しく、交響曲として完成度の高い作品です。
第1楽章、いきなりメランコリックな弦楽アンサンブルから始まりますが、中間部以降は哀調の中に勇壮さを漂わせた魅力的な主題が最後まで続きます。第2楽章は陽気なスケルツォ風の親しみやすい旋律で、短調の本作品の中で異彩を放っています。第3楽章は一転してゆったりとしたアダージョで、弦楽の美しい響きが印象的です。第4楽章は木管楽器が哀調たっぷりの旋律を奏で、それにオーケストラが呼応するような形で進みますが、7分過ぎから急に転調して明るく雄大な曲想でフィナーレを迎えます。
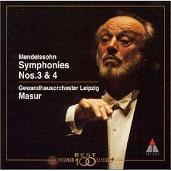
CDはクルト・マズア指揮ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団のものを買いました。このオケは18世紀から存在する世界でも最も伝統あるオケの一つで、何と19世紀半ばにはメンデルスゾーン自身が楽長を務めていたとか。ある意味、メンデルスゾーン作品を演奏するのにこれ以上ない陣容かもしれません。
カップリングは同じくメンデルスゾーンの交響曲第4番「イタリア」です。本作は20年ほど前にシノーポリ指揮でシューベルトの「未完成」とセットになったCDを購入していましたが、実は「未完成」ばかり聴いていていたためじっくり聴き込むのは今回が初めてです。第1楽章はイタリアの明るい太陽を思わせる華やかな曲調。この部分はTVCM等でもよく使われていますね。ただ、これがずっと続くと思うと肩すかしを食らいます。第2楽章は弦楽のピチカートをバックに物寂しげな主題を木管楽器が歌い上げます。第3楽章はゆったりしたメヌエット風で幾分か明るい印象。途中挟まれるホルンが牧歌的です。第4楽章はサルタレッロというイタリアの舞曲風のスタイルらしいですが、むしろ暗めの曲調で弦楽ユニゾンがどことなく不安を煽ったままフィナーレを迎えます。以上、出だしの脳天気さとは正反対の終わり方という変わった曲です。どちらもメンデルスゾーンの代表作として知られていますが、個人的には「スコットランド」の方がお気に入りですね。