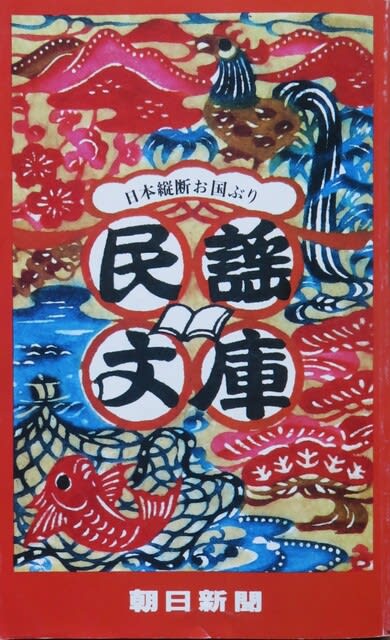先日、不要雑物整理廃棄処分中に、記憶から完全に喪失していた小冊子2冊が出てきた。
表題は、「日本縦断お国ぶり・民謡文庫」
何時頃、入手したものやら、ページを開いてみても、まるっきり覚えが無く、巻末を見ると、
制作・発行は NHKサービスセンターで、1981、1982、(無断転記禁ず)となっている。
どうも非売品のようで、表紙には、「朝日新聞」と印刷されていることから、何かの進呈品だったのかも知れない。

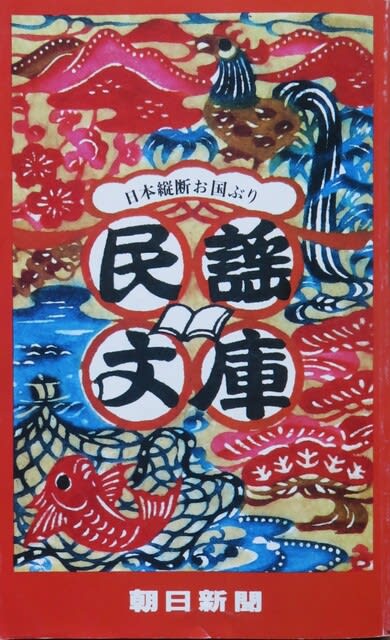
「民謡」・・・、最近は、とんと聴く機会が無くなってしまっているが、子供の頃は、よくラジオ等から流れていて、NHKの素人のど自慢等でも、盛んに民謡が歌われていたような気がする。
子供のこととて、しっかり覚えるようなことは無かったが、なんとなく脳裏に焼き付いている民謡が、かなり有り、懐かしくもなる。
昭和20年代後半から30年代、小学生、中学生の内から、民謡が好きだった祖母と一緒になってNHKラジオ第1放送の夜8時台の放送番組、「民謡はこころのふるさと・・・・♫」のナレーションで始まる「民謡をたずねて」という番組をなんとなく聴いていたこともあって、どちらかというと、民謡に親しみを感ずる人間になっている気がする。
昔のことを懐かしがるのは、老人のもっとも老人たるところだが、ページを捲りながら、
ボチボチと ランダムに、日本全国の「民謡をたずねて」・・・、みよう等と思い込んだところだ。
民謡をたずねて・その14
「南部俵積み唄(なんぶたわらつみうた)・俵つみ唄」
(青森県)
子供の頃、なんとなく聞いていた民謡の中には、まるで曲調も歌詞も記憶に残っていないものがほとんどだが、後年になってから、へー!、そういう民謡だったのか・・・等と改めて思い直し、お気に入り?に入れているような民謡もかなり有る。
「南部俵積み唄(単に「俵つむ唄」と呼ばれることも有るようだが)も、そのひとつ。
今更になって、ネットで調べてみると、
「南部俵積み唄」は、旧南部領(現在の青森県三戸郡)に伝わる民謡で、元々は、「門付唄(かどづけうた)」だったのだという。
「門付(かどづけ)」とは、正月や節分等の節目に、家々の門口や座敷を訪れ、太鼓や三味線ともに、舞などを披露して、米や銭を受け取る大道芸の一種で、そこで歌われた唄が「門付唄(かどづけうた)」。
「門付」は、三戸地方に限らず、江戸時代から全国各地で見られ、現代の「漫才」のルーツだと言われている。
そんな「南部俵積み唄」を、昭和30年代後半、民謡歌手の館松栄喜が歌い、レコードを発売したことで、全国的に知られる民謡に育っていったのだそうだ。
「南部俵積み唄」 (YouTubeから共有)