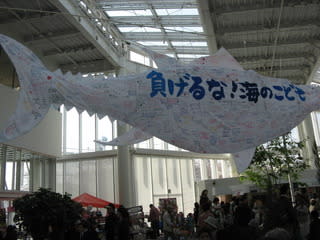自分が自分である証明は?

* * * * * * * *
リーアム・ニーソン主演のサスペンス・アクション。
ミステリじみた状況が興味を誘います。

医学博士マーティン・ハリス(リーアム・ニーソン)は、
学会へ出席するために、若い妻と共にベルリンへやって来ました。
しかし忘れ物に気づき、ホテルから飛行場へ向かうタクシーで事故に遭ってしまいます。
4日間の昏睡から目覚めた彼。
ところが妻からは知らない人といわれ、
また見ず知らずの男がマーティン・ハリスと名乗り、
彼になりかわって過ごしている。
身分を証明するものもなく、孤立無援。
事故のために本当に自分の頭がどうかしてしまったのか?
自分はマーティン・ハリスではないのか?
ところが彼は、自分の命を狙う謎の人物に付け狙われていることに気づくのです。
一体自分は何者なのか。
そして彼を付け狙うものの正体は?
このストーリーで怖いのは、
自分が何者かという証明は実はとても難しいし、
周りのあらゆる人に、あなたは知らない人だといわれたら、
自分自身をも信じられなくなってくる、というところ。
パスポートやカード、そういうものがなければ、自分を自分と証明できない。
現代社会の危うさです。
こんなことになってしまったら、
もう社会的に抹殺されたも同様。
ところがやっかいなことに、
そうした状況では自分自身でも自分が何者か解らなくなって来てしまいます。
現に記憶喪失や様々な精神疾患がある以上、
自分が絶対に正しいともいい切れない。
そういう危うさが何だか見にしみます。
このストーリーは、マーティンが自分のホームグラウンドでなく、
見知らぬ外国に来ている、というところで、
余計にこの状況を引き立たせているわけです。
また、水没したタクシーからの脱出がとてもリアルで怖かった・・・。
運転していたのは女性ドライバーで、
彼女がいち早くウインドウのガラスを割り、
気絶したマーティンを救い出すのです。
車が水没すると水圧でドアは決して開かないといいます。
だからあのように、ガラスを割る道具を常備していなければならない・・・と。
いつぞやTVでやっていたのを思い出しましたが、
この作品ですごく納得してしまいました。
そうして、その後彼女がマーティンの手助けをすることになるのですが、
こんなふうに女性がたくましいのも今風でいいですね。

ラストは確かに予測不能でした・・・!
冒頭の飛行場での二人の会話がヒントと言えばヒントですが、
まあ、それで解るわけもありませんか・・・。
とりあえず、タクシーの事故は仕組まれたものではなく、
偶発的なものだったということですね。
それにしてはこんな終わり方でいいのか、という気もしてしまいますが。
リーアム・ニーソンはもう結構なお年でありながら、
アクション満載。
ご苦労様です。
女性パワーもさることながら、熟年パワーも炸裂。
「アンノウン」
2011年/アメリカ/113分
監督:ジャウム・コレット=セラ
原作:ディディエ・バン・コーブラール
出演:リーアム・ニーソン、ダイアン・クルーガー、ジャニュアリー・ジョーンズ、エイダン・クイン

* * * * * * * *
リーアム・ニーソン主演のサスペンス・アクション。
ミステリじみた状況が興味を誘います。

医学博士マーティン・ハリス(リーアム・ニーソン)は、
学会へ出席するために、若い妻と共にベルリンへやって来ました。
しかし忘れ物に気づき、ホテルから飛行場へ向かうタクシーで事故に遭ってしまいます。
4日間の昏睡から目覚めた彼。
ところが妻からは知らない人といわれ、
また見ず知らずの男がマーティン・ハリスと名乗り、
彼になりかわって過ごしている。
身分を証明するものもなく、孤立無援。
事故のために本当に自分の頭がどうかしてしまったのか?
自分はマーティン・ハリスではないのか?
ところが彼は、自分の命を狙う謎の人物に付け狙われていることに気づくのです。
一体自分は何者なのか。
そして彼を付け狙うものの正体は?
このストーリーで怖いのは、
自分が何者かという証明は実はとても難しいし、
周りのあらゆる人に、あなたは知らない人だといわれたら、
自分自身をも信じられなくなってくる、というところ。
パスポートやカード、そういうものがなければ、自分を自分と証明できない。
現代社会の危うさです。
こんなことになってしまったら、
もう社会的に抹殺されたも同様。
ところがやっかいなことに、
そうした状況では自分自身でも自分が何者か解らなくなって来てしまいます。
現に記憶喪失や様々な精神疾患がある以上、
自分が絶対に正しいともいい切れない。
そういう危うさが何だか見にしみます。
このストーリーは、マーティンが自分のホームグラウンドでなく、
見知らぬ外国に来ている、というところで、
余計にこの状況を引き立たせているわけです。
また、水没したタクシーからの脱出がとてもリアルで怖かった・・・。
運転していたのは女性ドライバーで、
彼女がいち早くウインドウのガラスを割り、
気絶したマーティンを救い出すのです。
車が水没すると水圧でドアは決して開かないといいます。
だからあのように、ガラスを割る道具を常備していなければならない・・・と。
いつぞやTVでやっていたのを思い出しましたが、
この作品ですごく納得してしまいました。
そうして、その後彼女がマーティンの手助けをすることになるのですが、
こんなふうに女性がたくましいのも今風でいいですね。

ラストは確かに予測不能でした・・・!
冒頭の飛行場での二人の会話がヒントと言えばヒントですが、
まあ、それで解るわけもありませんか・・・。
とりあえず、タクシーの事故は仕組まれたものではなく、
偶発的なものだったということですね。
それにしてはこんな終わり方でいいのか、という気もしてしまいますが。
リーアム・ニーソンはもう結構なお年でありながら、
アクション満載。
ご苦労様です。
女性パワーもさることながら、熟年パワーも炸裂。
「アンノウン」
2011年/アメリカ/113分
監督:ジャウム・コレット=セラ
原作:ディディエ・バン・コーブラール
出演:リーアム・ニーソン、ダイアン・クルーガー、ジャニュアリー・ジョーンズ、エイダン・クイン