時を飛び越え、人の世の移り変わりを見る存在

* * * * * * * * * * * *
本作は確か原作を読んだのですが、映画は見ていませんでした。
音楽好きの死神・千葉(金城武)は雨男。
彼が人間界に現れるときにはいつも雨が降っています。
死神の彼は、7日後に死ぬ予定の人間に近づき、
「実行=死」か、「見送り=生かす」かを判定するのが仕事。
本作ではまず、薄幸の女性・藤木一恵(小西真奈美)に近づき、観察を始めます。
そしていよいよ判定を下そうとするその日、彼女に思いがけない運命が・・・。

千葉はこれまで判定を「見送り」にしたことがないのです。
ほとんどは予定通り「実行」となる。
けれどもこのたびの判定は・・・。
そして場面は変わり、時を経て、千葉は別の人物のところを訪れます。
本作ではその後、もう一人の別の人物のところへ行く。
つまり本作は大きく3つの場面に別れているのですが、
実は時を経て、同一人物の付近を描いているのです。
死神という人間ではない存在が、人の世の移り変わりをこともなく通り過ぎて現れる。
そうした視点がなかなか切ないですね。
ちょっとヴァンパイアにも似た存在なのでした。
千葉はさして人間界に興味はないので、言葉使いが少しトンチンカン。
そのずれた感じが楽しめます。
こういう浮世離れした感じ、金城武に実に似合います。
素晴らしいキャスティング。
少し古い作品を見るときには、
今活躍中の俳優が端役で現れたりするのを見つけるのが楽しみの一つ。
本作には田中哲司さんが出ていました。
当ブログで原作本のことを確認しましたが、
映画とはちがう場面から始まっているようです。
興味がありましたら、こちらをどうぞ。
<WOWOW視聴にて>
「Sweet Rain 死神の精度」
2008年/日本/113分
監督:筧昌也
原作:伊坂幸太郎
出演:金城武、小西真奈美、富司純子、光石研、村上淳、田中哲治
伊坂ワールド度★★★★☆
満足度★★★★☆










![Sweet Rain 死神の精度 コレクターズ・エディション [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51-yuhLpCsL._SL160_.jpg)









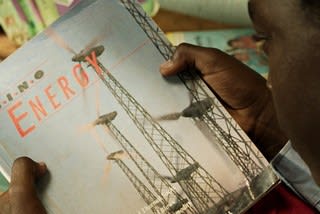




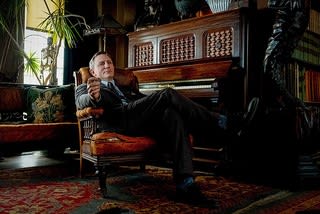









![スノー・ロワイヤル [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/414%2BUJu9OxL._SL160_.jpg)






