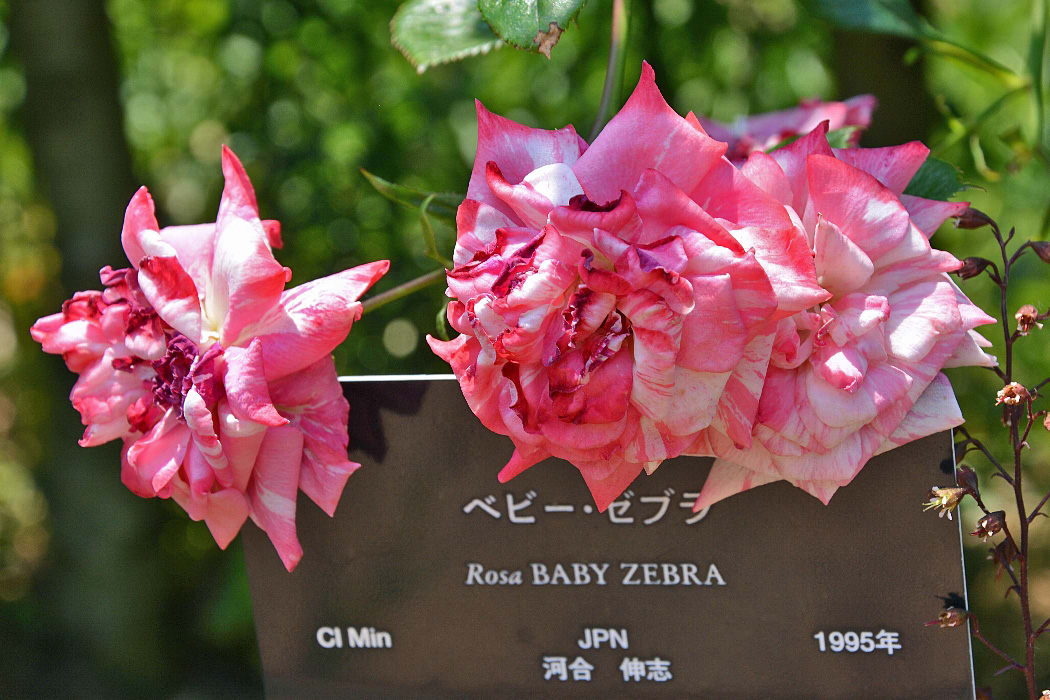「神奈川県立 花と緑のふれあいセンター“花菜(かな)ガーデン”」で今年5月27日に撮影した

「ヘルガス・ドリーム」。

ネットで検索しましたが全くヒットしません。名札も右下に張り付けたような簡単なもの。
ハイブリッド・ムルティフローラ系のオールドローズ(HMult)としかわかりません。
HMultはノイバラを交配親にした系統で、半つる性またはつる性となり、花は大きな房になって開花する。一般にはランブラーとして扱われる。

こちらは2014年5月23日に撮影していた「ヘルガス・ドリーム」。

通路にかかったアーチに仕立てられていたんですね。

2014年5月23日に1枚だけ撮っていたのが「ブルー・マジェンタ」。
こちらもHMultで1900年ころから知られている品種。香りは微香。
咲き始めの明るい赤紫色から、グレーを帯びた深みのある紫に変わり、見ごたえのあるグラデーションができる。
小さな花弁は盛り上がってポンポン咲きのようになる。枝はとげが少なくしなやかで扱いやすい。