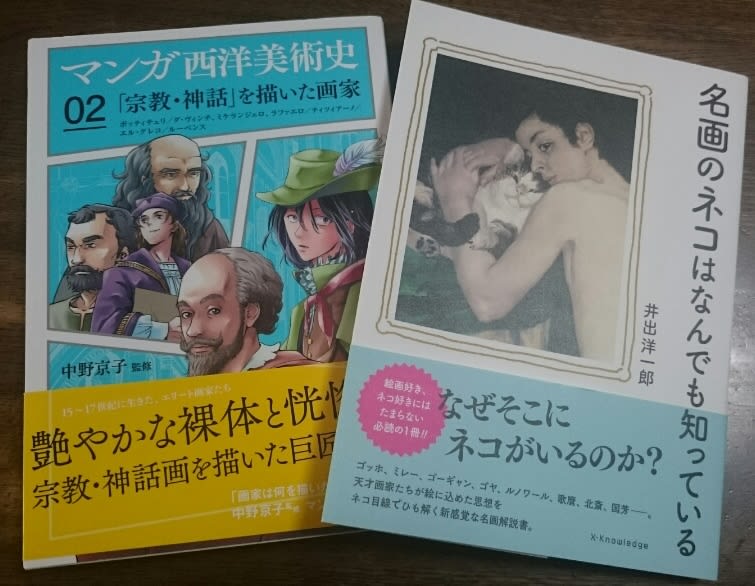相模湖っていったらピクニックランドかなー、昔行ったことあるよ。すごい田舎のイメージだったんだけど…
 ←音符を追うだけで必死だと聞く余裕がないから楽譜白い系がイイ
←音符を追うだけで必死だと聞く余裕がないから楽譜白い系がイイ
行ってみたら案外近かった。高尾の一駅先だものね。都会に行くより簡単。あ、うちが田舎よりだってだけだけど。
響きのいいホール、弾きやすいベーゼンドルファー、いいねこの会場(^o^)/
昨日のはYUMIさん主催でカンタービレ練習会。ただ弾きたい人は弾くし、レッスン希望の人はartomrさんが見てくれていずれも30分。しかし、自分で弾くなら30分は長いがレッスンとなると30分は短いよね??
はるさいを30分見てもらっても、混迷のうちに終わりそうな気がしたので、とりあえずふつうには並びそうなマメールロア(の4と5)にしました。
私が会場へ入ったときはちょうどYUMIさんがシューベルトの即興曲を見てもらってるところでした。私この曲はちょっとトラウマで、といっても自分で弾いたことがあるわけじゃないのですが、昭和の音楽教室では超耳タコ曲、しかも発表会でよく聞く曲ね。そんで、なんかこの長すぎる単調な曲をうだうだ弾かれるとこれがもうとてつもなく退屈なんですよ。あーまた似たようなところ出てきたぁ。。って感じ
シューベルトってちょっとね。と思っちゃってる一番のひっかかりはこれじゃないかって曲なんです。
ところが、この曲の音階ちっくなところを、artomrくんがこのホールのこのベーゼンで弾くと、きれいに響いて心うきうき。あれ?? これ悪くないぞ。
そしてあちこち、ノリや間や音の出し方や流れを改善していくのを聞いていると、あれーこの曲、そこまで単調じゃなかったかも(笑) YUMIさんの出す音もどんどん変わっていっておもしろい(^-^)
というわけでかなりシューベルト(のこの曲)を見直したところで自分の順番。
…まずは合わせてみると…
とりあえず通るんだけど、ってか、この曲の1stは相当音数が少ないんで、そりゃ通るんだけど、
フレーズの形とか、ここはこういう音じゃなくてこういう音、と細かくいっていくときりがない感じで、おぉーこれは30分で5(最終曲)まで行くんだろうか、とか思っていたのですが、昨日のartomrくんはしっかり時計見ていて、めいっぱいの時間の使い方を計画的にこなしていましたよ。
代表的なところをとりあげて、いくつか直してもらうだけでも、ぜんぜん響きが変わってくるもんです。
「ここはもっと2ndとハモるように」とかいっても、バイオリンじゃあるまいし、ハナっから別に音程狂ってるわけじゃないんですが、それでもよく聞いてなんか寄り添うように弾いてみるとほんとにハモるのが不思議です。
「そこ、2拍目の音が死んでる」
とかダメ出しされて冷や汗をいっぱいかきながら、
弾きなおした感じはぐっとよくなって、ただなかなか思ったようには安定して弾けなくて、「おっ、こんな感じ」と思ったり「あーーやっちゃった」と思ったり…
でもうまく響いたときはほんとに素敵。これがホールレッスンの醍醐味だよね。
家に帰ってから、録音を聞いてみたんだけど、スピーカーがパソコンのスピーカーなのもあって(爆)きれいに響いたときと死んだ音出してたときの差がいまいちわからないし、それにピアノの音と話し声の音量がすごく違うせいで話はほとんど聞き取れなくて、これじゃしょうがないな。間近で、ビデオに収めるのがいいんでしょうね(記録するとすれば)
横からこじろうが聞いていて、「今のジャララララ(グリッサンド)のところ、お母さん??」(と疑わしそうに)
そうだよーお母さんだよー(えへん)
あんまり弾くと痛くなるから、家では弾かずに、場所と回数だけ確かめていたからこじろうは聞き覚えがなかったんだ、そこだけ。で、ぶっつけだったけどグリッサンドはわりときれいに弾けたの。この「グリッサンドの嵐」の5番はイロモノオフで鳥目さんとやります。
にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも
にほんブログ村 中高一貫教育

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社 ←またろうがイラストを描いた本(^^)
←またろうがイラストを描いた本(^^)

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社
(今回もイラストはまたろう)
行ってみたら案外近かった。高尾の一駅先だものね。都会に行くより簡単。あ、うちが田舎よりだってだけだけど。
響きのいいホール、弾きやすいベーゼンドルファー、いいねこの会場(^o^)/
昨日のはYUMIさん主催でカンタービレ練習会。ただ弾きたい人は弾くし、レッスン希望の人はartomrさんが見てくれていずれも30分。しかし、自分で弾くなら30分は長いがレッスンとなると30分は短いよね??
はるさいを30分見てもらっても、混迷のうちに終わりそうな気がしたので、とりあえずふつうには並びそうなマメールロア(の4と5)にしました。
私が会場へ入ったときはちょうどYUMIさんがシューベルトの即興曲を見てもらってるところでした。私この曲はちょっとトラウマで、といっても自分で弾いたことがあるわけじゃないのですが、昭和の音楽教室では超耳タコ曲、しかも発表会でよく聞く曲ね。そんで、なんかこの長すぎる単調な曲をうだうだ弾かれるとこれがもうとてつもなく退屈なんですよ。あーまた似たようなところ出てきたぁ。。って感じ
シューベルトってちょっとね。と思っちゃってる一番のひっかかりはこれじゃないかって曲なんです。
ところが、この曲の音階ちっくなところを、artomrくんがこのホールのこのベーゼンで弾くと、きれいに響いて心うきうき。あれ?? これ悪くないぞ。
そしてあちこち、ノリや間や音の出し方や流れを改善していくのを聞いていると、あれーこの曲、そこまで単調じゃなかったかも(笑) YUMIさんの出す音もどんどん変わっていっておもしろい(^-^)
というわけでかなりシューベルト(のこの曲)を見直したところで自分の順番。
…まずは合わせてみると…
とりあえず通るんだけど、ってか、この曲の1stは相当音数が少ないんで、そりゃ通るんだけど、
フレーズの形とか、ここはこういう音じゃなくてこういう音、と細かくいっていくときりがない感じで、おぉーこれは30分で5(最終曲)まで行くんだろうか、とか思っていたのですが、昨日のartomrくんはしっかり時計見ていて、めいっぱいの時間の使い方を計画的にこなしていましたよ。
代表的なところをとりあげて、いくつか直してもらうだけでも、ぜんぜん響きが変わってくるもんです。
「ここはもっと2ndとハモるように」とかいっても、バイオリンじゃあるまいし、ハナっから別に音程狂ってるわけじゃないんですが、それでもよく聞いてなんか寄り添うように弾いてみるとほんとにハモるのが不思議です。
「そこ、2拍目の音が死んでる」
とかダメ出しされて冷や汗をいっぱいかきながら、
弾きなおした感じはぐっとよくなって、ただなかなか思ったようには安定して弾けなくて、「おっ、こんな感じ」と思ったり「あーーやっちゃった」と思ったり…
でもうまく響いたときはほんとに素敵。これがホールレッスンの醍醐味だよね。
家に帰ってから、録音を聞いてみたんだけど、スピーカーがパソコンのスピーカーなのもあって(爆)きれいに響いたときと死んだ音出してたときの差がいまいちわからないし、それにピアノの音と話し声の音量がすごく違うせいで話はほとんど聞き取れなくて、これじゃしょうがないな。間近で、ビデオに収めるのがいいんでしょうね(記録するとすれば)
横からこじろうが聞いていて、「今のジャララララ(グリッサンド)のところ、お母さん??」(と疑わしそうに)
そうだよーお母さんだよー(えへん)
あんまり弾くと痛くなるから、家では弾かずに、場所と回数だけ確かめていたからこじろうは聞き覚えがなかったんだ、そこだけ。で、ぶっつけだったけどグリッサンドはわりときれいに弾けたの。この「グリッサンドの嵐」の5番はイロモノオフで鳥目さんとやります。
にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも
にほんブログ村 中高一貫教育

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社
(今回もイラストはまたろう)