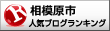鳩森八幡神社から東へ。坂道を降りると国立競技場が見えてきた。
この信号の向こうは「明治公園」。何げに明治が早くも登場しました。
でっかい国立競技場の円周に沿って、青山門へ移動。

 お鷹の松
お鷹の松
まず見つけたのはお鷹の松、「大正7年(1918)明治神宮外苑競技場(現・国立霞ヶ丘競技場)造成のために買い上げた霞岳町の敷地内に境妙寺という古寺があった。昔、徳川家光がお鷹狩りの途中この寺で休憩していたところ、江戸城から「遊女」という愛鷹が飛んで来て、庭前の松の枝に止まったので家光は大変喜び、この松をその鷹の名前をとって「遊女の松」と名付けたと伝えられる。後の世の人びとが、「お鷹の松」或は地名をとって「霞の松」とも呼んだ。碑文にある二代目の松(樹齢200年 高さ4メートル)は昭和39年、東京オリンピック開催のための拡張工事の際に取り去られ、碑石は競技場代々木門内に移設されていたが、このたび現在地に移し、新たにこれに黒松を配したものである。」
だそうで。…え~と?もしかせんでも、この松はお鷹の松とは全然関係ない松だよね?二代目の松ですらねえっ!!つーか、二代目は東京オリンピックの時に取り去った!ってソレ、抜いて捨てたんかいっ!!
つ、次だ。次、行ってみよう。
絵画館が見えてきた。(トップ画像)。ブラタモリで言ってたけど、絵画館で窓のない国会議事堂の外観してるよな。
さて、この辺りに樺太国境画定標石があるはずなんだが…。
どこだろう~?
あんまり一心に探しすぎて、あっこさんとはぐれてしまった。
ああっ!!発見です。


樺太国境画定標石 明治37.38年に日露戦役の講和条約で樺太の北緯50度以南は、日本の領土になりました。
その境界を標示するため、日露両国委員は、明治40年9月4基の天測標と17基小標石を建てて境界を確定しました。
この境界標石は、外苑創設に際し、明治時代の一つの記念物として、樺太庁が之を模造し外苑に寄贈したものです。当時苑内北方隅の樹間に在りましたが、この度、全国樺太連盟よりの、これが顕彰周知方の篤い要望に応えて、絵画館前の現地に移し整備配置しました。
日本側の菊の紋章の背面には露国の鷲の紋章が刻んであります。
又、聖徳記念絵画館の壁画「樺太国境画定」(安田稔画)には、両国委員が境界標を建設する光景を史実に基づいて描いた絵画が展示されております」
う~~ん。石の裏側は立ち入り禁止で確認出来ない~。

ブラタモリでは絵画館の屋上に上がって撮影してましたが、上の画像の中央奥にあるのが有名な外苑の銀杏並木です。
ちなみに、手前の池はかつてプールだったことがあるんだって。ってブラタモリで言ってました。かっぱ天国とかなんとか~。
実はトップ画像の絵画館の画像を選んだのは、絵画館の建物でなくアスファルトを見ていただきたかったから。
明治神宮外苑の舗装
工期:1924年5月ー1926年1月
明治神宮外苑の道路の舗装は、東京市(当時)でも大規模で本格的な加熱アスファルト混合物を用いた舗装であり、1926年(大正15年)1月に完成しました。
この工事は、我が国においてワービット工法を採用した最初の工事であったばかりでなく、アスファルトは国産品(秋田県豊川産)を使用し、当時の最新鋭機による機会化施行が行われました。
この舗装は長い年月の使用に耐え、66年間(1992年改良)にわたって車道として使われてきたことは、驚嘆に値します。また、この案内板の前の舗装は当時のまま現存しており、日本における車道用アスファルト舗装としては最古のものです。
ということで、トップ画像のアスファルトは、1926年に作られたオリジナルの車道です。
凄いよね。
ところで、またまた疑問を拾ってしまった…。
それは、国産のアスファルトを使用し…の部分です。
アスファルトって、道路の舗装で使ってるアレだよね?
あれって、石油製品でしょう?違うの?つーか、日本産のアスファルトが存在してるのかぁ~~!!
さっそくWIKIで検索。
「アスファルト=土瀝青。原油に含まれる炭化水素類の中で最も重質のものである。減圧蒸留装置で作られた減圧残油はそのまま製品アスファルトとなり、ストレート・アスファルトと呼ばれる。」
わ~か~ら~な~い~。説明文が既に専門用語。
でも瀝青というのには見覚えが…。
アスファルトの歴史…古代から使用されてきた。日本では縄文時代後期から北海道から日本海側で産出した天然アスファルトを熱して石鏃(石の矢じり)や骨銛(骨のモリ)など漁具の接着、破損した土器や土偶の修復、漆器の下塗りなどに利用された。<wikiより>
そうだったのか。私が物知らずなだけというオチでした。

もう一つ、明治の名残は御観兵榎です。
かつて、この辺りには陸軍の青山練兵場があって、明治天皇の御台臨のもとにしばしば観兵式が行われ、なかでも明治23年(1890)2月11日の憲法発布観兵式や、明治39年(1906)4月30日の日露戦役凱旋観兵式などは、特に盛大でした。
明治天皇が御観兵される時は、いつもこの榎の西前方に御座所が設けられたので、この榎を、「御観兵榎」と命名し永く保存しておりましたが、平成7年(1995)9月17日老令(樹齢200余年)の為台風12号の余波の強風により倒木しました。
平成8年(1996)1月、初代御観兵榎の自然実生忌推定樹齢60年)を苑内より移植し、「二代目御観兵榎」として植え継ぎました。

見つけました。これは由緒は正しいけど、明治天皇の御観兵榎じゃないんですが、脇にある石に注目。
 題字 東郷平八郎書
題字 東郷平八郎書
明治38年日本海海戦においてロシアバルチック艦隊を壊滅させた、当時の連合艦隊司令長官 東郷神社の祭神
かつての明治神宮の外苑施設、青山練兵場、昭和の東京オリンピックの名残りが外苑には探せばのこっています。
私が発見したのはこれ。

石で組んだ入り口です。ここを徒歩で北へ歩いたのですが、古いタイプの石柱と鉄棒の柵とか、北にも石の入り口が残ってました。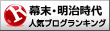 幕末・明治(日本史) ブログランキングへ
幕末・明治(日本史) ブログランキングへ
この信号の向こうは「明治公園」。何げに明治が早くも登場しました。
でっかい国立競技場の円周に沿って、青山門へ移動。

 お鷹の松
お鷹の松まず見つけたのはお鷹の松、「大正7年(1918)明治神宮外苑競技場(現・国立霞ヶ丘競技場)造成のために買い上げた霞岳町の敷地内に境妙寺という古寺があった。昔、徳川家光がお鷹狩りの途中この寺で休憩していたところ、江戸城から「遊女」という愛鷹が飛んで来て、庭前の松の枝に止まったので家光は大変喜び、この松をその鷹の名前をとって「遊女の松」と名付けたと伝えられる。後の世の人びとが、「お鷹の松」或は地名をとって「霞の松」とも呼んだ。碑文にある二代目の松(樹齢200年 高さ4メートル)は昭和39年、東京オリンピック開催のための拡張工事の際に取り去られ、碑石は競技場代々木門内に移設されていたが、このたび現在地に移し、新たにこれに黒松を配したものである。」
だそうで。…え~と?もしかせんでも、この松はお鷹の松とは全然関係ない松だよね?二代目の松ですらねえっ!!つーか、二代目は東京オリンピックの時に取り去った!ってソレ、抜いて捨てたんかいっ!!
つ、次だ。次、行ってみよう。
絵画館が見えてきた。(トップ画像)。ブラタモリで言ってたけど、絵画館で窓のない国会議事堂の外観してるよな。
さて、この辺りに樺太国境画定標石があるはずなんだが…。
どこだろう~?
あんまり一心に探しすぎて、あっこさんとはぐれてしまった。
ああっ!!発見です。


樺太国境画定標石 明治37.38年に日露戦役の講和条約で樺太の北緯50度以南は、日本の領土になりました。
その境界を標示するため、日露両国委員は、明治40年9月4基の天測標と17基小標石を建てて境界を確定しました。
この境界標石は、外苑創設に際し、明治時代の一つの記念物として、樺太庁が之を模造し外苑に寄贈したものです。当時苑内北方隅の樹間に在りましたが、この度、全国樺太連盟よりの、これが顕彰周知方の篤い要望に応えて、絵画館前の現地に移し整備配置しました。
日本側の菊の紋章の背面には露国の鷲の紋章が刻んであります。
又、聖徳記念絵画館の壁画「樺太国境画定」(安田稔画)には、両国委員が境界標を建設する光景を史実に基づいて描いた絵画が展示されております」
う~~ん。石の裏側は立ち入り禁止で確認出来ない~。

ブラタモリでは絵画館の屋上に上がって撮影してましたが、上の画像の中央奥にあるのが有名な外苑の銀杏並木です。
ちなみに、手前の池はかつてプールだったことがあるんだって。ってブラタモリで言ってました。かっぱ天国とかなんとか~。
実はトップ画像の絵画館の画像を選んだのは、絵画館の建物でなくアスファルトを見ていただきたかったから。
明治神宮外苑の舗装
工期:1924年5月ー1926年1月
明治神宮外苑の道路の舗装は、東京市(当時)でも大規模で本格的な加熱アスファルト混合物を用いた舗装であり、1926年(大正15年)1月に完成しました。
この工事は、我が国においてワービット工法を採用した最初の工事であったばかりでなく、アスファルトは国産品(秋田県豊川産)を使用し、当時の最新鋭機による機会化施行が行われました。
この舗装は長い年月の使用に耐え、66年間(1992年改良)にわたって車道として使われてきたことは、驚嘆に値します。また、この案内板の前の舗装は当時のまま現存しており、日本における車道用アスファルト舗装としては最古のものです。
ということで、トップ画像のアスファルトは、1926年に作られたオリジナルの車道です。
凄いよね。
ところで、またまた疑問を拾ってしまった…。
それは、国産のアスファルトを使用し…の部分です。
アスファルトって、道路の舗装で使ってるアレだよね?
あれって、石油製品でしょう?違うの?つーか、日本産のアスファルトが存在してるのかぁ~~!!
さっそくWIKIで検索。
「アスファルト=土瀝青。原油に含まれる炭化水素類の中で最も重質のものである。減圧蒸留装置で作られた減圧残油はそのまま製品アスファルトとなり、ストレート・アスファルトと呼ばれる。」
わ~か~ら~な~い~。説明文が既に専門用語。
でも瀝青というのには見覚えが…。
アスファルトの歴史…古代から使用されてきた。日本では縄文時代後期から北海道から日本海側で産出した天然アスファルトを熱して石鏃(石の矢じり)や骨銛(骨のモリ)など漁具の接着、破損した土器や土偶の修復、漆器の下塗りなどに利用された。<wikiより>
そうだったのか。私が物知らずなだけというオチでした。

もう一つ、明治の名残は御観兵榎です。
かつて、この辺りには陸軍の青山練兵場があって、明治天皇の御台臨のもとにしばしば観兵式が行われ、なかでも明治23年(1890)2月11日の憲法発布観兵式や、明治39年(1906)4月30日の日露戦役凱旋観兵式などは、特に盛大でした。
明治天皇が御観兵される時は、いつもこの榎の西前方に御座所が設けられたので、この榎を、「御観兵榎」と命名し永く保存しておりましたが、平成7年(1995)9月17日老令(樹齢200余年)の為台風12号の余波の強風により倒木しました。
平成8年(1996)1月、初代御観兵榎の自然実生忌推定樹齢60年)を苑内より移植し、「二代目御観兵榎」として植え継ぎました。

見つけました。これは由緒は正しいけど、明治天皇の御観兵榎じゃないんですが、脇にある石に注目。
 題字 東郷平八郎書
題字 東郷平八郎書明治38年日本海海戦においてロシアバルチック艦隊を壊滅させた、当時の連合艦隊司令長官 東郷神社の祭神
かつての明治神宮の外苑施設、青山練兵場、昭和の東京オリンピックの名残りが外苑には探せばのこっています。
私が発見したのはこれ。

石で組んだ入り口です。ここを徒歩で北へ歩いたのですが、古いタイプの石柱と鉄棒の柵とか、北にも石の入り口が残ってました。