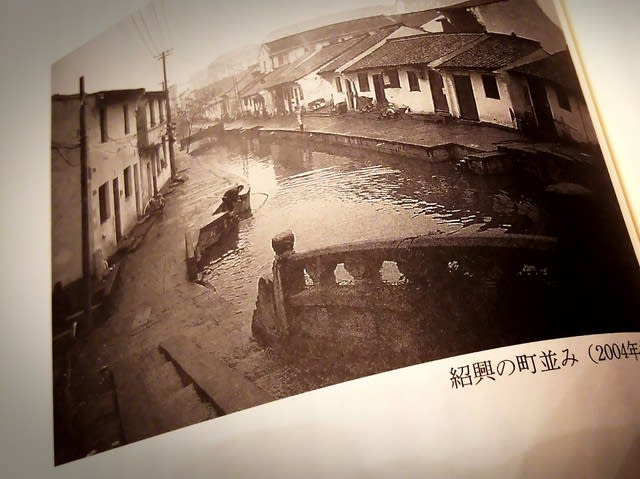司馬遼太郎
【ワイド版】
『街道をゆく 23 南蛮の道Ⅱ』★★★
http://publications.asahi.com/kaidou/23/index.shtml
続々
まだまだ熱冷めず。
---
十六世紀の無敵艦隊は、詩的には高貴としか言いようのない浪費だった。当時の艦隊一隻をつくるのに森が一つ消えるといわれた。フェイリペ二世のこの艦隊は、戦艦が百二十七隻、のせている砲は二千門といわれた。これらを建造し鋳造するだけでも巨大な自然破壊であったのに、イギリスとの戦いで、その過半――つまりは返らざる森林――を海に沈めてしまった。この一戦でスペインは世界規模の海上権をうしない、詩人のうたう「悲惨のカスティーリャ」という国土と、スペイン人の心だけがのこった。
「スペインには、宗教も芸術も文化財もある。しかしほかに何もない。いるのはスペイン人だけだ」
---
大航海時代という華麗な世界史的な演劇の幕を切っておとしたのは、いうまでもなくポルトガルであった。
---
人間が集団を組んで異常な行動に出るとき、神とか平和とか正義とかといったように、およそその行為の実態とはかけ離れた高貴なことばをかかげる。二十世紀に入って日本軍が中国を侵略したのも「平和のため」であり、ヴェトナムがカンボジアを侵略したのも「正義」のためであったということを、後世、信じられるだろうか。
---
もしスペインに一日しか滞在できないとしたら、迷わずトレドの街にゆけ、ということばがあるそうである。
---

これは架空の遊びである。もし自分がフェリペ二世のような地位に置かれたとき、どういう思想、気分、言動、さらには多民族の運命に対する――同時に世界史に対する――選択をしつづけるか、こう想像することは、人間そのものを考える上で興味がある。なぜなら、かれはどこにでもいるごく平凡な人間だからである。いまも区役所の窓口にもいるし、国鉄にもいるし、小学校の現場にもいるし、宗教団体の幹部のなかにもいる。
「フェリペ二世はあれはあれでよくやった」
と、多くのスペイン人は、わりあい甘くおもっているそうだが、このことは、死後おくり名として「慎重王」とよばれたことでも察せられる。
しかし、当時かれの支配下にあったフランス人やオランダ人たちにとって、この王の印象は残虐と不寛容であり、「南の悪魔」とさえよばれた。また、当時、世界に訴える手段をもたなかった南北アメリカの原住民にとって、生命を草のように刈りとる征服者(コンキスタドール)たちの背後にいる、死の略奪についての最高司令者でもあった。
かれは、文字どおり、世界のぬしといってよかった。ヨーロッパはそれの支配下にあり、アメリカ大陸だけでなく、アフリカと南アジアを所有していた。ちなみにフィリピンという名称も、かれの名に由来するのではないか。
その上、南アメリカから滝のように金、銀がながれこんできているのである。世界史でかれほど、その命令がゆきとどく範囲がひろかった王はなく、かれほど金銀を豊富ににぎった王もない。
さらに重要なことは、歴史のさまざまな闇の中から血まみれて登場してくる英雄的な王たちは、たとえかれの十分の一ほどの領土と富を握りえたとしても、それはみずから望み、それがために他を利用し、殺し、諸条件を生かし、機会をとらえるなど、いわば自分自身が稼ぎとったものだが、フェリペ二世の場合、すべてを父からゆずられた、ということである。かれはたまたまそういう条件のもとにうまれたにすぎず、かれが拓いた運命ではない。
その才質からいっておおぜいの中の一人にすぎず、従ってわれわれをかれにあてはめてみるという遊びには現実感がないではない。


---
記念碑では船首に、長身のエンリケ航海王子が立っている。例の修道士のような姿の大理石の彫像で、かれはカラヴェラ船の模型を右手にもち、右脚を踏み出して、遠くを望んでいるのである。その彫像は中世の教会が好んだ写実像である。
丁寧な写実表現によって愚意をふくませるというカトリック美術の伝統が、現代彫刻家によって律儀に守られているのがおもしろい。さらに王子のあとに、おなじ手法による群像がつづく。ヴァスコ・ダ・ガマもいれば、剣を杖にする者もいる。緯度側器ももつ者、ペンを持つ者、聖書や旗をかざす者、さらにはうずくまって合掌している僧服の者もいた。みな名ある人物にちがいない。

---