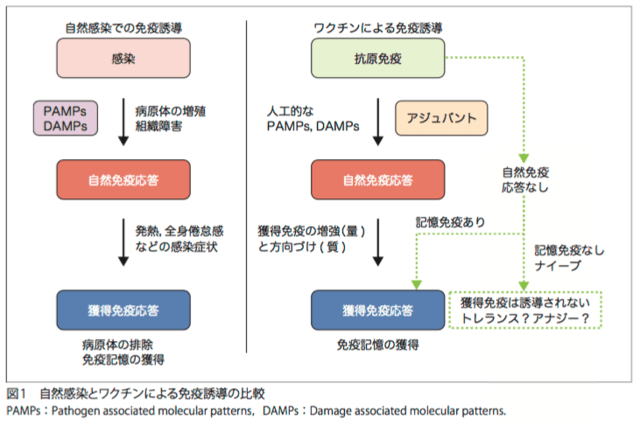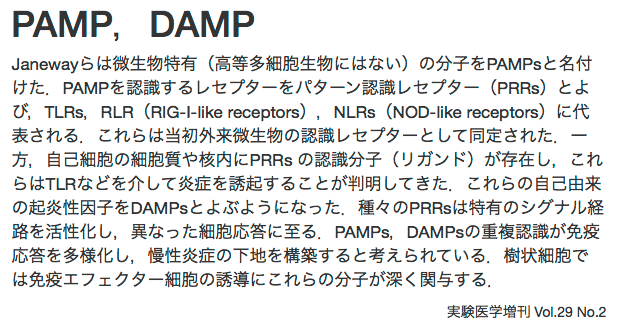日本は現在、「2020年度までに風疹を排除」することを目標にしています。
しかし2012-2013年に流行し、先天性風疹症候群(CRS)が45例発生したことは記憶に新しいところ。
それ以降、妊娠可能年齢の女性を対象に風疹抗体価検査や風疹ワクチン費用補助などをしていますが、それで十分なのでしょうか。
否!
流行の母体となっているのは、日本のワクチン行政の谷間にはまった30-50歳代の男性達です。
この世代のみ、抗体保有率が低く(78%)、集団免疫率に到達していません。
しかし社会で一番活躍する年代でもあり、仕事を休んで抗体検査をしたり自費でワクチン接種するのはハードルが高いのが現実です。
そのハードルを越えるためには、社内での集団接種および費用公費負担しかないと私は考えています。
でも厚生労働省はそのような方策をとることなく、相変わらず「2020年までに風疹排除」と謳っているだけ。
妊婦中心の対策にとどまっていては風疹排除は不可能であり、成人男性をも対象にする方針転換が今、必要なのです。
さて、風疹ワクチンに関する2013年のCDCの記事を紹介します。
生ワクチンの免疫持続期間が1回接種と2回接種で分けて記載してあるデータを初めて見ました。
表の「免疫の持続期間-2回接種」の項目は、「2回目接種後の期間」という意味です。
■ 風疹ワクチンと免疫(CDC Watch 2013年8月)

■ 先天性風疹症候群(CRS)(CDC Watch 2013年6月)
・米国において1964-1965年にかけて風疹の流行があり、約1250万件の風疹が発生し、11250件の人工妊娠中絶または自然流産があり、2100件の新生児死亡と20000件のCRS合併児が発生した。
・2004年に全米ワクチンプログラムが実施されていこう、米国においては風疹の流行は駆逐された。しかし、輸入症例は後を絶たない。
・咽頭スワブから検出された風疹ウイルスの遺伝子配列を調べると、そのウイルスの由来が判明する(紹介されている3症例はすべてアフリカ出身の母親、ウイルスもアフリカ由来のものであった)。
<参考>
□ 「2020年度までの風しん排除のために、実効ある施策を要望します」(日本産婦人科学会ほか、2017)
次に国立感染症研究所発行の病原微生物検出情報(Vol.37 No.4, 2016年4月)からの記事を抜粋。
成人男性対象の風疹対策、具体的には30-50歳代男性のワクチン接種を東京都が企業と医師会と連携して具体的に取り組み始めた事業が紹介されており、今後他地域へ広がるモデルケースになる可能性を感じました。
■ <特集>麻疹・風疹/先天性風疹症候群 2016年3月現在
・成人男性を中心とした2012-2013年の風疹流行の患者報告数は、2012年2386例、2013年14344例、2014年319例、2015年163例であった。年齢群別に見ると2012/2013年には成人がそれぞれ83.4/87.8%を占めた。


予防接種歴は接種歴不明が多く、接種歴2回の割合は少なかった。2015年を見ると、未接種22.1%、接種歴不明54.6%、1回接種18.4%、2回接種4.9%であった。

CRSは2012年4例、2013年32例、2014年9例、2015年0例であった。
・2015年に17都道府県で風疹感受性調査が行われ、風疹抗体価測定は赤血球凝集抑制法(HI法)で評価した。2歳以上30代前半まで男女ともほとんどの年齢群で90%以上の抗体保有率(抗体価≧1:8)であったが、30代後半-50代前半の年齢層の抗体保有率は男性では78%と低かった(女性では97%)。

・CRS患者では風疹ウイルスが排除されにくく、時に1年以上ウイルスを保有することがある。
<海外での風疹対策の現状>
・2012年の世界保健大会では「2015年までにWHO6地域のうち少なくとも2地域で風疹の排除を達成し、さらに2020年までには少なくとも5地域において排除を達成すること」を目標に掲げた。結果としては、アメリカ地域のみ排除を達成したものの、他の地域では目標を達成できる見込みがほとんどない。
・風疹の排除の定義:よく機能したサーベイランス制度の下で、ある地域において12ヶ月以上にわたって土着の風疹ウイルスによる伝播が認められず、その伝播に伴ったCRSの発生が認められないこと。
・2016年1月時点で接種プログラムに風疹ワクチンが導入されているのは194カ国中147カ国(75.8%)。2014年の対象年齢群における風疹ワクチン接種率は全世界で46%(2005年24%、2010年41%)とまだ不十分である。WHO地域ごとの接種率は、アフリカ10%、東地中海42%、南東アジア12%、アメリカ92%、ヨーロッパ94%、西太平洋91%と地域格差がある。
・日本の所属するWHO西太平洋地域では、これまで風疹の“制御”を目標にしてきたが、2014年に“排除”へ切り替えられ、2020年を排除目標年とすることが推奨された。
<職場で始める!感染症対応力向上プロジェクト>

・2015年10月に開始した東京都、東京商工会議所、東京都医師会が連携した企業の感染症対策を支援するプロジェクト。
A)コースⅠ 感染症理解のための従業者研修
従業者1人1人が感染症の予防、まん延防止ができるよう、自習教材を活用して必要な知識を習得する。教材は択一式問題50題と解説書で構成し、風疹に関する設問は必須問題としている。
B)コースII 事業所単位での感染症BGP(業務継続計画)の作成
職場での感染症予防、蔓延防止を目的に業務継続計画を作成することにより、企業のリスク管理と職場を感染症から守る取り組みを計画的に実施する。業務継続計画で想定する主な感染症は、身近な感染症である季節性インフルエンザ、ノロウイルス、働く世代における対応が課題となっている風疹。
C)コースⅢ 事業所単位での風疹予防対策の推進
集団免疫の理解を図り、事業所単位での従業者の風疹抗体保有率の向上を促す。東京都医師会は地域ごとに「予防接種等協力医療機関」を確保した。
・達成基準(↓)。達成基準を満たした協力企業を「達成企業」とした。2016年3月時点で協力企業は142、達成企業は9。

<2020年度の風疹排除に向けて>
・2013年の感染症発生動向調査によると、20-60歳代の男性風疹患者のうち、感染経路判明例の68.5%が職場で感染、一方の女性の感染経路は35.2%が職場、33.5%が家族となっている。
・2014年3月に国立感染症研究所が「職場における風疹対策ガイドライン」をとりまとめた。その中で「就業時間中に予防接種を受けに行くというのは労働者にとってもハードルが高い」と記載されている。その状況への対応として、厚生労働省医政局長通知「医療機関外の場所で行う健康診断の取り扱いについて」が2015年3月31日付で改正され、医療機関外の場所で行う予防接種のうち、一定の要件を満たすものについては新たに診療所開設の手続きを要しないものとされた。
・経済産業省次世代ヘルスケア産業協議会は2015年3月に東京証券取引所と共同で「健康経営銘柄」22業種22社を選定した。その調査の中で「健康診断時の麻疹・風疹などの感染症抗体検査の実施」が項目として記載されている。
<参考>「風しんに関する特定感染症予防指針」(厚生労働省、2014年3月)
<感染経路からみた妊婦の風疹罹患予防>
・2013年に報告された20-60歳女性風疹患者中感染経路判明例で最も多かったのが「夫」。妊婦の抗体価スクリーニングはされているが夫の抗体価は調べられていない。自治体によってはパートナーへも風疹ワクチン接種の補助を行っているところもあるが、抗体価が低い夫のみという自治体も多く、平日に抗体検査とワクチン接種をするに至っていないパートナーは少なくないと思われ、家族内感染を断つのは難しい。
次に多かったのが「同僚」。職場内での風疹感染に対する意識の低さも問題視されるべきであろう。
次は同じく国立感染症研究所「病原微生物検出情報」(Vol.36 No.7, 2015年7月)より;
■ <特集>風疹・先天性風疹症候群 2015年6月現在



・出生時にはCRS症状がなくても、その後難聴、白内障が顕在化する場合があるので、風疹に罹患した或いはその疑いがある母親から生まれた児の注意深い観察が必要である。
・CRS児の10-20%は生後1年を経ても風疹ウイルス(rubella virus, RV)を排泄するという報告がある。
(東京都の取り組み)
・東京都健康安全研究センターが2013-2015年に都内で発生したCRS児12例(東京都で発生した総数は、2013年13例、2014年3例の合計16例)の調査を行った結果、RV排泄状況は以下の通りであった:
生後3ヶ月時点:91.7%(12例中11例)、生後6ヶ月:33.3%(4/12例)、生後9ヶ月:16.7%(2/12例)、生後12ヶ月:8.3%(1/12例)。最長は13ヶ月。
(大阪での取り組み)
・CRS発症予防では妊婦対策が中心であったが、風疹排除を目的とするならば妊婦以外にも目を向ける必要がある。
・とにかく成人男性が問題:風疹感染は一般的に症状が軽いため見落とされやすく、20-40代の男性では両要求かを取得せずに仕事を続ける場合も多く、結果的に職場内で感染が拡大する傾向がある。男性の未婚率は30代で40%、40代で25%であり、現在行っている風疹抗体検査およびワクチン助成の対象者とならない男性の割合が高い。
<産婦人科医から見た2012-2013年の風疹流行の課題>
・過去の風疹予防接種施策の問題:定期接種の機会がなかった、あるいは移行措置で施策がなされたにもかかわらず結果的に低接種率に帰した年代と、風疹患者数の多い年齢とが見事に一致している(↓)

・接種率向上を図るポイント:
1.接種無償化(定期接種)
2.個別通知
3.接種確認と未接種者への繰り返し通知
4.休日や職場での接種機会の提供
5.接種率の低い都道府県の公表
・CRS45例の公開情報「先天性風しん症候群(CRS)の報告(2014年10月8日現在)」
ワクチン接種歴あり:9例、妊娠中風疹罹患なし:4例、双方の相当:2例が存在する。
(例1)妊娠中に発疹と発熱を認め医療機関を受診したが、風疹の診断に至らず、出生した児がCRSだった。
(例2)第1指分娩後に風疹ワクチンを受けたが今回HI8倍、妊娠中風疹症状なし、出生した児がCRSだった。
結局、妊娠早期にはっきり風疹と診断された例以外にCRSは予測できない。風疹の排除こそが唯一の解決方法である。
<先天性風疹症候群(CRS)の子にみられる難聴>
・CRSのほとんどの臨床症状は妊娠8週までに罹患した場合に出現する症状であり、それ以降での罹患では出現率は低下する。しかし、難聴は8週以降の感染でも発症する頻度が高く、CRSの80-90%に認められる。
・CRS児の50%は出生直後に何も臨床症状がない。
・補聴器使用開始は生後半年以内が理想的であるが、CRS児の開始年齢は遅くなる傾向がある。ウイルス排泄による二次感染が懸念されるため、地域の母湯院や訪問看護の受け入れが悪いことも一因である。
・CRS難聴の特徴:
ウイルスの血管障害による基底膜、血管条と球形嚢の変性、その他あぶみ骨の固着などが報告されており、伝音難聴/感音難聴のどちらも生じる。
聴力レベルも軽度から重度まで、左右聴力レベルも非対称で一側性難聴のこともある。
出生直後の聴力が正常であったとしても、2-3歳までに遅発性難聴を生じるため、たとえ新生児聴覚スクリーニングで正常判定でも、3歳までは3-6ヶ月ごとの聴力評価が必要である。
・療育の問題点:
ウイルス排泄がとまるまで集団の中に入れることができないため、地域の聾学校や療育施設での指導・介入ができず、医療機関でさえも受診抑制せざるを得ない。
・潜在的CRSの可能性:
重度難聴児の眼底検査を行ったところ、CRSに特徴的な眼底所見を有する児が既報告以上に認められ、さらに風疹流行時期・地域に一致していた(Tamayo ML, et al., Int J Pediatr Otorhinolaryngol 77: 1536-1540, 2013)。出生時期に何も症状がなければCRSであることがわからず、原因不明の難聴児として対応されている可能性がある。
<職場における風疹対策>
・2012年度の感染症流行予測調査によると、風疹に対する免疫を持たない20-49歳の成人は475万人で、そのうち男性が397万人と8割以上を占めている。
・風疹感染の最大の懸念はCRSの発生であり、従業員直接の危険ではないため、感染リスクの高い20-50代男性で当事者意識を持つものは限られる。
・予防接種歴の調査は難しく、母子手帳の記載を確認できるのは20-40代の成人のうち36%にとどまる(Hori A, et al., PLOS ONE 10: 0129900, 2015)。
・風疹罹患者のウイルス排出期間、つまり他人へ感染させ得る期間は、発疹などの症状出現の前後1週間とされる。症状が出たら自宅待機という対策では不十分である。感染に気づかない男性が、職場や家庭、地域で妊娠出産年齢の女性へ感染させるケースが最も危惧される。
・企業の安全配慮義務に対して、従業員には自分の健康を自己管理する事故保険義務がある。
しかし2012-2013年に流行し、先天性風疹症候群(CRS)が45例発生したことは記憶に新しいところ。
それ以降、妊娠可能年齢の女性を対象に風疹抗体価検査や風疹ワクチン費用補助などをしていますが、それで十分なのでしょうか。
否!
流行の母体となっているのは、日本のワクチン行政の谷間にはまった30-50歳代の男性達です。
この世代のみ、抗体保有率が低く(78%)、集団免疫率に到達していません。
しかし社会で一番活躍する年代でもあり、仕事を休んで抗体検査をしたり自費でワクチン接種するのはハードルが高いのが現実です。
そのハードルを越えるためには、社内での集団接種および費用公費負担しかないと私は考えています。
でも厚生労働省はそのような方策をとることなく、相変わらず「2020年までに風疹排除」と謳っているだけ。
妊婦中心の対策にとどまっていては風疹排除は不可能であり、成人男性をも対象にする方針転換が今、必要なのです。
さて、風疹ワクチンに関する2013年のCDCの記事を紹介します。
生ワクチンの免疫持続期間が1回接種と2回接種で分けて記載してあるデータを初めて見ました。
表の「免疫の持続期間-2回接種」の項目は、「2回目接種後の期間」という意味です。
■ 風疹ワクチンと免疫(CDC Watch 2013年8月)

■ 先天性風疹症候群(CRS)(CDC Watch 2013年6月)
・米国において1964-1965年にかけて風疹の流行があり、約1250万件の風疹が発生し、11250件の人工妊娠中絶または自然流産があり、2100件の新生児死亡と20000件のCRS合併児が発生した。
・2004年に全米ワクチンプログラムが実施されていこう、米国においては風疹の流行は駆逐された。しかし、輸入症例は後を絶たない。
・咽頭スワブから検出された風疹ウイルスの遺伝子配列を調べると、そのウイルスの由来が判明する(紹介されている3症例はすべてアフリカ出身の母親、ウイルスもアフリカ由来のものであった)。
<参考>
□ 「2020年度までの風しん排除のために、実効ある施策を要望します」(日本産婦人科学会ほか、2017)
次に国立感染症研究所発行の病原微生物検出情報(Vol.37 No.4, 2016年4月)からの記事を抜粋。
成人男性対象の風疹対策、具体的には30-50歳代男性のワクチン接種を東京都が企業と医師会と連携して具体的に取り組み始めた事業が紹介されており、今後他地域へ広がるモデルケースになる可能性を感じました。
■ <特集>麻疹・風疹/先天性風疹症候群 2016年3月現在
・成人男性を中心とした2012-2013年の風疹流行の患者報告数は、2012年2386例、2013年14344例、2014年319例、2015年163例であった。年齢群別に見ると2012/2013年には成人がそれぞれ83.4/87.8%を占めた。


予防接種歴は接種歴不明が多く、接種歴2回の割合は少なかった。2015年を見ると、未接種22.1%、接種歴不明54.6%、1回接種18.4%、2回接種4.9%であった。

CRSは2012年4例、2013年32例、2014年9例、2015年0例であった。
・2015年に17都道府県で風疹感受性調査が行われ、風疹抗体価測定は赤血球凝集抑制法(HI法)で評価した。2歳以上30代前半まで男女ともほとんどの年齢群で90%以上の抗体保有率(抗体価≧1:8)であったが、30代後半-50代前半の年齢層の抗体保有率は男性では78%と低かった(女性では97%)。

・CRS患者では風疹ウイルスが排除されにくく、時に1年以上ウイルスを保有することがある。
<海外での風疹対策の現状>
・2012年の世界保健大会では「2015年までにWHO6地域のうち少なくとも2地域で風疹の排除を達成し、さらに2020年までには少なくとも5地域において排除を達成すること」を目標に掲げた。結果としては、アメリカ地域のみ排除を達成したものの、他の地域では目標を達成できる見込みがほとんどない。
・風疹の排除の定義:よく機能したサーベイランス制度の下で、ある地域において12ヶ月以上にわたって土着の風疹ウイルスによる伝播が認められず、その伝播に伴ったCRSの発生が認められないこと。
・2016年1月時点で接種プログラムに風疹ワクチンが導入されているのは194カ国中147カ国(75.8%)。2014年の対象年齢群における風疹ワクチン接種率は全世界で46%(2005年24%、2010年41%)とまだ不十分である。WHO地域ごとの接種率は、アフリカ10%、東地中海42%、南東アジア12%、アメリカ92%、ヨーロッパ94%、西太平洋91%と地域格差がある。
・日本の所属するWHO西太平洋地域では、これまで風疹の“制御”を目標にしてきたが、2014年に“排除”へ切り替えられ、2020年を排除目標年とすることが推奨された。
<職場で始める!感染症対応力向上プロジェクト>

・2015年10月に開始した東京都、東京商工会議所、東京都医師会が連携した企業の感染症対策を支援するプロジェクト。
A)コースⅠ 感染症理解のための従業者研修
従業者1人1人が感染症の予防、まん延防止ができるよう、自習教材を活用して必要な知識を習得する。教材は択一式問題50題と解説書で構成し、風疹に関する設問は必須問題としている。
B)コースII 事業所単位での感染症BGP(業務継続計画)の作成
職場での感染症予防、蔓延防止を目的に業務継続計画を作成することにより、企業のリスク管理と職場を感染症から守る取り組みを計画的に実施する。業務継続計画で想定する主な感染症は、身近な感染症である季節性インフルエンザ、ノロウイルス、働く世代における対応が課題となっている風疹。
C)コースⅢ 事業所単位での風疹予防対策の推進
集団免疫の理解を図り、事業所単位での従業者の風疹抗体保有率の向上を促す。東京都医師会は地域ごとに「予防接種等協力医療機関」を確保した。
・達成基準(↓)。達成基準を満たした協力企業を「達成企業」とした。2016年3月時点で協力企業は142、達成企業は9。

<2020年度の風疹排除に向けて>
・2013年の感染症発生動向調査によると、20-60歳代の男性風疹患者のうち、感染経路判明例の68.5%が職場で感染、一方の女性の感染経路は35.2%が職場、33.5%が家族となっている。
・2014年3月に国立感染症研究所が「職場における風疹対策ガイドライン」をとりまとめた。その中で「就業時間中に予防接種を受けに行くというのは労働者にとってもハードルが高い」と記載されている。その状況への対応として、厚生労働省医政局長通知「医療機関外の場所で行う健康診断の取り扱いについて」が2015年3月31日付で改正され、医療機関外の場所で行う予防接種のうち、一定の要件を満たすものについては新たに診療所開設の手続きを要しないものとされた。
・経済産業省次世代ヘルスケア産業協議会は2015年3月に東京証券取引所と共同で「健康経営銘柄」22業種22社を選定した。その調査の中で「健康診断時の麻疹・風疹などの感染症抗体検査の実施」が項目として記載されている。
<参考>「風しんに関する特定感染症予防指針」(厚生労働省、2014年3月)
<感染経路からみた妊婦の風疹罹患予防>
・2013年に報告された20-60歳女性風疹患者中感染経路判明例で最も多かったのが「夫」。妊婦の抗体価スクリーニングはされているが夫の抗体価は調べられていない。自治体によってはパートナーへも風疹ワクチン接種の補助を行っているところもあるが、抗体価が低い夫のみという自治体も多く、平日に抗体検査とワクチン接種をするに至っていないパートナーは少なくないと思われ、家族内感染を断つのは難しい。
次に多かったのが「同僚」。職場内での風疹感染に対する意識の低さも問題視されるべきであろう。
次は同じく国立感染症研究所「病原微生物検出情報」(Vol.36 No.7, 2015年7月)より;
■ <特集>風疹・先天性風疹症候群 2015年6月現在



・出生時にはCRS症状がなくても、その後難聴、白内障が顕在化する場合があるので、風疹に罹患した或いはその疑いがある母親から生まれた児の注意深い観察が必要である。
・CRS児の10-20%は生後1年を経ても風疹ウイルス(rubella virus, RV)を排泄するという報告がある。
(東京都の取り組み)
・東京都健康安全研究センターが2013-2015年に都内で発生したCRS児12例(東京都で発生した総数は、2013年13例、2014年3例の合計16例)の調査を行った結果、RV排泄状況は以下の通りであった:
生後3ヶ月時点:91.7%(12例中11例)、生後6ヶ月:33.3%(4/12例)、生後9ヶ月:16.7%(2/12例)、生後12ヶ月:8.3%(1/12例)。最長は13ヶ月。
(大阪での取り組み)
・CRS発症予防では妊婦対策が中心であったが、風疹排除を目的とするならば妊婦以外にも目を向ける必要がある。
・とにかく成人男性が問題:風疹感染は一般的に症状が軽いため見落とされやすく、20-40代の男性では両要求かを取得せずに仕事を続ける場合も多く、結果的に職場内で感染が拡大する傾向がある。男性の未婚率は30代で40%、40代で25%であり、現在行っている風疹抗体検査およびワクチン助成の対象者とならない男性の割合が高い。
<産婦人科医から見た2012-2013年の風疹流行の課題>
・過去の風疹予防接種施策の問題:定期接種の機会がなかった、あるいは移行措置で施策がなされたにもかかわらず結果的に低接種率に帰した年代と、風疹患者数の多い年齢とが見事に一致している(↓)

・接種率向上を図るポイント:
1.接種無償化(定期接種)
2.個別通知
3.接種確認と未接種者への繰り返し通知
4.休日や職場での接種機会の提供
5.接種率の低い都道府県の公表
・CRS45例の公開情報「先天性風しん症候群(CRS)の報告(2014年10月8日現在)」
ワクチン接種歴あり:9例、妊娠中風疹罹患なし:4例、双方の相当:2例が存在する。
(例1)妊娠中に発疹と発熱を認め医療機関を受診したが、風疹の診断に至らず、出生した児がCRSだった。
(例2)第1指分娩後に風疹ワクチンを受けたが今回HI8倍、妊娠中風疹症状なし、出生した児がCRSだった。
結局、妊娠早期にはっきり風疹と診断された例以外にCRSは予測できない。風疹の排除こそが唯一の解決方法である。
<先天性風疹症候群(CRS)の子にみられる難聴>
・CRSのほとんどの臨床症状は妊娠8週までに罹患した場合に出現する症状であり、それ以降での罹患では出現率は低下する。しかし、難聴は8週以降の感染でも発症する頻度が高く、CRSの80-90%に認められる。
・CRS児の50%は出生直後に何も臨床症状がない。
・補聴器使用開始は生後半年以内が理想的であるが、CRS児の開始年齢は遅くなる傾向がある。ウイルス排泄による二次感染が懸念されるため、地域の母湯院や訪問看護の受け入れが悪いことも一因である。
・CRS難聴の特徴:
ウイルスの血管障害による基底膜、血管条と球形嚢の変性、その他あぶみ骨の固着などが報告されており、伝音難聴/感音難聴のどちらも生じる。
聴力レベルも軽度から重度まで、左右聴力レベルも非対称で一側性難聴のこともある。
出生直後の聴力が正常であったとしても、2-3歳までに遅発性難聴を生じるため、たとえ新生児聴覚スクリーニングで正常判定でも、3歳までは3-6ヶ月ごとの聴力評価が必要である。
・療育の問題点:
ウイルス排泄がとまるまで集団の中に入れることができないため、地域の聾学校や療育施設での指導・介入ができず、医療機関でさえも受診抑制せざるを得ない。
・潜在的CRSの可能性:
重度難聴児の眼底検査を行ったところ、CRSに特徴的な眼底所見を有する児が既報告以上に認められ、さらに風疹流行時期・地域に一致していた(Tamayo ML, et al., Int J Pediatr Otorhinolaryngol 77: 1536-1540, 2013)。出生時期に何も症状がなければCRSであることがわからず、原因不明の難聴児として対応されている可能性がある。
<職場における風疹対策>
・2012年度の感染症流行予測調査によると、風疹に対する免疫を持たない20-49歳の成人は475万人で、そのうち男性が397万人と8割以上を占めている。
・風疹感染の最大の懸念はCRSの発生であり、従業員直接の危険ではないため、感染リスクの高い20-50代男性で当事者意識を持つものは限られる。
・予防接種歴の調査は難しく、母子手帳の記載を確認できるのは20-40代の成人のうち36%にとどまる(Hori A, et al., PLOS ONE 10: 0129900, 2015)。
・風疹罹患者のウイルス排出期間、つまり他人へ感染させ得る期間は、発疹などの症状出現の前後1週間とされる。症状が出たら自宅待機という対策では不十分である。感染に気づかない男性が、職場や家庭、地域で妊娠出産年齢の女性へ感染させるケースが最も危惧される。
・企業の安全配慮義務に対して、従業員には自分の健康を自己管理する事故保険義務がある。