先週の金曜日の朝 またも 親戚が 亡くなりました。
今度は 東京在住。
鹿児島のおばば達は あわてて上京の準備です。
ところが、航空券を買ってから 葬儀の段取りがわかりびっくりしています。
お通夜は 亡くなって五日目の夜、告別式は六日目となっていたからです。
理由は 火葬場が混んでいるからです。
昨年の今頃 友人の弟さんが亡くなった時も 横浜で同じぐらい待たされました。
福岡の場合、木曜日の夜に亡くなり、金曜日は本通夜で 土曜日が告別式でした。
友引にぶつからない場合は 大体 このような流れになるのが一般的なのではないでしょうか。
救急車で搬送されようにも 治療してもらえる病院がなかなか見つからなかったり、
亡くなってもすぐに葬式を出せないなどは 残念ながら首都圏の負の部分です。
一昨日 夜のお通夜のころの雷雨 は 送る側 旅立つ側の涙雨のような気がしました。
は 送る側 旅立つ側の涙雨のような気がしました。
昨日の告別式までは 亡くなってから日にちも経過していることもあり、故人に縁のあった人への周知も滞りなく
たくさんの方にお別れをしていただいたことは たいへんありがたいことでした。
今度は 東京在住。
鹿児島のおばば達は あわてて上京の準備です。
ところが、航空券を買ってから 葬儀の段取りがわかりびっくりしています。
お通夜は 亡くなって五日目の夜、告別式は六日目となっていたからです。
理由は 火葬場が混んでいるからです。
昨年の今頃 友人の弟さんが亡くなった時も 横浜で同じぐらい待たされました。
福岡の場合、木曜日の夜に亡くなり、金曜日は本通夜で 土曜日が告別式でした。
友引にぶつからない場合は 大体 このような流れになるのが一般的なのではないでしょうか。
救急車で搬送されようにも 治療してもらえる病院がなかなか見つからなかったり、
亡くなってもすぐに葬式を出せないなどは 残念ながら首都圏の負の部分です。
一昨日 夜のお通夜のころの雷雨
 は 送る側 旅立つ側の涙雨のような気がしました。
は 送る側 旅立つ側の涙雨のような気がしました。昨日の告別式までは 亡くなってから日にちも経過していることもあり、故人に縁のあった人への周知も滞りなく
たくさんの方にお別れをしていただいたことは たいへんありがたいことでした。














 と心配する家族がいたり、
と心配する家族がいたり、
 。
。

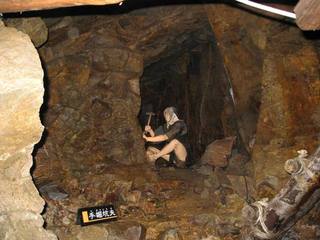


 。
。



 」
」 。 彼が出演した映画 ほとんど観てます。
。 彼が出演した映画 ほとんど観てます。 映画です。
映画です。 。
。 」と 一言。
」と 一言。 』と 私の腹の中。
』と 私の腹の中。
 」と言っても そんなことはないとか。うーん 変わっている
」と言っても そんなことはないとか。うーん 変わっている

 空輸で翌日届きます。 新鮮!
空輸で翌日届きます。 新鮮! )
)






