和裁のお稽古を始めて3か月目に入った頃、浴衣も仕立て上がると、
先生に
「袷を縫ってみますか?」 と 尋ねられました。
私は、待ってましたとばかり、
「はい、縫ってみたいと思います。お願いします。」 と 即答。
先生は、
「材料はありますか?」 と 聞かれました。
「気に入った反物を見かけて 買ったものが いくつか 紬であります。
亡くなった母が仕立てずにいた反物も 古いですけど あります」と言いますと、
「次回 持っていらっしゃい」 とのことで、いよいよ、私の本格的和裁のお稽古がスタートしました。
初めて縫った袷は 二十年近く前に 横浜の高島屋の初商いで求めた 古紅花紬という モノトーンの横段のものです。
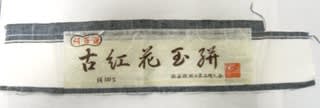
和裁のお稽古を始めるようになって、すぐに 呉服屋さんに 湯通しをお願いしてありました。
しかし、八掛け(裾まわし布)の色合わせが 心配です。
「八掛けの色合わせの相談をしたいのですが」 と お願いしますと、
「それでは お稽古の前に 反物を持っていらっしゃいな」 とおっしゃってくださいました。

私は、相談する前は、薄いグレイか 反物のなかにちょっとある山吹色ぐらいが いいかな?と思っていたのですが、
先生は、なんと、「黒が粋でいいでしょう。 ほかの色だと ありふれてつまらないですね」 とのアドバイス。
そこで、黒と決めて、呉服屋さんで 求めました。
お安くしますよとの言葉を添えて、両駒の紬用八掛けが8400円だったと思います。
胴裏は、反物と同じように、以前 デパートで買い求めていたものを使うことに。
材料が そろい お稽古出来るようになったのですが、
皆と同じように、一年に一枚仕立て上がるかどうかの 悠長なおけいこはしたくないな という思いがありました。
なんとかして 早く覚えたいと考えていたのです。
一つには、先生が 高齢であるということがありましたし、一年に一枚程度の仕上がりだと、
お稽古の費用で 数枚の仕立てを頼めてしまうので ちょっと割に合わないものになると 思いました。
トトに和裁のお稽古に行こうと思うと話したのは 年の初めのこと。
「月々の生活費の中から、出費出来るんだったら やったら」という答えでした。
もちろん、私も 当時は 子供の教育費のピーク時(長男 私立大学二年目 長女 私立高校)でしたから、
自分のお稽古の費用を トトに出してもらうつもりはさらさらなかったのですが…。
自分のお金で 着物を仕立てるのは 二十数年ぶりのこと。
母がまだ 生きていた頃、色留め袖を染めてもらって以来でした。
その時、柄や色を選んで、手描きにしてもらうか、型染にするか、悩んでやっと決断し、やれやれと思ったら、
次に湯のし代だの 胴裏の費用だのと加算されるのを 初めて知ったのがその時で
着物って お金がかかるんだと思ったものです。
今回 初めて自分で袷を仕立てることになり、表地のほかに 湯通し代や 八掛けの分と あっという間に 五割増。
早く 袷の仕立て方を覚えたい、上手に仕立てられるようになりたいとの思いから、
二枚の反物を 同時に 仕立てよう と思い立ちました。
そこで、先生に
「お教室で習ったことを、家で復習するために もう一反の着物を同時に仕立てたいと思います。
裁ち方や 家でやったところを その次のお稽古の時に 見ていただけないでしょうか? 」 と 恐るおそる聞いてみました。
すると、「いいですよ」 と 意外に簡単に私のわがままを引き受けてくださったのです。
こうして 私の 袷の仕立てのお稽古がスタートしました。
今から、五年と半年前のことです。
先生に
「袷を縫ってみますか?」 と 尋ねられました。
私は、待ってましたとばかり、
「はい、縫ってみたいと思います。お願いします。」 と 即答。
先生は、
「材料はありますか?」 と 聞かれました。
「気に入った反物を見かけて 買ったものが いくつか 紬であります。
亡くなった母が仕立てずにいた反物も 古いですけど あります」と言いますと、
「次回 持っていらっしゃい」 とのことで、いよいよ、私の本格的和裁のお稽古がスタートしました。
初めて縫った袷は 二十年近く前に 横浜の高島屋の初商いで求めた 古紅花紬という モノトーンの横段のものです。
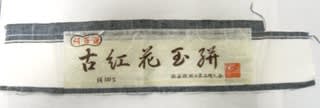
和裁のお稽古を始めるようになって、すぐに 呉服屋さんに 湯通しをお願いしてありました。
しかし、八掛け(裾まわし布)の色合わせが 心配です。
「八掛けの色合わせの相談をしたいのですが」 と お願いしますと、
「それでは お稽古の前に 反物を持っていらっしゃいな」 とおっしゃってくださいました。

私は、相談する前は、薄いグレイか 反物のなかにちょっとある山吹色ぐらいが いいかな?と思っていたのですが、
先生は、なんと、「黒が粋でいいでしょう。 ほかの色だと ありふれてつまらないですね」 とのアドバイス。
そこで、黒と決めて、呉服屋さんで 求めました。
お安くしますよとの言葉を添えて、両駒の紬用八掛けが8400円だったと思います。
胴裏は、反物と同じように、以前 デパートで買い求めていたものを使うことに。
材料が そろい お稽古出来るようになったのですが、
皆と同じように、一年に一枚仕立て上がるかどうかの 悠長なおけいこはしたくないな という思いがありました。
なんとかして 早く覚えたいと考えていたのです。
一つには、先生が 高齢であるということがありましたし、一年に一枚程度の仕上がりだと、
お稽古の費用で 数枚の仕立てを頼めてしまうので ちょっと割に合わないものになると 思いました。
トトに和裁のお稽古に行こうと思うと話したのは 年の初めのこと。
「月々の生活費の中から、出費出来るんだったら やったら」という答えでした。
もちろん、私も 当時は 子供の教育費のピーク時(長男 私立大学二年目 長女 私立高校)でしたから、
自分のお稽古の費用を トトに出してもらうつもりはさらさらなかったのですが…。
自分のお金で 着物を仕立てるのは 二十数年ぶりのこと。
母がまだ 生きていた頃、色留め袖を染めてもらって以来でした。
その時、柄や色を選んで、手描きにしてもらうか、型染にするか、悩んでやっと決断し、やれやれと思ったら、
次に湯のし代だの 胴裏の費用だのと加算されるのを 初めて知ったのがその時で
着物って お金がかかるんだと思ったものです。
今回 初めて自分で袷を仕立てることになり、表地のほかに 湯通し代や 八掛けの分と あっという間に 五割増。
早く 袷の仕立て方を覚えたい、上手に仕立てられるようになりたいとの思いから、
二枚の反物を 同時に 仕立てよう と思い立ちました。
そこで、先生に
「お教室で習ったことを、家で復習するために もう一反の着物を同時に仕立てたいと思います。
裁ち方や 家でやったところを その次のお稽古の時に 見ていただけないでしょうか? 」 と 恐るおそる聞いてみました。
すると、「いいですよ」 と 意外に簡単に私のわがままを引き受けてくださったのです。
こうして 私の 袷の仕立てのお稽古がスタートしました。
今から、五年と半年前のことです。














 )本を手にしていました。
)本を手にしていました。
 」 と言い放ってしまった
」 と言い放ってしまった

 。
。






 がプリントしてある生地で もう一枚 裁断しようとしていましたが、
がプリントしてある生地で もう一枚 裁断しようとしていましたが、














