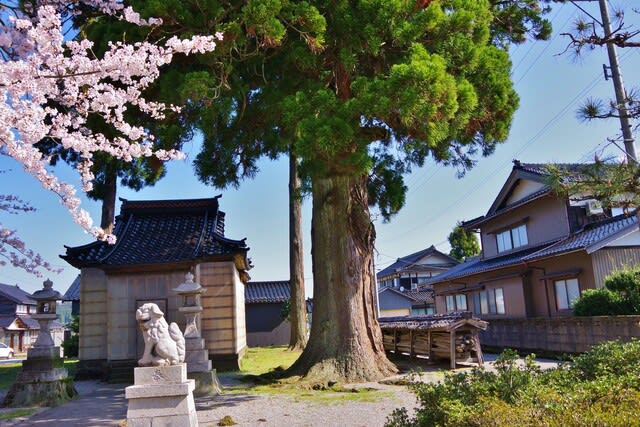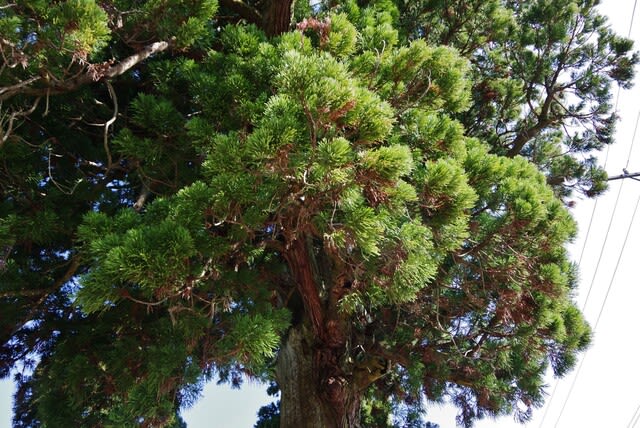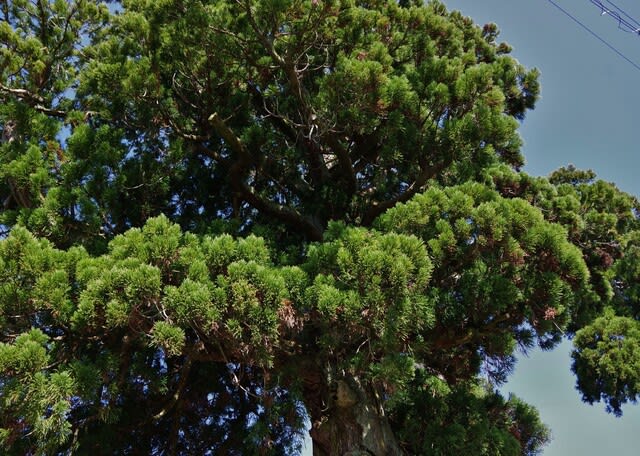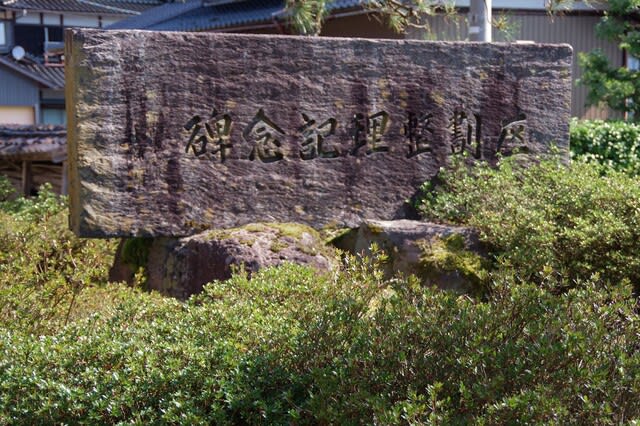砂子谷地区は、南砺市役所の北西約8kmのところ、石川県境に近い地区です
南砺市役所東側の国道304号線を北へ、約200mの「福光駅前」信号を左(西北西)へ
まだ国道304号線で小矢部川を渡ります、小矢部川沿いの千本桜は満開を迎えていました
約1.5kmで「道の駅福光 なんといっぷく茶屋」前を過ぎ、山間へ入って行きます
道成に約2.3kmで新蔵原トンネルに入ります
新蔵原トンネルを貫け約4kmで左手に「蓮如上人旧跡・土山御坊跡⇐」の案内板に従って鋭角に左(南東)へ
約300m坂道を緩く下った所を斜め左(南東)へ

間も無く道路左手に鳥居が見えて来ます
前の道路脇に 車を止めさせて頂きました
車を止めさせて頂きました


境内入口参道は南西向きです

富士社社號標です

東側には「巨木 推定樹齢千弍百余年 孫下稀有の老杉あり」の石碑が建っています

境内西端に大きな樹冠が見えています

石段を上がりましょう
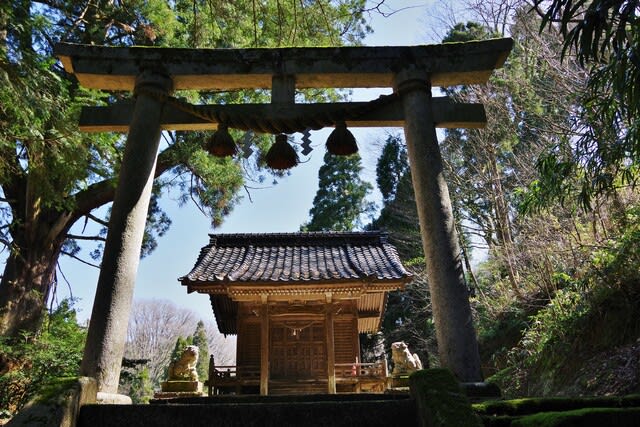
石段上にはニノ鳥居です
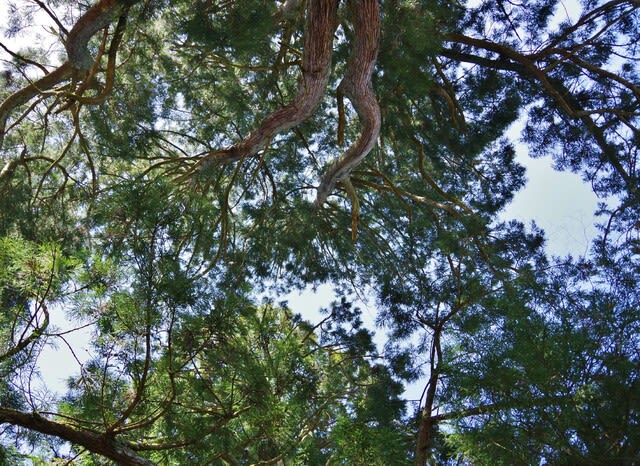
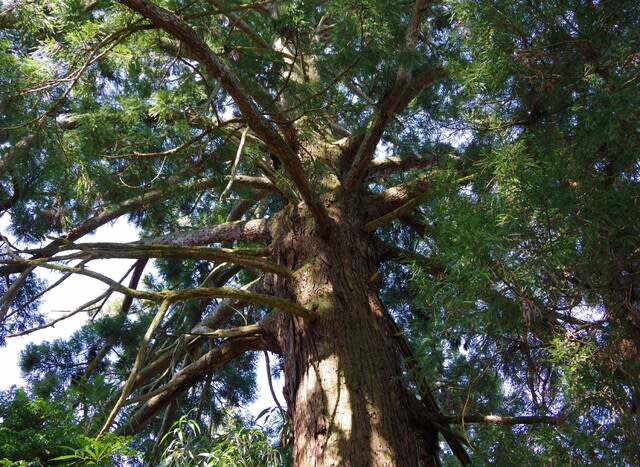

境内南西端のスギの大木です、下の鳥居前から見えた樹冠は、このスギのものですね

拝殿です


本殿覆い屋です
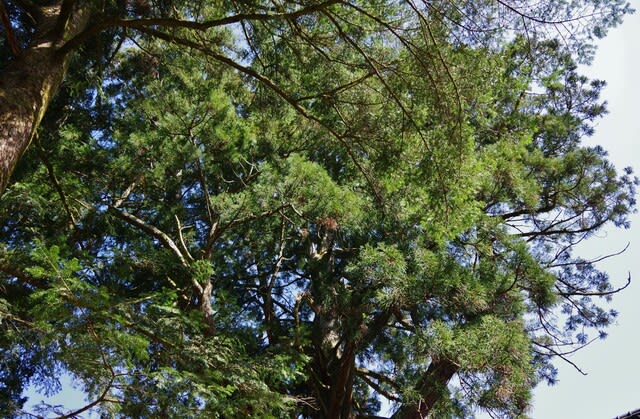

社殿西側に目的の「砂子谷の大杉」です
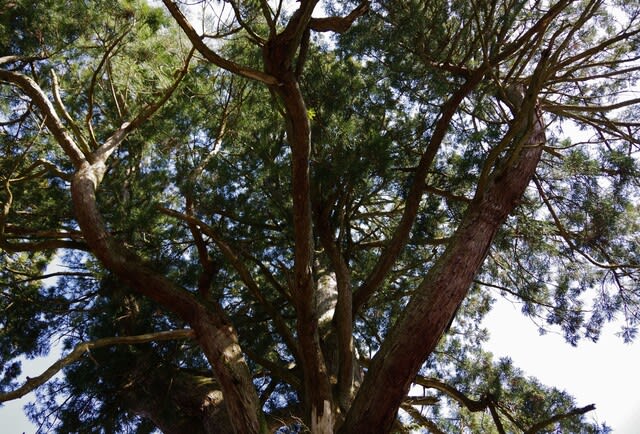


東側から
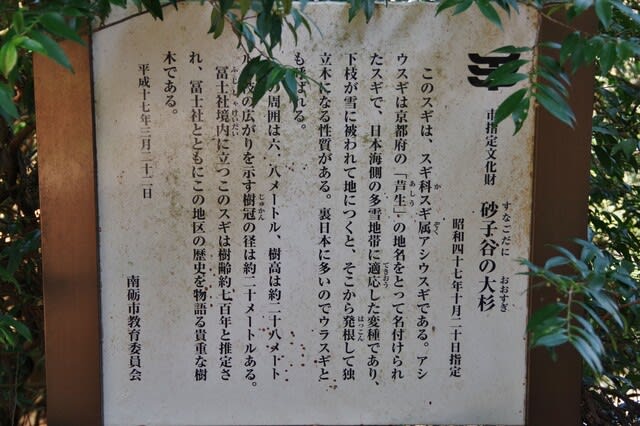
説明版です
市指定文化財 砂子谷の大杉
昭和47年10月20日指定
このスギは、スギ科スギ属アシウスギである。
アシウスギは京都府の「芦生」の地名をとって名付けられたスギで、日本海側の多雪地帯に適応した変種であり、下枝が雪に被われ地につくと、そこから発根して独立木になる性質がある。
裏日本に多いのでウラスギとも呼ばれる。
幹の周囲は6.8m、樹高は約28m、枝の広がりを示す樹冠の径は約20mある。
冨士社境内に立つこのスギは樹齢約700年と推定され、冨士社とともにこの地区の歴史を物語る貴重な樹木である。
平成17年3月22日
南砺市教育委員会
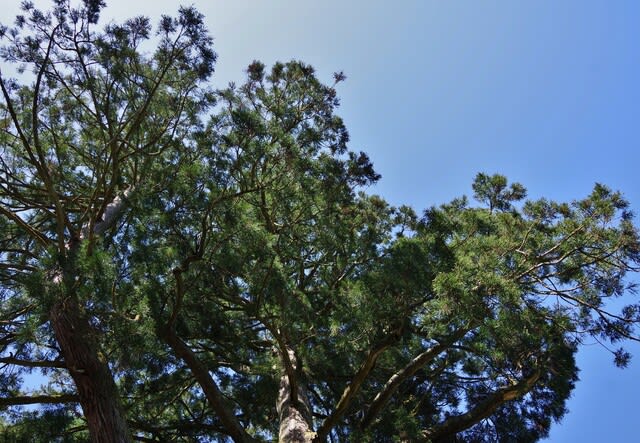


北東側から
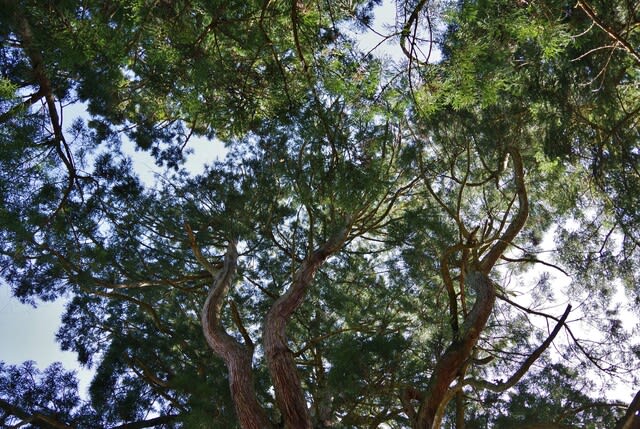


南東側から

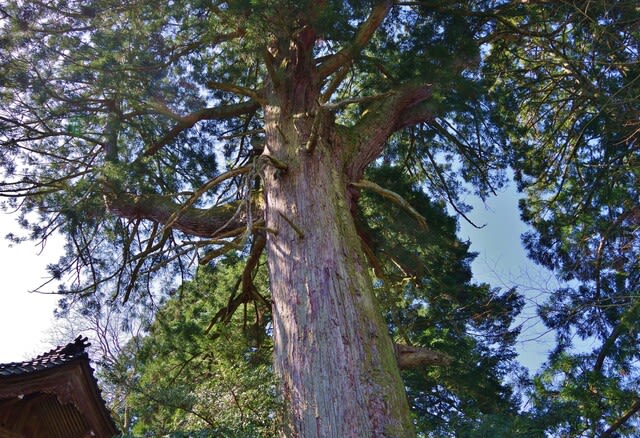

北側から

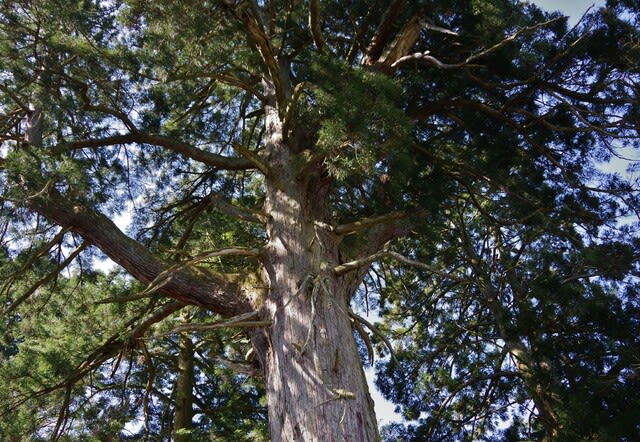

北側道路から
では、次へ行きましょう

南砺市役所東側の国道304号線を北へ、約200mの「福光駅前」信号を左(西北西)へ
まだ国道304号線で小矢部川を渡ります、小矢部川沿いの千本桜は満開を迎えていました
約1.5kmで「道の駅福光 なんといっぷく茶屋」前を過ぎ、山間へ入って行きます
道成に約2.3kmで新蔵原トンネルに入ります
新蔵原トンネルを貫け約4kmで左手に「蓮如上人旧跡・土山御坊跡⇐」の案内板に従って鋭角に左(南東)へ
約300m坂道を緩く下った所を斜め左(南東)へ

間も無く道路左手に鳥居が見えて来ます

前の道路脇に
 車を止めさせて頂きました
車を止めさせて頂きました

境内入口参道は南西向きです


富士社社號標です


東側には「巨木 推定樹齢千弍百余年 孫下稀有の老杉あり」の石碑が建っています


境内西端に大きな樹冠が見えています


石段を上がりましょう

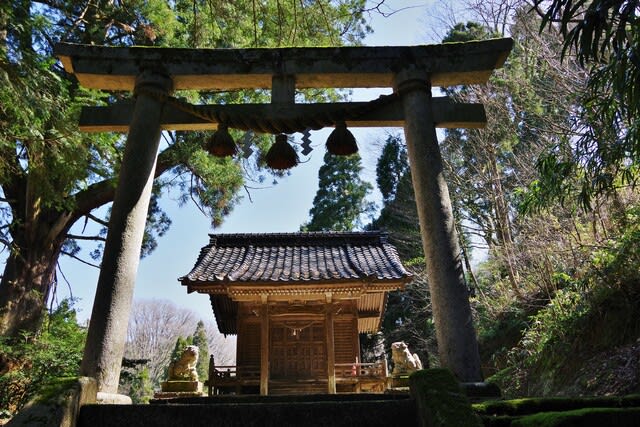
石段上にはニノ鳥居です

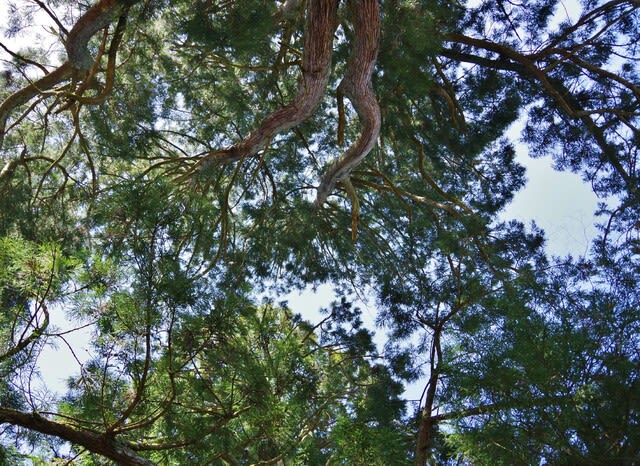
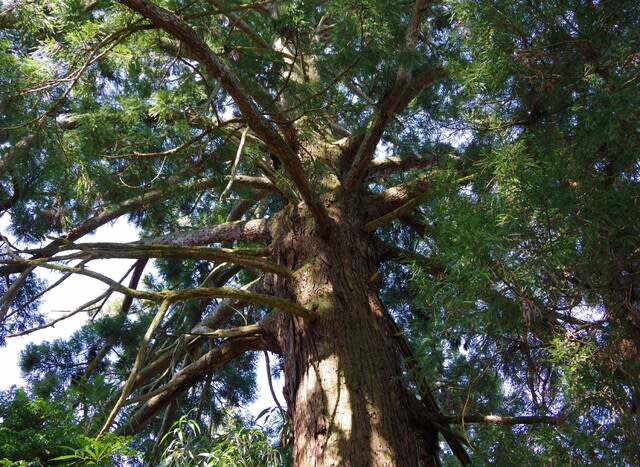

境内南西端のスギの大木です、下の鳥居前から見えた樹冠は、このスギのものですね


拝殿です



本殿覆い屋です

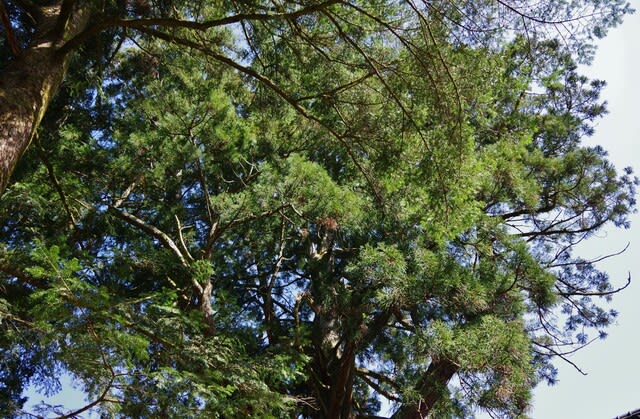

社殿西側に目的の「砂子谷の大杉」です

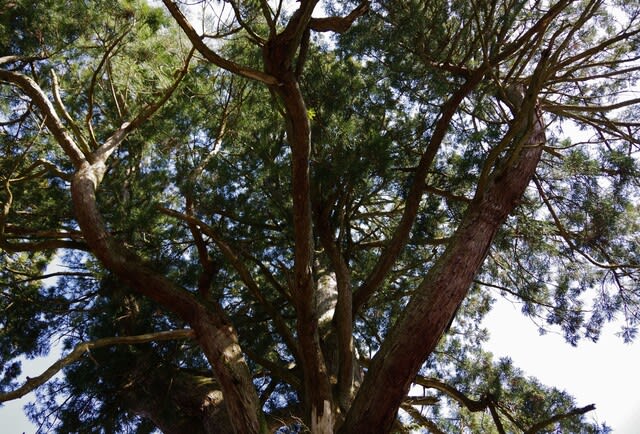


東側から

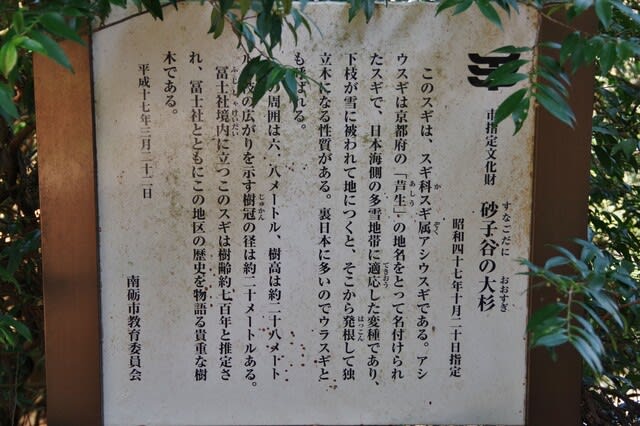
説明版です
市指定文化財 砂子谷の大杉
昭和47年10月20日指定
このスギは、スギ科スギ属アシウスギである。
アシウスギは京都府の「芦生」の地名をとって名付けられたスギで、日本海側の多雪地帯に適応した変種であり、下枝が雪に被われ地につくと、そこから発根して独立木になる性質がある。
裏日本に多いのでウラスギとも呼ばれる。
幹の周囲は6.8m、樹高は約28m、枝の広がりを示す樹冠の径は約20mある。
冨士社境内に立つこのスギは樹齢約700年と推定され、冨士社とともにこの地区の歴史を物語る貴重な樹木である。
平成17年3月22日
南砺市教育委員会
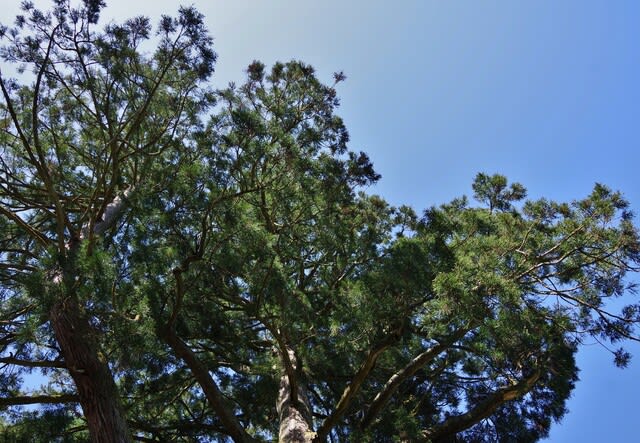


北東側から

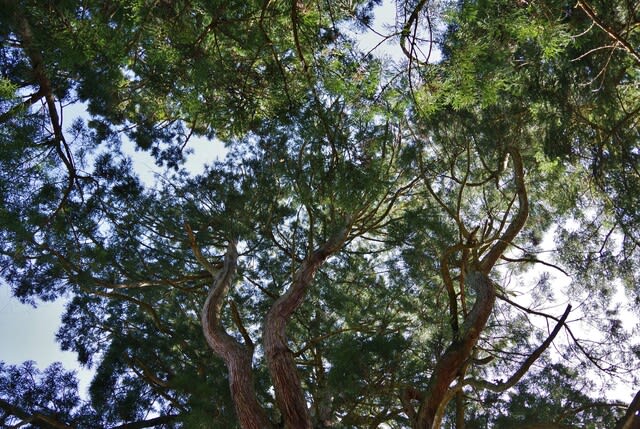


南東側から


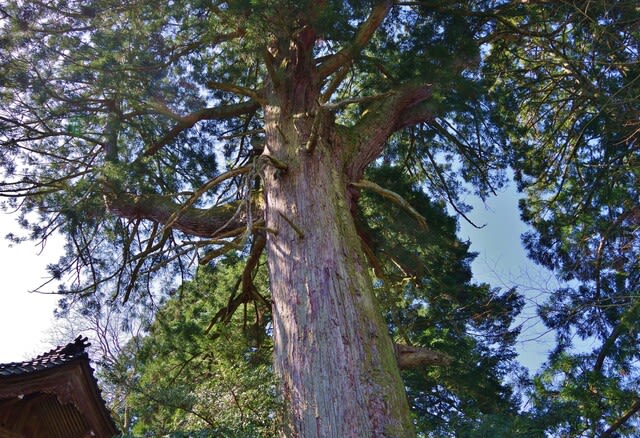

北側から


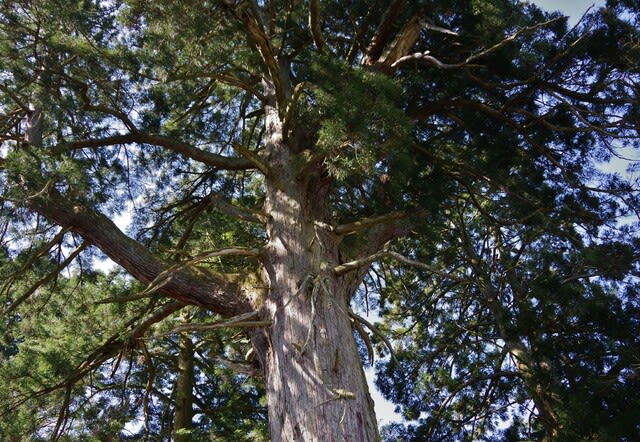

北側道路から

では、次へ行きましょう