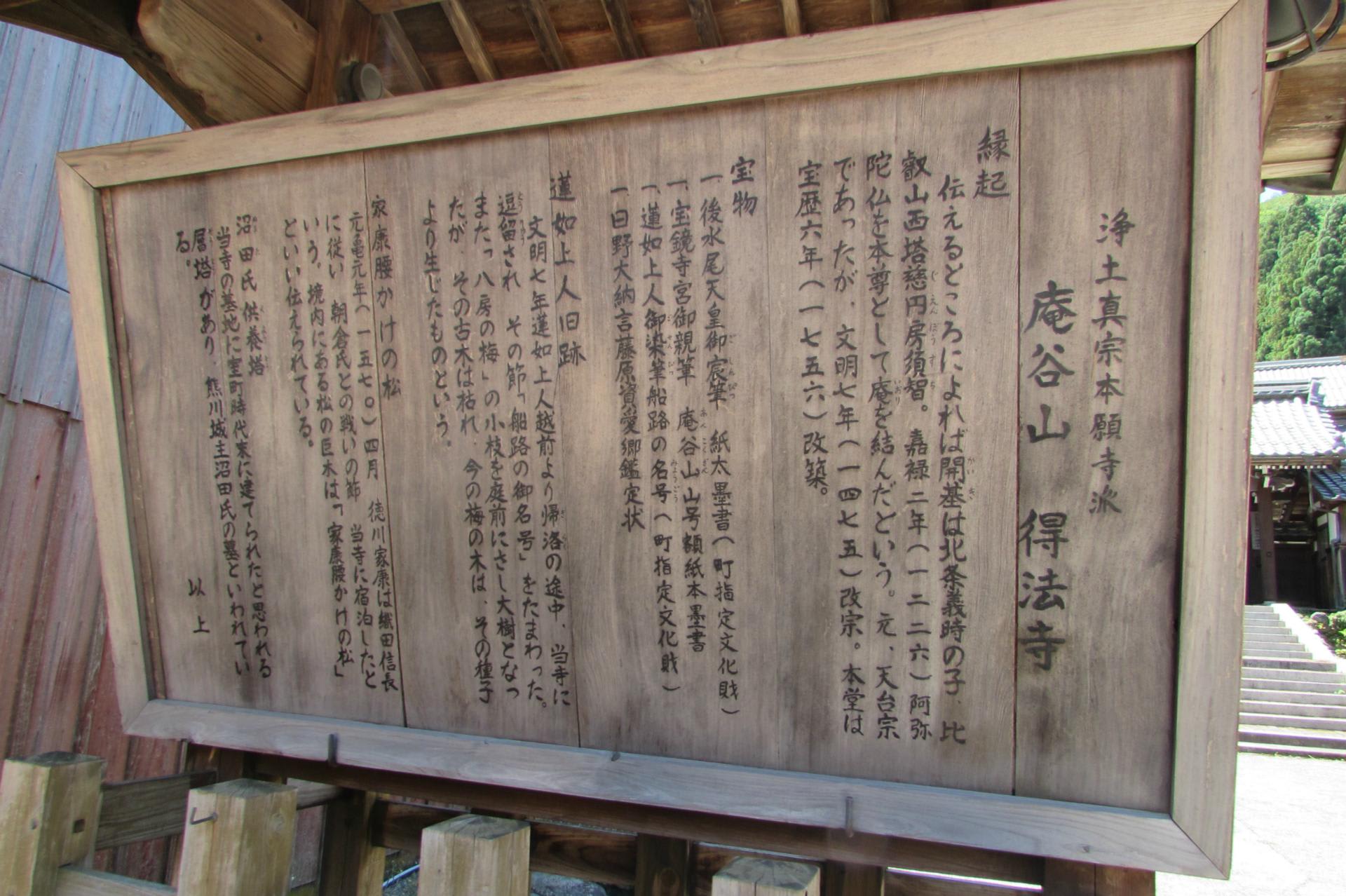2016年6月3日、熊川宿から天徳寺、明通寺、神宮寺、最後にこちらの小浜西組の伝統的建造物群保存地区を散策しました。小浜市街地の西方に位置します。人魚の浜無料駐車場に車を止めて散策です。
map
小浜は福井県の南西部、日本海に面した港町です。古くは日本海側から京への物資の中継地であり、若狭国の政治の中心地でもあった。慶長6年(1601)に京極高次の小浜城築城後町人地が拡大し、貞享元年(1684)に東、中、西の3組に区分された。
保存地区はそのうち西組のほぼ全域で、商家町と茶屋町、寺町からなる。商家と茶屋では建築様式が多少異なっており、茶屋は二階前面に縁や出窓を出す特徴がある。近世城下町の町割を継承し歴史的風致を今日によく伝えています。
ところどころに登録有形文化財の建物が残っています。
マーメイドテラス
「八百日比丘尼の伝説に因み、長寿を願う人魚の像が建つテラス。海に沈む夕日が美しく、絶好の写真スポットとして賑う。」





高鳥歯科医院(登録文化財)
「大正14年の西洋建築物」


八幡神社の鳥居、八幡小路で海鼠壁の土蔵があります。





大鳥居(小浜市指定文化財)















本殿














町並みへ


案内図

資料館










白鳥会館(登録文化財)
「明治22年の西洋建築物。大火を教訓に建てられた元薬店蔵。」







お疲れ様でした。一番西側だったため、肝心の三丁町に行きそびれました。
map
小浜は福井県の南西部、日本海に面した港町です。古くは日本海側から京への物資の中継地であり、若狭国の政治の中心地でもあった。慶長6年(1601)に京極高次の小浜城築城後町人地が拡大し、貞享元年(1684)に東、中、西の3組に区分された。
保存地区はそのうち西組のほぼ全域で、商家町と茶屋町、寺町からなる。商家と茶屋では建築様式が多少異なっており、茶屋は二階前面に縁や出窓を出す特徴がある。近世城下町の町割を継承し歴史的風致を今日によく伝えています。
ところどころに登録有形文化財の建物が残っています。
マーメイドテラス
「八百日比丘尼の伝説に因み、長寿を願う人魚の像が建つテラス。海に沈む夕日が美しく、絶好の写真スポットとして賑う。」





高鳥歯科医院(登録文化財)
「大正14年の西洋建築物」


八幡神社の鳥居、八幡小路で海鼠壁の土蔵があります。





大鳥居(小浜市指定文化財)















本殿














町並みへ


案内図

資料館










白鳥会館(登録文化財)
「明治22年の西洋建築物。大火を教訓に建てられた元薬店蔵。」







お疲れ様でした。一番西側だったため、肝心の三丁町に行きそびれました。