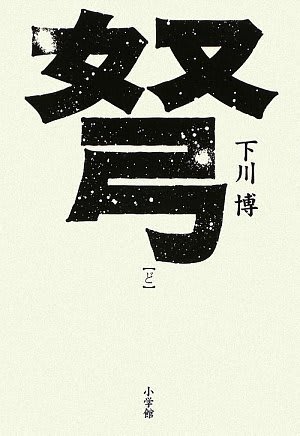 むかしから歴史に関して不思議に思っていたことがある。明治よりも前の、たとえば農民たちは、天皇のことをどれだけ意識していたんだろう。
むかしから歴史に関して不思議に思っていたことがある。明治よりも前の、たとえば農民たちは、天皇のことをどれだけ意識していたんだろう。
税の徴収者である武士のことは、当然意識していなければならないはずだが、しかし京の都に鎮座する天子様のことは?
同僚の社会科教師に素直にきいたら「うーん」と考えこんでしまったので、やはりむずかしい問題なのだろう。
同じことが【士農工商】なる身分制度にも言えて、どの時点からそれは強固なものになったのかがよくわからなかったのだ。
その答の一端がこの小説からうかがえる。塗料に使う柿渋によって財をたくわえた村が、盗賊たちを撃退するためにある方法をとる……「七人の侍」そのままの設定でありながら、むしろめざしたのは荘園経営の破綻などの経済問題。話が経済にあるかぎり、武士とは厄介者にすぎない事実がうまく説明してある。
単なる勧善懲悪なストーリーではなく、極楽浄土の理想を追った僧が、しかし最後に……これは、あるよなあ。
命中率が高く、故に身分の低い者たちにうってつけだった弩(クロスボウ)が日本で一般化しなかった理由が、武器を高貴なものとすることで身分の固定化に結果的に貢献した経緯も納得できる。
元寇によって中国から碧眼紅毛の異人が日本に流入していたとか、手形決済が楠木正成の時代にすでに行われていたとか、お勉強になる作品であり、そしてそれ以上に人間ドラマとしてすばらしかった。ぜひ。















