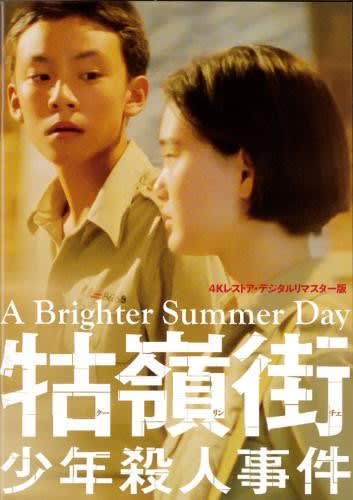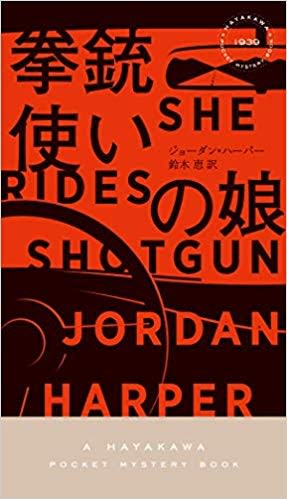
棚の本が“呼んでいる”ってことはないですか。どう考えてもお前向きの本じゃないかと。わたし、呼ばれたんですよこの「拳銃使いの娘」に。
でも、図書館で借りたら返却期限が来てしまい、泣く泣く読まないままで返してしまいました。そしたら年末のミステリランキングを騒がせてやがる。こういうときは悔しいよね。
さあ再チャレンジ。こんな描写が出てきます。
“弾傷のことは昔ニックが教えてくれた。弾をえぐり出すなんてのは、映画の中のでたらめだ。むりにひっぱり出すのは、そのままにしておくより傷によくない。ニックは留置場で聞いた話をネイトにしてくれた。ロサンジェルスの三人組の拳銃強盗の話だ。ひとりが肩に弾を食らい、放っておくと死にそうなほどひどく出血していた。しかし弾傷があると、怪我人を病院へ連れていくわけにいかないから、そいつらはどうしたかというと、獰猛なピットブルを怪我人の肩に食いつかせた。そして犬が弾傷をぐちゃぐちゃのハンバーグにすると、怪我人を犬に襲われたといって病院にかつぎこんだ。この話の教訓は、撃たれるなということだ。”
……やっぱり俺向きじゃないか(笑)。このオフビートさは大好き。
刑務所のなかでボスの弟を殺してしまい、家族全員の抹殺命令が出る中で、11才の娘と強盗しながら逃亡する拳銃使い。モデルになっているのはどう考えても「レオン」。殺し屋ジャン・レノがナタリー・ポートマンを守るお話。娘が実は天才児であるあたりも参考にしたはずだ。書いたのはテレビ業界でヒットを飛ばしている新人ジョーダン・ハーパー。
勢いだけでなく、父親は死んだ兄の言葉で、娘はマスコットの熊を通じてしか親子がなかなかコミュニケートできないあたりの設定もにくい。おすすめですこれ。