
先週のある朝の筑波山麓
■先日来の政府予算の仕分けの件(愚記事;宇野弘蔵と蓮舫 、あるいはやはり、陶酔権干犯問題だった。 )で、深く感じるところがあったので、いろいろ調べてみると、日本は「科学技術立国」どころか研究者養成システムが事実上壊滅しつつあるらしい。それはむしろ、"焼け太り"の反対の、「太り焼け」で。膨張して、陳腐化し、空洞化した。
1990年代の大学院重点化以来大学院の定員を増やしてきた。その一端としてポスドク1万人計画もあった。概算、毎年1万6千人の博士が誕生。一方、大学教官、研究者のパーマネントのポストは毎年高々1万。したがって毎年6000人の博士が余っている(たぶんもっと多い)。これが約10年続いた。現在10万人ほどの非正規教官、非正規研究者がたまってきているらしい。博士が民間への就職したがらない、できないことはいうまでもない。
計算上は、博士課程を修了して、大学の先生に一生なれない「博士」が毎年七〇〇〇人以上誕生していることになる。企業などは、博士号取得者をあまり採用したがらないし、博士課程修了者も、ここまでお金と時間を投資したのだから、「今まで研究したことを生かすべく」というより「無駄にしたくないため」、せめてどこかの大学の先生になりたいと思う。それゆえ、終了後も、非常勤講師や塾講師など不安定雇用に就いて生活費を調達し、研究を続け論文を書きながら、ポストが空くまで何年も待つことになる。このように多数の大学院博士課程修了者がパイプラインから「漏れて」オーバー・ドクターという形で、滞留していく。何年も待ってポストに就ければよい方で、二十年後には、滞留したままラインに乗ることができない中年のフリーター博士が一〇万人を超える規模で出現すると私は予想する。
山田昌弘、『希望格差社会』
参考サイト;
・ 大学・公的研究機関等における ポストドクター等の雇用状況調査 ― 平成18年度調査 ―
・pdf 理系白書 ポスドク
・1972年の...OD問題に憶う ---土方克法
■ポスドク問題の主要はバイオ・ポスドク問題。
上記、山田昌弘、『希望格差社会』の話は文系、理系あわせた博士修了者総体の話である。少し、分析的に考えて、理系のポスドク問題を見る。統計をみるとポスドク(総数16000人)のうち半分近くが、バイオ系なのだ。6000人くらいらしい(#1)。つまり、ポスドク問題、ポスドク問題というが、実態は,なぜバイオ系ポスドクは"不幸"なのか?問題ということになる。
なぜ、バイオ分野でこれだけ増えたのかは、21世紀はバイオの世紀!とかの宣伝があったらしい。なぜ、そういう宣伝が行われたのか?は知らない。こういう顛末もあった;バイオテクノロジー戦略大綱の破綻。
6000人が滞留しているのだ。今話題の仕分け作業による科学技術への政府支出問題がなくても、すなわち、COEとかGCEOやPDの予算が減らされなくとも、この先5年、10年この6000人のうち研究者になれるのは何割かである。何年も待ってポストに就ければよい方で、二十年後には、滞留したままラインに乗ることができない中年のフリーター博士になるしかないだろう。バイオ・ポスドクの民間企業への就職は3重の意味で困難である。
1) そもそもバイオ産業が少ない。
2) 日本産業社会の問題;
日本社会とは「コンパートメンタライゼーション=縦割り」がきわめて強い社会だという紛れもない事実である。三〇歳まで「生業」につかなかった人間を受け入れる場などまったくない。(潮木守一、『職業としての大学教授』)
3) バイオ系の研究が、多量の 行き当たりばったり 試行 思考 錯誤的実験をこなすという性格を持ち、バイオ研究者が必ずしも数学、物理、化学の基礎素養を身につけていないことが、バイオ以外の他の産業分野への就職を困難にしている。(要は、wiki ピペド問題、アンサイクロペディアピペット土方)
ひたすら「科学技術立国」のために予算をつけろという"短絡的"な議論はまぬけだ。科学⇒真理⇒いいこと⇒神聖にして犯すべからず⇒問答無用⇒金出せ!というメンタリティにはびっくりする。歴史の法廷に立つ覚悟ができているのか!とかよく言うよな。さらに、むしろ、税金のことより、多くの若者の人生を"無駄"にしていることが問題だ。人の人生を考えた"研究ガバナンス"こそ必要である。今回の仕分けが前途ある若い人々に現状認識の機会となったとすれば、そのことが成果である。
■学生に周知を。
とにかく、この現状を学生に知らせる必要がある。無責任に大学院に進学させ、その学生の人生を棒にふらせてはいけない。 (おとろしいことに、こういう報告もある⇒ 「メーリングリストなんかで、やってることを知ったという人?」と聞いたら半数ぐらいに増えた。 残りは…ひょっとして無関心?)
こういう状況なのに、私はむしろ博士課程の学生の数は維持しつつ、博士号取得者の就職先を拡大するように、大学院教育を変えていくのが正しいと考えている。基本的には、高度な教育をうけて、高い専門能力、幅広い視野、広い教養をもった人間が社会に多くいることはよいことだと思うからである。だから、問題は大学院で研究者以外のキャリアでも有効であるような教育がなされていないことだ。(Cerebral secreta: 某科学史家の冒言録■[大学]博士は募集停止すべきか?)と主張している大学教官もいる。
(この教官は、 「ほかの教員が是非、総研大へ来てください、と言っているところに、私だけ、博士号をとっても就職先がないので、進路決定は慎重に、などと言ったりするわけだ。ほかの先生方はいったい生命系の博士の就職状況をどれだけ理解しているのだろうか?おそらく生命系でも分野によって事情が違うのだろうと思われるが。」とも言っている。その整合性が不明。)
こういう意見に対し、山田昌弘は「過剰な教育」を批判している。つまり、数字の問題として過剰であると。さらに、おいらが考えるに、「博士号取得者の就職先を拡大する」というのは論理的ではあるが、それは現実を全く無視している判断であるといわざるを得ない。できもしないことを根拠に若者を唆してはいけない。ポスドク1万人計画の始まる前に目指していた目的(それは、絵空事であったということは残念なことだ)と今の現実のギャップに対する認識がない。ただし、やはり、「高い専門能力、幅広い視野、広い教養をもった人間が社会に多くいることはよいこと」ではある。しかし、「高い専門能力、幅広い視野、広い教養」は実社会の職業人にはそれほど求められていない。いわば、趣味なのである。
もっとも、中年のフリーター博士になったのは才能のないヘタレなダメなやつ、俺様はちがうんだとか、あるいは、たとえ中年のフリーター博士になろうとも、サイエンスにいささかでも貢献ができればそれで幸せというツワモノの若者にはどしどしがんばってほしい。


歴史の法廷が 立っちゃいました。@被告志願=defence, 上等だ!
召喚(よんで)ます。
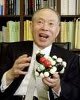
非・自省派@動物化するポストモダン!
歴史の法廷に立つ覚悟ができているのか!(人間の定義)って言うけど、
自分が一番、歴史意識が希薄(=動物=スノビズムとしてのサイエンス⇒とにかく金出せ!⇒すなわち、鈴木宗男)。
#1;ポストドクター等の雇用状況調査 ― 2006年度実績 ―
ライフサイエンス、ポスドク数6459人、ポスドク全体の全体の39.4%.









